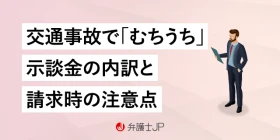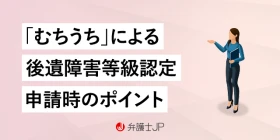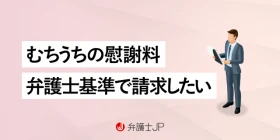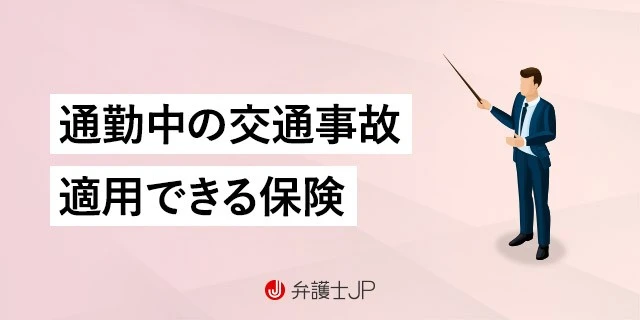
通勤中の交通事故には労災保険を使う? 自賠責・任意保険との併用も?
労災保険給付は勤務中の事故のみならず、通勤中の交通事故にも適用できます。ですが交通事故では通常、加害者が加入する自動車保険から賠償金が受け取れます。そのため、労災保険を使うべきか、迷う方もいます。
では通勤災害においては、自賠責・任意保険と労災保険は併用するべきなのでしょうか?
1. 通勤中の交通事故には労災保険を使うべきか?
通勤中の交通事故は、労災保険の適用対象です。ここでは併用時の注意点や併用のメリットなどをご説明します。
(1)労災保険と自賠責・任意保険は併用可能
一般的に歩行中や車の運転中に交通事故に遭った場合、被害者には加害者が加入している任意保険から治療費や休業損害、慰謝料などの保険金が支給されます。加害者が任意保険に未加入の場合は、自賠責の範囲内で補償を受けられます。
加えて交通事故が通勤中や仕事での移動中に起きた場合には、通勤災害として労災保険の対象にもなります。労災保険は事業主に加入義務があり、会社や労働者本人が申請すれば、保険を適用できます。
このように自賠責・任意保険と労災保険はまったく別の保険なのです。そのため一つの事故に対して併用することが可能です。
(2)併用時の注意点
保険を併用する場合、注意しなければいけない点があります。それは費目が重なった場合の「支給調整」です。
労災保険と自賠責・任意保険の補償内容の多くは重なっています。たとえば事故によるケガで仕事ができなくなった場合に適用される、労働災害の「休業補償給付」と、任意保険の「休業損害」です。
両方から同じ目的の補償を受け取れば、二重払いです。そこで重なる項目についてはどちらか一方だけが適用されるように「支給調整」が行われるのです。
保険のパンフレットなどに目安金額が書いてあったとしても、両方から満額もらえるわけではありません。
(3)労災保険を使うメリット
支給調整が行われるのであれば、加害者からの保険金だけでいいと考える方もいるでしょう。ですが労災保険を使うことにはメリットがあります。
①重複していない補償を受け取れる
労災保険と自賠責・任意保険の補償内容には、重複していない部分もあります。中でも大きいのが労災保険の「特別支給金」です。
特別支給金は通常の補償とは違って福祉的な観点から支給されるもので、見舞金のような役割があります。これは自賠責・任意保険には存在しません。
逆に「慰謝料」は労災保険にはありませんが、自賠責・任意保険にはあります。
併用することでこれら重複していない部分の給付を受けることができ、保険金の総額がアップします。
②労災保険の方が手厚いケースがある
労災保険と自賠責・任意保険は給付額や算出の方法が違うため、労災保険の方が、補償が手厚いケースがあります。
たとえば事故の発生に対して被害者に一定の過失がある場合、自賠責や任意保険では過失割合に応じて治療費が減額されますが、労災保険にはその仕組みはないため、全額支払ってもらえます。
③前払一時金が使える
労災保険の障害補償年金や遺族補償年金には「前払一時金制度」があります。これは本来受け取れる総額のうち、一部を前払いで支給してもらう仕組みです。
利用することで得をするわけではありませんが、事故で家族が亡くなるなどした場合、さまざまな支払いや生活費のために、まとまったお金が必要になることがあります。そういった場合に役に立つでしょう。
2. 労災保険と自賠責・任意保険を併用できるケース
労災保険は労働者全員が利用できるわけではありません。労災保険と自賠責・任意保険の両方が使えるのはどのようなケースか、確認していきましょう。
(1)保険の併用ができないケース
労災保険は、すべての事業主に加入義務があります。ただし「労災保険の保険料を支払いたくない」「支払う余裕がない」といった理由で、労災保険に加入していない会社もあります。その場合には、通勤災害に対して労災保険の適用を申請できません。
また交通事故で労災を使えば必ず労災保険料が上がると思い込み、労働基準監督署に報告せず、事故の発生自体を隠してしまう会社もあります。いわゆる労災隠しです。会社が労災申請をせず、労働者も何もしなければ給付金は受け取れません。
(2)保険の併用ができるケース
労災保険に加入していて会社がきちんと労災を申請してくれる場合、また加害者が自賠責・任意保険に加入している場合は、被害者本人が希望すれば併用は可能です。
ただし、先ほどご説明したように支給調整はされるため、どちらを優先して適用するかはよく検討する必要があります。
労災保険と自賠責・任意保険のどちらを先に手続きすべきかわからない、会社が労災保険に入っていない、保険会社との交渉が決裂し示談できないなど、通勤災害をめぐるトラブルはすぐに弁護士に相談しましょう。弁護士が補償内容について検討し、アドバイスしてくれます。
- こちらに掲載されている情報は、2022年11月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

交通事故に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年07月14日
- 交通事故
-
- 2024年07月11日
- 交通事故
-
- 2024年07月03日
- 交通事故