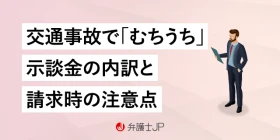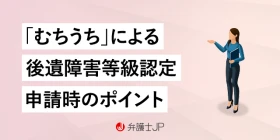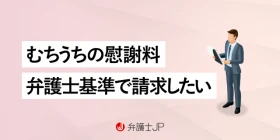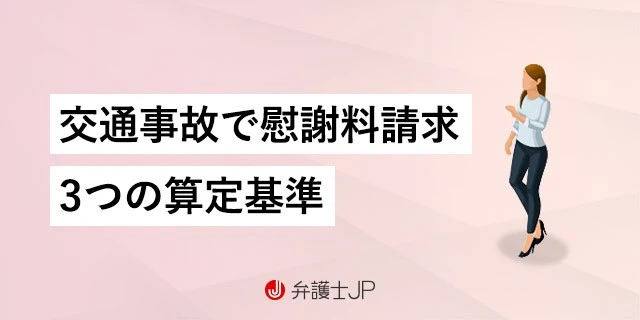
交通事故の被害者は知っておくべき弁護士基準(裁判所基準)の重要性
交通事故の被害に遭ってケガをした方は、加害者に対して慰謝料や治療費といった内容の損害賠償を請求することができます。請求できる慰謝料の計算方法について調べていたら、「弁護士基準」というフレーズを見聞きすることがあるのではないでしょうか。
今回は、この「弁護士基準」の意味や重要性を解説します。損害賠償請求の流れや受け取り時期についてもあわせて確認しましょう。
1. 交通事故の慰謝料とは
交通事故でケガをした被害者は、加害者に対して、自身に生じた損害の賠償請求をすることができます。その1つが慰謝料です。慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。
交通事故における慰謝料の種類は以下の3つです。
(1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)
ケガをして通院や入院をしたときの慰謝料です。入通院日数や治療期間に応じて算定されます。
(2)後遺障害慰謝料
後遺症が残ってしまって、後遺障害等級が認定された場合に請求できる慰謝料です。後遺障害等級が認定されれば、傷害慰謝料とは別に支払われます。
(3)死亡慰謝料
被害者が亡くなってしまったときに相続人が受け取れる慰謝料です。死亡した本人固有の苦痛と近親者が被る精神的苦痛への慰謝料が含まれます。
2. 慰謝料以外にも請求できる賠償金
慰謝料はあくまでも損害賠償金の一部です。交通事故でケガをした場合の賠償金には次のようなものがあります。
- 治療費
- 通院交通費
- 付添費用
- 休業損害
- 後遺障害の逸失利益
3. 慰謝料算定の3基準、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)
慰謝料の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準が用いられます。
それぞれの特徴や違いは以下の通りです。
(1)自賠責基準
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)から支払われる際の基準です。3つの中でもっとも低く設定されている算定基準で、十分な慰謝料を受け取れるものとはいえません。しかしながら、被害者が加害者側の保険会社と直接交渉をした場合には自賠責基準が適用されることがほとんどです。
自賠責基準の慰謝料は、実際の通院日数を2倍したもの、もしくは通院期間のいずれか少ないほうに4300円をかけて算出されます。
(2)任意保険基準
保険会社が独自に定めた基準です。任意保険会社が独自で設定している基準ですので、会社によって若干の差はあるものの、自賠責基準と大きな違いはありません。自賠責保険の限度額を超えて、任意保険から賠償金が支払われる場合に任意保険基準が適用されます。
(3)弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準は、過去の判例や裁判所の考え方をもとに定められた基準です。事故の実態に即しており、妥当性の高い基準となります。3つのうちもっとも高い水準であり、自賠責基準の2倍から3倍の金額になることも珍しくありません。
4. 交通事故によるケガで、弁護士基準で慰謝料を算定するとどうなるのか
交通事故のケガの慰謝料を弁護士基準で算定した場合と、自賠責基準で算定した場合を比較してみましょう。
(1)むちうちで、通院日数30日、治癒まで90日の場合
このケースを上記の自賠責基準で計算した場合、治癒までに通院した日数30日を2倍したものに4300円をかけたものが、慰謝料の総額となりますので25万8000円です。
一方で、弁護士基準の場合、53万円が基準となります。このように、同じケガであっても弁護士基準になるだけで金額に大きな差が出るケースが大半です。
5. 被害者自身で、弁護士基準で算定された慰謝料を請求することは難しい
弁護士基準での交渉に相手方の保険会社が応じるのは、最終的に裁判を起こすことのできる弁護士が交渉するからです。ご自身で交渉をしても、保険会社が弁護士基準で対応してくれる可能性はかなり低いです。
自動車保険や火災保険に、弁護士特約が付いている場合は、特約から弁護士費用が支払われます。弁護士費用特約の上限は、多くの保険会社で300万円となっておりますので、大半のケースで、自己負担なく弁護士への依頼が可能です。ご自身が加入していなくても、同居の家族や配偶者が加入していれば、弁護士費用特約を利用可能な場合も多いです。
加入していない場合に、弁護士費用を考慮してもトータルでプラスになるケースも多くありますので、まずは無料相談等を利用して、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年06月16日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

交通事故に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年07月14日
- 交通事故
-
- 2024年07月11日
- 交通事故
-
- 2024年07月03日
- 交通事故