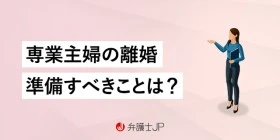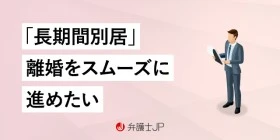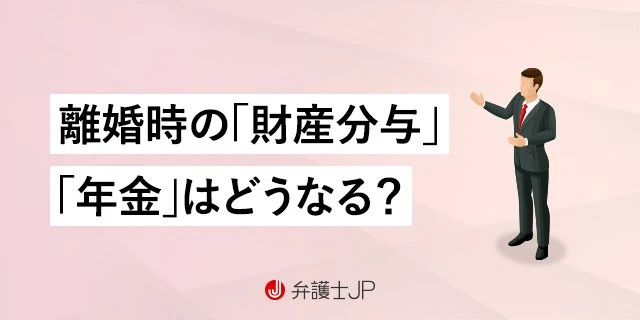
離婚時の「3号分割」年金の分割はどのようにすれば良い?
離婚時の話し合いでは、貯金や持ち家の財産分与については考えていても、「年金分割」は見落としがちです。
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」があり、適用条件が異なります。
今回は、主として3号分割について、その仕組みや請求方法、注意点を解説します。
1. 離婚時の年金分割について
離婚をすると、その後の生活は自分でやりくりしていかなければいけません。ですが、収入や貯蓄がないため、老後の生活に不安を抱く方もいるでしょう。そこで、離婚時にしっかり決めておきたいのが、年金分割です。
(1)年金分割制度とは
年金分割制度とは、結婚生活を送っていた期間の厚生年金・共済年金記録(標準報酬月額と標準賞与額)を、離婚時に夫婦で分割する仕組みです。
夫が会社員で、妻が結婚後ずっと専業主婦であった場合、夫は老後に「厚生年金+国民年金」を受け取れますが、妻は「国民年金」しか受け取れません。その状況で離婚した場合、元妻は生活に困る可能性があります。
そこで、夫婦間格差を是正するために、平成19年4月、結婚していた期間の厚生年金・共済年金保険料は夫婦が協力して納付したものと考えて年金記録を分割する「年金分割制度」がスタートしました。
(2)年金分割制度の対象
分割できるのは厚生年金と共済年金だけで、国民年金や国民年金基金、厚生年金基金は対象外です。つまり結婚後、夫婦がともに国民年金に加入していた場合には利用できません。
なお、法律婚の夫婦だけでなく、事実婚の夫婦についても、関係を解消した場合には請求することが可能です。
2. 3号分割とは?
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。利用対象者などの違い、選び方についてご説明します。
(1)合意分割とは
合意分割とは、婚姻期間中の厚生・共済年金記録を夫婦で分割する仕組みです。合意分割という名前の通り、両者が分割と按分割合に合意していることが利用の前提です。
主な利用条件と特徴は以下の通りです。
- 平成19年4月1日以降に離婚が成立
- 夫婦間の合意が必要。合意がない場合は裁判手続きにより按分割合を決定
- 按分割合は、標準報酬総額の2分の1以下の範囲内において合意で定める割合
- 婚姻期間中すべての厚生・共済年金記録が対象
- 請求期間は、離婚の翌日から2年以内
按分割合は、上限に収まり、かつ年金分割の合意により年金分割を受ける側が自らの標準報酬額を減額されない範囲であれば、自由に定めることができますが、一般的には2分の1です。
合意分割を利用するためには、相手方の同意が必要となり、夫婦の一方が勝手に請求することはできません。
(2)3号分割とは
3号分割とは、国民年金の第3号被保険者になっていた期間について、その期間中の配偶者の厚生・共済年金記録を分割する仕組みのことです。
利用条件と特徴は以下の通りです。
- 平成20年5月1日以降に離婚が成立
- 分割対象は平成20年4月1日以降で、国民年金の第3号被保険者だった期間の配偶者の厚生・共済年金記録
- 夫婦間の合意は不要
- 按分割合は、標準報酬総額の2分の1
- 請求期間は、離婚の翌日から2年以内
「第3号被保険者」とは、厚生年金または共済組合加入者の被扶養配偶者で、年収130万円未満、20歳以上60歳未満の国民年金加入者のことです。保険料は厚生年金や共済組合が負担しているため、第3号被保険者自身は払っていません。
3号分割は、第3号被保険者期間があることが利用の前提となっているため、共働きで互いに厚生年金に加入している場合は、対象外となります。
対象となるのは、平成20年4月以降の年金記録分のみであり、それ以前の年金記録を分割したい場合、合意分割を併用する必要があります。
ただし、婚姻中に会社員として働き厚生年金保険に加入し、一時期、国民年金の第3号被保険者だったといった場合は、合意分割を請求することで、3号分割も同時に請求されたと判断されます。
3号分割の場合、合意分割と異なり、年金事務所に対して年金分割を請求するに際し、相手の同意は不要であり、第3号被保険者が請求すれば利用できるため、手続きとしては簡便です。
3. 3号分割の請求手続き
3号分割は、国民年金しか加入しておらず、老後の収入源に不安がある方にとって、生活を支える大事な制度です。請求をする場合には、以下を参考にして手続きをしてください。
(1)手続きの流れ
3号分割の請求は、次の書類をそろえて年金事務所に申請します。
- 3号分割標準報酬改定請求書
- 請求者の年金番号またはマイナンバーがわかる書類
- 婚姻期間がわかる書類(戸籍謄本など)
- 1か月以内に作成された2人の生存がわかる書類(住民票など)
(2)3号分割請求の注意点
自分が3号分割の対象者であるかどうかは、年金事務所に問い合わせて確認しましょう。年金分割の対象期間や、将来受け取れる年金の見込額を確認したい場合には、年金事務所に「年金分割のための情報通知書」や、「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」の発行を頼んでください。
なお、年金分割のための情報通知書は、離婚前であれば、相手の同意がなくても、夫婦の一方で請求・受領することができますが、離婚後に請求した場合、相手方にも同じ通知が届いてしまいます。分割請求をしようとしていることが相手に間接的に伝わってしまうため注意してください。
また、年金分割の請求には、「離婚の翌日から2年以内」という期限があります。そのため、離婚時に財産分与などの離婚条件を決める際に、併せて考えておくのがよいでしょう。請求期限が迫っている場合や、相手と揉めている場合には、弁護士に相談してください。
- こちらに掲載されている情報は、2022年12月22日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年03月17日
- 離婚・男女問題
-
- 2023年02月27日
- 離婚・男女問題
-
- 2021年12月15日
- 離婚・男女問題