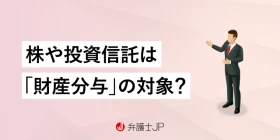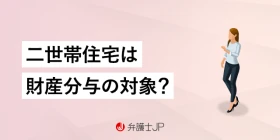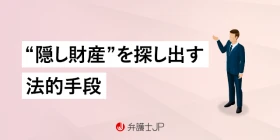離婚における財産分与、家や住宅ローンはどのように扱われる?
マイホームは、「人生で一番高い買い物」と言われることもあります。離婚における財産分与では、価値が高いものの簡単に分けることができない「家」や、その家を購入するために組んだ「住宅ローン」の扱いが問題になることも少なくありません。
この記事では、財産分与における「家」や「住宅ローン」の扱いについて紹介します。
1. 家は財産分与の対象になる?
(1)財産分与の対象
離婚における財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産である「共有財産」を分ける手続きです。
「共有財産」は、婚姻期間中に夫婦が築いた財産であり、実質的に夫婦が共有する財産であればよく夫婦の共有名義である必要はありません。たとえば、夫婦の一方を名義人とする銀行口座や不動産であっても、婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産であれば共有財産として財産分与の対象になります。
一方で、夫婦それぞれの固有の財産である「特有財産」は財産分与の対象にはなりません。具体的には、婚姻前に取得していた財産や婚姻中に親からの贈与や相続で得た財産などが「特有財産」にあたります。
(2)家が共有財産なら財産分与の対象になる
持ち家が夫婦が婚姻期間中に貯めたお金で購入したものである場合には、共有財産とみなされて財産分与の対象になります。その際、不動産の名義人が夫婦の共有名義であるか夫婦の一方の名義であるかは問題になりません。
ちなみに、家の購入に際して婚姻前に貯めたお金を頭金として支払ったり、親から資金を援助してもらったりしているような場合には、家の一部に特有財産が含まれる、という扱いになります。特有財産が含まれているときにはその分を差し引いて財産分与を考える、などの対応が必要になるのです。
(3)家の財産分与の方法
持ち家が財産分与の対象になる場合には、多くのケースでは、離婚に伴って「売却する」、または「一方が住み続ける」という方法がとられることになります。
住宅ローンを組まずに家を購入したり住宅ローンをすでに完済していたりするような場合には、財産分与は比較的シンプルに考えればよいことになります。しかし住宅ローンが残る家が財産分与の対象になる場合には、よく検討して対処する必要があるのです。
2. 住宅ローンがある家はどのように扱われる?
(1)売却する場合
家を売却する場合には、不動産売却によって金銭的な数字に換価されるため処理しやすいといえます。住宅ローンの残る家を売却した場合には、まず売却代金を住宅ローンの返済にあてます。そして余ったお金があれば財産分与として夫婦で分け合う、という扱いができます。
しかし、売却代金が住宅ローンの返済額より安かった場合には、返済できなかった分は債務として継続して残ります。そして、ローンの名義人は離婚後も返済義務を負うことになるのです。この残債務の返済義務は、財産分与の対象にはならず名義人のみが負うものになります。
(2)一方が住み続ける場合
離婚後も家に住み続ける場合、夫婦の一方が住宅ローンの名義人であれば、離婚後もそのまま自分で返済していけばよいのですから、あまり問題は生じません。しかし住宅ローンの名義人ではない一方が家に住み続けるケースや、共有名義の家に一方が住み続けるケースでは、複雑な問題が生じる可能性があります。
たとえば、夫名義で借りた住宅ローンの返済が残っている家について、妻が財産分与で取得することになった場合を考えてみましょう。
この場合、妻としては自分は家に住み続けながらも夫が住宅ローンの返済を続けてくれることが最もありがたいでしょう。ところがそうなると、離婚後に夫の返済が滞れば家に設定されている担保権が実行され、妻が自分の住む家を失うリスクが生じるのです。
では、住宅ローンの債務者を夫から妻に名義変更すれば解決できるのかというと、そう簡単にはいくものでもありません。なぜなら、住宅ローンの債務者になるためには金融機関の承認が必要になるためです。
金融機関としては、妻に夫と同程度以上の収入(返済能力)がなければ、名義変更を認めるメリットはありません。そのため、金融機関の承認を得ることが難しいケースも少なくありません。別の金融機関からの借入も検討しますが、これも難しいことが多いです。
また夫婦の共有名義の住宅ローンを組んでいる場合には、内部的な負担関係として住み続ける方が全部を支払うという合意をすることも考えられるところではありますが、家を離れる方も金融機関との関係では債務の負担は免れませんので、住み続ける方が支払わなくなった場合には、家を離れる方が住んでいないにも関わらず多額の債務を負うリスクがあるのです。
このようなリスクを回避するためには、金融機関と交渉して債務者から外れることができればベストといえますが、簡単には認めてもらえません。金融機関としては、「夫婦が揃って返済する」という約束でお金を貸しているために、債務者が減ることは、返済してもらえないリスクが高まるということにつながるのです。
このように一方が家を取得して住み続けるという選択は、難しい問題を伴うことも少なくありません。そのため、状況に応じて不動産売却するなどの判断も必要になるといえるでしょう。
持ち家は夫婦が所有する財産のなかでも特に高額なものであるために、家の財産分与をどうするかということは、離婚における手続きのなかでも重大な事項となります。持ち家がある夫婦が離婚をする際には、弁護士に相談することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2022年02月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年05月03日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年03月22日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年01月22日
- 離婚・男女問題