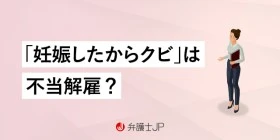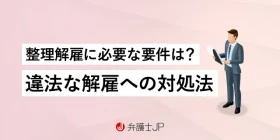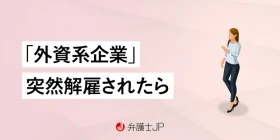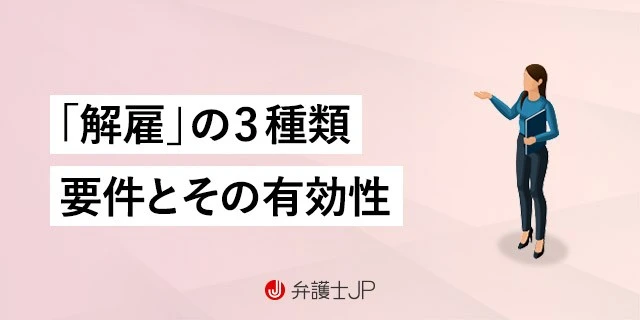
突然解雇を告げられた……その種類は? 正しい方法・手続きなのか
解雇とは、労働者の意思とは関係なく、使用者の一方的な意思によって労働契約を終了させることをいいます。会社から突然解雇を告げられたとしても、思い当たる理由がない方は、どのように対応したらよいかわからずとても困惑することでしょう。
解雇には、大きく分けて3つの種類があり、それぞれの解雇の種類に応じて解雇の要件、方法、手続きなどが異なってきます。不当解雇であるとして争うためにも、どのような種類の解雇であったのかが重要になります。
今回は、解雇の種類ごとに、その内容、方法、手続きなどを解説します。
1. 解雇の種類
解雇には、大きく分けて(1)普通解雇、(2)懲戒解雇、(3)整理解雇の3種類があります。以下では、それぞれの解雇の内容について説明します。
(1)普通解雇
普通解雇とは、懲戒解雇と整理解雇以外の解雇のことをいい、労働者が労働契約上の義務に違反したことを理由として労働契約を解除するものです。
普通解雇の理由となるものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 能力不足、成績不良、適格性の欠如
- 職務怠慢、勤怠不良
- 体調不良、病気、ケガによる就業不能
- 職場規律違反、業務命令違反
(2)懲戒解雇
懲戒解雇とは、労働者に重大な職務規律違反や悪質な非違行為などがあった場合に、懲罰としての懲戒処分としてなされる解雇のことをいいます。懲戒処分には、軽いものから、戒告、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇(諭旨退職)、懲戒解雇があります。懲戒解雇は、懲戒処分のなかでももっとも重い処分として位置づけられています。
懲戒解雇の理由となるものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 会社の経費を流用するなどの横領行為をした場合
- 度重なるセクハラやパワハラによって職場の風紀を著しく乱した場合
- 会社の名誉や信用を著しく害する犯罪行為をした場合
(3)整理解雇
整理解雇とは、会社の業績悪化などの経営上の理由から行う解雇のことをいいます。整理解雇では、普通解雇や懲戒解雇のように、労働者側の落ち度は問題にはならず、労働者側に何ら落ち度がない場合であっても会社側の都合で解雇を行うものです。
整理解雇の理由となるものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 業績悪化による人件費削減
- 事業所、部署の閉鎖を理由とする解雇
- 会社の倒産に伴う解雇
2. 解雇するための条件
使用者が労働者を解雇する場合には、解雇の種類によってその要件や手続きなどが異なってきます。以下では、解雇の種類別の要件と手続きについて説明します。
(1)普通解雇
使用者が労働者を普通解雇するためには、解雇をすることに客観的に合理的な理由があり、解雇が社会通念上相当と認められることが必要になります(労働契約法16条)。普通解雇の有効性は、一般的には、就業規則などに解雇事由が規定されていますので、労働者の行為が解雇事由に該当するかどうかという面と解雇事由に該当するとしても解雇を選択することが相当であるかという面から審査されることになります。
これらの要件を満たした場合には、有効に普通解雇を行うことができますが、普通解雇の手続きとして、30日前に解雇予告をするか30日分の解雇予告手当を支払うことが必要になります(労働基準法20条)。
(2)懲戒解雇
使用者が労働者を懲戒解雇するためには、上記の普通解雇の要件(労働契約法16条)に加えて、懲戒処分の要件も満たす必要があります(労働契約法15条)。
懲戒処分は、労働者に与える不利益が大きいことから、根拠となる懲戒事由や処分の内容が就業規則などに明記されていなければなりません。
そして、懲戒解雇を有効に行うためには、就業規則上の懲戒事由に該当する事実があるかどうかという面と懲戒解雇という処分が行為内容や勤務歴などに照らして重すぎないかどうかという面から審査されることになります。
懲戒解雇をする場合であっても、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要になりますが、例外的に「労働者の責に帰すべき事由」によって解雇をする場合には、労働基準監督署長の認定を受けることによって、解雇予告および解雇予告手当の支払いが不要になります(労働基準法20条1項ただし書)。
なお、懲戒解雇の場合には退職金を不支給または減額する規定がある場合には、懲戒解雇の理由によっては退職金が不支給または減額になることもあります。
(3)整理解雇
整理解雇は、労働者に非がない状況で会社側が一方的に労働契約を終了させるものですので、その有効性は、普通解雇や懲戒解雇よりも厳格に判断されることになります。
整理解雇の有効性については、以下の要素を総合考慮して判断されることになります。
①人員削減の必要性
人員削減の必要性とは、企業経営上、人員削減措置がやむを得ないといえることまたは十分な必要性に基づいていることをいいます。
②解雇回避努力
解雇回避努力とは、解雇以外の人員削減方法(残業削減、配転、出向、希望退職者募集、一時休業など)によって解雇を可能な限り回避することをいいます。
③人選の合理性
人選の合理性とは、客観的かつ合理的な選定基準を定め、それを適切に運用して対象者を選定することをいいます。会社が恣意的に対象者を選定することは認められません。
④手続きの妥当性
手続きの妥当性とは、使用者が労働者または労働組合に対して、整理解雇の方針、手続き、規模、条件など説明を行い、真摯に協議することをいいます。
- こちらに掲載されている情報は、2022年05月29日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年06月14日
- 労働問題
-
- 2023年04月24日
- 労働問題
-
- 2023年02月28日
- 労働問題