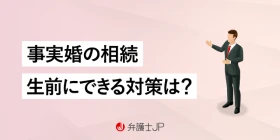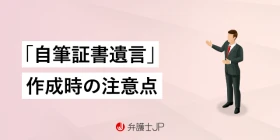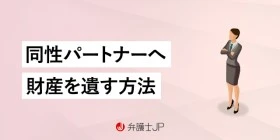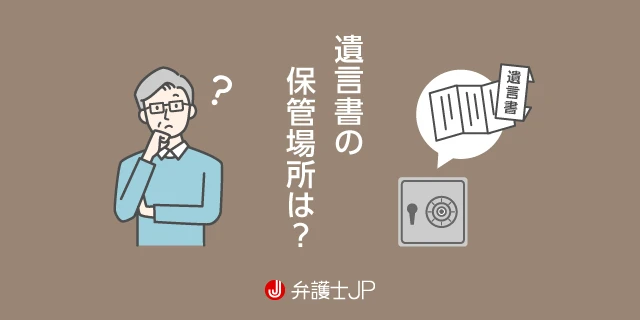
- (更新:2023年01月31日)
- 遺産相続
遺言書の保管場所はどこにすべき? 遺言書の種類を踏まえて解説します
遺言書を作成するときは、その内容はもちろんのこと、保管場所についても慎重に検討する必要があります。
そこで、遺言書を作成したあとの保管場所はどのようなものがあるのか、遺言書の種類を踏まえながらご説明します。
1. 遺言書の法的位置づけ
遺言書とは、ご自身が亡くなった際に開始する相続において、ご自身の意思を実現するために大切なものです。また、相続開始後に、ご遺族が遺産分割をめぐってトラブルになることを防止できる効果も期待できます。
ところが、せっかく遺言書を作成しても、保管場所次第では相続人や第三者に遺言書を破棄されたり、内容を改ざんされてしまうおそれがあります。その結果、ご自身の意思が反映されない相続になったり、作成した遺言書そのものが法的に無効となってしまうこともあります。
遺言書が意味を持つのは、ご自身が亡くなり相続が開始したときです。当然ながら、死後に相続人や遺言書をご自身の意思に沿って動かすことはできませんから、遺言書の破棄や改ざんを防ぐために、相続が発生するまでの遺言書の保管場所については、慎重な配慮が必要です。
2. 遺言書の保管場所は、公的なものと私的なものがある
(1)公的な保管場所
①法務局
法務局が保管する遺言書は、「自筆証書遺言」とよばれるものです。自筆証書遺言は、財産目録をのぞく本文を、遺言者ご自身が自筆で作成するものです。そして法務局は、「自筆証書遺言書保管制度」に基づき、自筆証書遺言について、形式面の確認を経たうえで保管します。
この制度を利用して法務局に保管している場合、相続開始後に、法定相続人が法務局に、必要書類を用意して問い合わせれば遺言書を発見することができますので、相続人がこの制度を知っていれば、遺言書にたどり着くことができるでしょう。
②公証役場
公証役場が保管する遺言書は、「公正証書遺言」です。公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもとに、遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。そして作成された公正証書の謄本は、公証役場で保管されます。公正証書遺言は公証人により作成されますので、形式の誤りが発生する可能性は極めて低いと考えてよいでしょう。
公正証書遺言の場合、相続開始後に、法定相続人が必要書類を用意して公証役場に問い合わせれば遺言書を発見できますので、相続人が遺言書を発見しやすい手続きと言えます。
自筆証書遺言書保管制度の活用も公正証書方式による遺言書作成も、保管や作成のための費用がかかります。しかし、いずれも遺言書を法務局や公証役場という公的な第三者が保管するため、相続人や第三者に破棄されたり改ざんされる可能性は極めて低くなりますので安心です。
(2)私的な保管場所
①自宅
自筆証書遺言を作成される方の多くは、自宅に保管されています。
しかし、自宅に保管している場合、生前に家族に知られないような場所に保管していると死後も気づかれず、わかりやすい場所に保管していると遺言書の破棄や改ざんを受けやすいという問題があります。
②法律事務所や信託銀行が提供する遺言書保管サービス
法律事務所や信託銀行などでも遺言書保管サービスを行っていることがあります。
相続人等による破棄や隠匿を防ぐことはできますが、いずれも保管費用がかかることが一般的であり、遺言者が生前に相続人に保管場所を伝えていないと、相続開始後に相続人が遺言書を発見することが難しくなる可能性があります。
以上のように、法務局や公証役場に保管しておくことで、相続人等による破棄や隠匿を防ぐことができますし、相続開始後に法定相続人が遺言書にたどり着くことも比較的容易です。
そのため、保管場所としては法務局か公証役場をおすすめします。
3. 遺言書の保管場所は相続人に伝えておく
せっかく遺言書を作成しても、相続が開始したあとに相続人が遺言書を見つけることができないのであれば意味がありませんから、どのような保管場所を選ぶとしても、相続人となる人には遺言書がどこに保管されているか、生前のうちに伝えるようにしてください。
前述のとおり、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合や、公正証書遺言の場合には、前者は法務局に、後者は公証役場に必要書類を用意して問い合わせれば遺言書を発見できますが、それでも相続人がそのような制度を知らなければ発見することはできません。
4. 遺言書作成時には弁護士に相談を
保管場所の選定と併せ、遺言書を作成するときは弁護士に相談することをおすすめします。
相続全般について知見があり、相続に関するトラブルの解決に知見と実績のある弁護士であれば、形式面について問題ない遺言書とすることはもちろん、ご自身の死後の遺志を実現し、遺留分侵害など遺族間にトラブルのない円満な相続をするための遺言書作成のサポートをしてもらえます。
遺言書は大切なご家族への最後のメッセージでもあります。それが伝わり円満な相続となるようにするためにも、遺言書作成に当たっては、ぜひ弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年01月31日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年06月13日
- 遺産相続
-
- 2024年03月25日
- 遺産相続
-
- 2023年12月14日
- 遺産相続