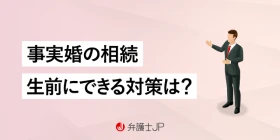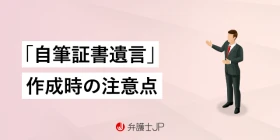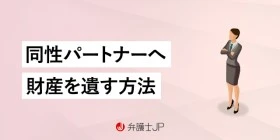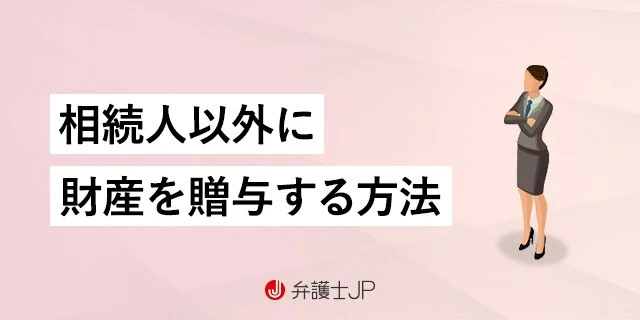
死因贈与とは? 遺贈との違いや手続きの方法を解説
相続対策として財産の引き継ぎ方を決める際には、遺言による贈与(遺贈)などのほか「死因贈与」も選択肢として検討しましょう。死因贈与の特徴を踏まえてうまく活用すれば、遺贈よりもメリットのある形で、後世に財産を譲り渡すことができます。
今回は「死因贈与」の手続き・メリット・デメリットなどについて、遺贈との違いを踏まえて解説します。
1. 死因贈与とは?
「死因贈与」とは、贈与者の死亡を停止条件(効力発生の条件)として、対象となる財産を受贈者に移転する契約をいいます。
(1)死因贈与と遺贈の違い
死因贈与は、被相続人となる方が死亡することを条件として財産を贈与する点で、「遺贈」に類似しています。しかしながら、遺贈は遺言者の「単独行為」であるのに対して、死因贈与は贈与者と受贈者の間の「契約」である点が異なります。
すなわち、遺贈には受遺者の同意が不要であるのに対して、死因贈与には受贈者の同意が必要です。
そして、遺贈の場合には受遺者が一方的に放棄することができる一方で(民法第986条第1項、第990条。包括遺贈の放棄は、相続放棄の方式に従う必要あり)、死因贈与では受贈者が一方的に放棄することは認められず、解除には当事者双方の合意が必要です。
また、遺贈を行う際には、民法に定められた方式(自筆証書・公正証書・秘密証書)を厳密に遵守して遺言書を作成する必要があります(民法第960条)。
これに対して死因贈与は、特に契約の方式が法定されていないため、口頭の合意でも成立する点が特徴的です。ただし、後に他の相続人と揉める可能性がありますので、口頭での合意ではなく書面を作成しておくことが重要です。
(2)通常の死因贈与・負担付死因贈与
贈与者が受贈者に対して無償で財産を移転する通常の死因贈与のほか、受贈者に何らかの義務を課す「負担付死因贈与」も認められます(民法第553条)。
負担付死因贈与の活用例としては、被相続人の生前における身辺の世話と引き換えに財産を贈与する場合などが考えられます。
(3)始期付所有権移転仮登記による権利の確保について
死因贈与の対象財産が不動産の場合、贈与者の承諾があることを条件として、受贈者が単独で「始期付所有権移転仮登記」を申請することができます。
始期付所有権移転仮登記とは、贈与者の死亡を停止条件とした贈与の仮登記です。仮登記の効力により、後に本登記を備えた場合、仮登記後に登記を備えた第三者に対して、対抗関係で優位に立つことができます。
死因贈与による財産の移転を確実なものとしておきたい場合は、贈与者の協力を得て、始期付所有権移転仮登記の手続きをとっておくとよいでしょう。
2. 死因贈与を行うメリット・デメリット
遺贈との比較
死因贈与の方式によって財産を贈与する場合、遺言による贈与(遺贈)に比べて、以下のメリット・デメリットが存在します。
遺贈と死因贈与のどちらを選択するのがよいか、ご家庭の状況に合わせて事前に検討してください。
弁護士に相談すれば、諸般の事情を比較検討したうえで、どちらを選択すべきかについてアドバイスを受けられます。
(1)死因贈与のメリット
遺贈と比較した場合の死因贈与の主なメリットは、以下のとおりです。
①厳密な方式が定められていない
遺贈は厳密な遺言書の方式ルールに従う必要があるのに対して、死因贈与には特に法律で定められた方式がありません。
このことから、遺言書が形式不備で無効となってしまうケースが見られるのに対して、死因贈与は形式不備による無効のリスクが低いのが特徴です。
ただし、死因贈与の内容を明確化するためには、公正証書等の方式で死因贈与契約書を作成しておく方がよいでしょう。
②贈与者にあらかじめ贈与の旨を伝えられる
遺贈は一方的に財産の承継人を指定するのに対して、死因贈与の場合は、受贈者の同意の下で契約を締結することになります。
したがって、受贈者は贈与者の生前の段階から、将来死因贈与が行われる旨を知ることができ、計画的な資産運用等が可能となります。
③負担付死因贈与を活用し、総合的な相続対策が可能
死因贈与の条件として、受贈者に義務を課す「負担付死因贈与」を活用すれば、贈与者の相続・終活に向けた希望を柔軟に反映することができます。
たとえば、贈与者自身の身辺の世話などを依頼したり、目をかけている親族(孫など)の扶養のために財産を贈与したりすることも可能です。
(2)死因贈与のデメリット
死因贈与の大きなデメリットとしては、不動産を対象財産とする場合に、遺贈と比較して不動産取得税・登録免許税の負担が重いことが挙げられます。
死因贈与の場合、不動産取得税は固定資産税評価額の4%、登録免許税は固定資産税評価額の2%が一律でかかります。
これに対して、法定相続人に対する遺贈であれば、不動産取得税は非課税、登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で済みます(法定相続人以外の者に対する遺贈の場合は、死因贈与と同様です)。
したがって、法定相続人に対して承継する財産を特定したい場合には、死因贈与ではなく遺贈を選択した方が、税務面からは有利といえるでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年05月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年06月13日
- 遺産相続
-
- 2024年03月25日
- 遺産相続
-
- 2023年12月14日
- 遺産相続