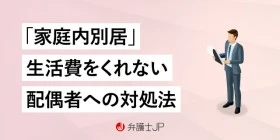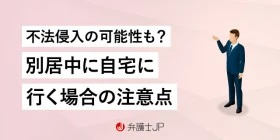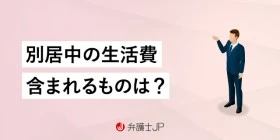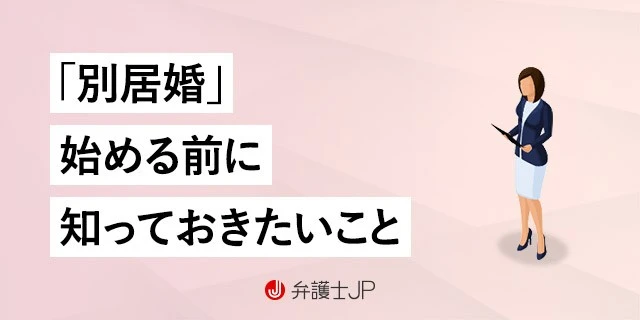
別居婚とは? メリット・デメリットから手続きまで解説
夫婦・パートナーの関係性や結婚生活のスタイルが多様化する中で、最近では「別居婚」を選択する男女が増えています。
今回は別居婚の概要・メリット・デメリット・手続きや、別居婚を始める際の注意点などをまとめました。
1. 別居婚とは?
「別居婚」とは、婚姻届を提出した後も別居生活を続ける夫婦の関係性を意味します。
(1)別居婚の定義
「別居婚」は、法律上定義された言葉ではありません。一般的には、婚姻届を提出した後も同居せず、結婚前と同様に別居を続ける婚姻形態を指すことが多いようです。
別居婚の形は多様であり、必ずしも一つに決まっているわけではありません。
ほとんど同じ場所で寝泊まりすることはなく、それぞれが独身時代同然の生活を営むケースは、別居婚の典型例といえるでしょう。
その一方で、生活の拠点は別々としつつ、1年の大半を同じ場所で寝泊まりするような形もあります。この場合、夫婦が同居する通常の婚姻(同居婚)との区別は曖昧であり、当事者の意識によって呼び分けていることが多いです。
(2)別居婚が選択される主な理由
別居婚が選択される理由は、夫婦の背景事情によってさまざまです。たとえば、以下のような理由が挙げられます。
- お互いに干渉しない状態を確保したい
- 常に新鮮な気持ちで相手と接したい
- いずれかに連れ子がいて、連れ子のストレスになることを避けたい
- これまで同居していたが、関係性を見直すために一度距離を置きたい
- いずれかの親が要介護となり、実家の近くに住む必要がある
など
2. 別居婚のメリット・デメリット
別居婚には、メリット・デメリットの両面があります。別居婚を選択するか否かは、夫婦の状況に合わせて、メリット・デメリットの両方を総合的に考慮した上で決定しましょう。
(1)別居婚のメリット
別居婚の主なメリットは、以下のとおりです。
- それぞれの仕事、趣味、介護などに専念しやすい
- 相手に対して新鮮な気持ちを持ち続けやすい
- 連れ子のストレスになりにくい
- 悪化した関係性を改善するきっかけになり得る
など
(2)別居婚のデメリット
別居婚の主なデメリットは、以下のとおりです。
- 同居の場合よりも生活費が増える
- 不貞行為が発生しやすい
- 夫婦の協力関係を構築しにくい
- 子どもが生まれた場合は再検討が必要
など
3. 別居婚を始める際の手続き
別居婚を始める際には、夫婦の状況に合わせて、いくつかの手続きを行う必要があります。別居婚に伴い、必要になる主な手続きは以下のとおりです。
(1)婚姻届の提出
別居婚の場合でも、通常の婚姻と同様に、市区町村役場へ婚姻届を提出します。
婚姻届の提出以降は、別居状態であっても法律上の夫婦として取り扱われます。具体的には、以下の権利義務が発生する点にご留意ください。
- 同居、協力および扶助の義務(民法第752条)
- 夫婦間の契約の取消権(民法第754条)
- 婚姻費用の分担義務(民法第760条)
- 日常家事に関する債務の連帯責任(民法第761条)
- 相続権(民法第890条)
など
(2)住民票の異動
結婚前の住所にそれぞれが住み続ける場合は、住民票を移動する必要はありません。
これに対して、互いの家を行き来しやすいように、どちらかまたは両方が引っ越す場合には、「転入」または「転居」の手続きを行う必要があります。
①転入
異なる市町村間で住所を変更する場合は「転入」となります(住民基本台帳法第22条第1項)。元の住所の市町村に転出届を提出した後、新住所の市町村に転入届を提出します。
②転居
同じ市町村の中で住所を変更する場合は「転居」となります(同法第23条)。住所地の市町村に転居届を提出します。
なお、2023年2月6日以降、転出届の提出と転入手続き・転居手続きの予約が、マイナポータルを通じてオンラインでできるようになりました。
(参考:「引越し手続オンラインサービス」(デジタル庁))
(3)健康保険の扶養に関する手続き
別居婚であっても、会社員や公務員が加入する健康保険については、収入基準を満たせば配偶者を被扶養者とすることができます(国民健康保険の場合は、扶養の概念がありません)。
<被扶養者の収入要件>
①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
原則として、認定対象者の年間収入が、以下の1. 2.を両方満たすこと
- 130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
- 被保険者の年間収入の2分の1未満
※被保険者の年間収入の2分の1以上であっても、保険者の審査によって被扶養者と認められる場合があります。
②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、以下の1. 2.を両方満たすこと
- 130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
- 被保険者からの援助による収入額より少ないこと
別居婚の配偶者は、被保険者と同一世帯に属していないため、上記②の審査基準が適用されます。「年収130万円未満」であることに加えて、年収よりも多額の婚姻費用の支払いを受けていることが、健康保険の被扶養者の要件とされていることにご注意ください。
(参考:「被扶養者とは?」(全国健康保険協会))
(4)会社への報告(家族手当を受給する場合など)
会社によっては、家族を扶養している従業員に対して、賃金とは別に家族手当などを支給しているケースがあります。
家族手当などは、別居婚であっても受給できる可能性があります。会社の制度を確認した上で、該当している場合には婚姻した旨を会社に連絡しましょう。
また、年末調整の際に配偶者控除の適用を受ける場合も、会社に対して扶養対象配偶者を記載した「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」を提出する必要があります。
(参考:「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」(国税庁))
(5)子どもを出産した場合の手続き
子どもを出産した場合は、出生日から14日以内に、市役所・区役所または町村役場に出生届を提出します。
出生届の提出先は、以下のいずれかの市役所・区役所・町村役場です。父親・母親のほか、同居者も届け出ることができます。
- 子の出生地
- 子の本籍地
- 届出人の所在地
(参考:「出生届」(法務省))
4. 別居婚を始める際に決めておくべきこと
別居婚では、夫婦それぞれが独立した生活を営む一方で、夫婦として協力しなければならない場面もたびたび生じます。
そのため、婚姻生活を送るに当たってのルールを決めておく必要性は、通常の婚姻に比べて高いといえるでしょう。少なくとも以下の事柄については、婚姻届を提出する前の段階で、大まかにでも決めておくことをおすすめいたします。
(1)住む場所
別居婚といえども、それぞれが完全に自由に済む場所を定めると、夫婦間の行き来が難しくなってしまうことも想定されます。
たとえば、住所を変える際には相手に相談する、あまりにも遠くへの引っ越しはしないなど、住む場所に関して一定のルールを定めておくのがよいでしょう。
(2)連絡方法
普段の連絡については、電話やメッセージアプリなどを使って自然体で行えば問題ないでしょう。
しかし、普段別居をしている場合、緊急時には連絡がつきにくくなることが懸念されます。そのため、実家などの連絡先を伝え合うなど、緊急連絡先を明確に決めておくことをおすすめいたします。
(3)生活費の分担
夫婦は、生活費など婚姻から生じる費用を分担する義務を負います(民法第760条)。
別居婚の場合も同様で、収入が多い側は少ない側に対して、婚姻費用を支払わなければなりません。裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にして、毎月の婚姻費用の精算について取り決めておきましょう。
(参考:「養育費・婚姻費用算定表」(裁判所))
(4)会う頻度
別居婚の場合、会う頻度を自然な流れに任せていると、関係性が疎遠になった際には、まったく会わなくなってしまうケースもよくあります。そうなると、夫婦関係の破綻は早晩避けられません。
夫婦としての協力関係を維持するためには、一定以上の頻度で会うことを取り決めておくことも一つの選択肢です。
(5)子どもに関する方針
別居婚夫婦の間では、子どもを作るかどうかについて意見が分かれるケースもよくあります。子どもに関する意見の不一致は離婚のきっかけになりやすいので、別居婚をする前の段階で話し合っておくべきでしょう。
また実際に子どもが生まれた場合、別居婚を続けるべきか、同居して共に子どもを育てるかを再考するタイミングといえます。
子どもの情操教育の観点からは、父母がそろって子どもを養育することが望ましいです。その一方で、同居を始めれば別居婚時代の生活は一変します。子どもが生まれた場合を想定して、別居を解消するのか否かを事前に話し合いましょう。
5. 円満に別居婚を続けるためのポイント
別居婚生活を円満に送るためには、決めるべきことをきちんと話し合い、トラブルの原因をできる限り少なくすることが大切です。上記に挙げた事柄のほか、何を決めておくべきかを夫婦間で議論することをおすすめいたします。
また、取り決めた事項は書面にまとめて、夫婦それぞれが署名・押印しておきましょう。その内容すべてが法的効力を有するわけではありませんが、別居状態で夫婦生活を送る上での指針になることは間違いありません。
別居婚に関する注意事項やトラブルについて、懸念や疑問点がある場合は弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年03月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年12月01日
- 離婚・男女問題
-
- 2023年06月30日
- 離婚・男女問題
-
- 2023年06月05日
- 離婚・男女問題