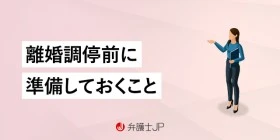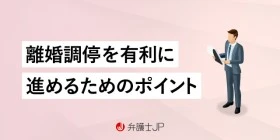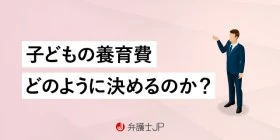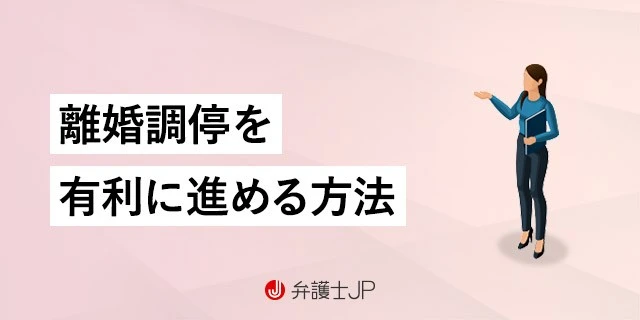
離婚調停委員とは? 上手に付き合うためには?
離婚調停手続きにおいて重要な役割を果たすのが、話し合いの仲介者に当たる「調停委員」です。調停委員を味方に付けることができれば、離婚調停を有利に進められます。
今回は、離婚調停における調停委員の役割や資格要件、調停委員を味方に付ける方法などを解説します。
1. 離婚調停の調停委員とは?
離婚調停は、これから離婚を検討している夫婦が、離婚の可否や離婚条件などを話し合う家庭裁判所の手続きです。
(参考:「夫婦関係調整調停(離婚)」(裁判所))
離婚調停を申し立てると、必ず2名の調停委員が選任されます。調停委員は、裁判官1名とともに調停委員会を構成し、離婚調停の進行役を務めます。
まずは、離婚調停における調停委員の役割と資格要件を確認しておきましょう。
(1)離婚調停における調停委員の役割
離婚調停において、調停委員は夫婦の話し合いを仲介する役割を果たします。
調停委員は、夫婦双方と個別に面談する中で主張を聞き取り、互いの主張を比較しながら、時には譲歩を提案するなどして合意形成をサポートします。客観的・中立的な立場から、夫婦間で冷静な話し合いが行われるように取り計らうことが、離婚調停における調停委員の役割です。
(2)離婚調停の調停委員になる人の資格要件
離婚調停の調停委員は、以下の①②③の要件をいずれも満たす者の中から、最高裁判所が任命します(民事調停委員及び家事調停委員規則1条、2条)。
①以下のいずれかに該当すること
- 弁護士となる資格を有する者
- 家事紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者
- 社会生活の上で豊富な知識経験を有する者
②40歳以上70歳未満であること(ただし、特に必要がある場合はそれ以外の年齢でも可)
③以下の欠格事由に該当しないこと
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 公務員として、免職の懲戒処分を受けた日から2年を経過しない者
- 裁判官として、弾劾裁判所による罷免の裁判を受けた者
- 弁護士などの各種士業として除名等の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
- 医師免許または歯科医師免許を取り消され、再免許を受けていない者
2. 離婚調停の調停委員を味方に付けるには?
離婚調停では、調停委員を味方に付けることができれば、相手方との話し合いを有利に進められます。そのためには、以下のポイントに留意した上で離婚調停に臨みましょう。
(1)わかりやすく主張を伝える
第一に重要なのは、ご自身の主張を調停委員に正しく理解してもらうことです。
特に以下の離婚条件については、どのような内容を希望するのか、調停委員に対して明確に伝える必要があります。
- 財産分与(年金分割を含む)
- 慰謝料
- 婚姻費用
- 親権
- 養育費
- 非親権者と子どもの面会交流
さらに、ご自身が希望する離婚条件が適切である理由についても、法律・裁判例や事実関係に沿って、調停委員にわかりやすく伝えなければなりません。口頭で伝えるだけでなく、事前に準備した書面なども活用して、調停委員にわかりやすく説明することを心がけましょう。
(2)主張の正当性を証拠によって裏付ける
ご自身の主張を裏付ける有力な証拠があれば、調停委員を一挙に味方に付けることができます。
ご自身が離婚を希望していて、相手方が離婚を拒否している場合には、法定離婚事由(民法第770条第1項)を立証できる証拠を提出するのがよいでしょう。たとえば不貞行為を主張するのであれば、相手方と不倫相手が自宅やホテルを行き来する写真や、両者のメッセージのやり取りなどが有力な証拠となります。
離婚条件についても、証拠がそろっていればご自身の主張が認められやすくなります。たとえば財産分与の増額を主張する場合は、資産・収入に関する客観的な資料を提出しましょう。
有力な証拠と主張がきちんと対応していれば、調停委員からの信頼を得ることができます。
(3)弁護士に代理人を依頼する
ご自身の希望・主張が合理的であることを調停委員にわかってもらうには、弁護士を代理人として離婚調停に臨むことをおすすめいたします。
弁護士は、依頼者の希望・主張を法的な観点から整理して、調停委員にわかりやすく伝えてくれます。法的な根拠に基づいた主張を伝えることができるため、好条件で離婚が成立する可能性が高まります。
また、家庭裁判所に提出する書類の準備も弁護士に一任でき、労力が大幅に軽減される点も大きなメリットです。仮に離婚調停が不成立となり、離婚裁判へ移行することになっても、弁護士に依頼していればスムーズに対応してもらえます。
調停委員を味方に付け、スムーズかつ好条件で離婚を成立させたい場合は、弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年02月16日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年05月24日
- 離婚・男女問題
-
- 2023年05月12日
- 離婚・男女問題
-
- 2023年01月31日
- 離婚・男女問題