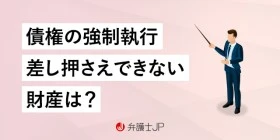- (更新:2023年05月29日)
- 債権回収
【債権回収】少額訴訟のメリット・デメリットや手続きの流れを解説
金銭トラブルがおき、どうしても支払いをしてもらえないときは、最終手段として法的措置をとることになります。法的措置といえば訴訟が思い浮かぶ方も多いと思いますが、訴訟は時間もお金もかかるため、二の足を踏む方も少なくありません。しかし、金額によっては少額訴訟制度が利用できるのをご存じでしょうか。
本コラムでは、債権回収の最終手段ともいえる少額訴訟について、そもそも少額訴訟とはどのような制度なのか、メリット・デメリットは何か、またその手続きの流れについてわかりやすく解説します。
1. 少額訴訟とは?
訴訟というと、「長期にわたって何度も裁判所から呼び出されて、原告・被告が問題解決に向けて法廷の場で主張を戦わせるもの」というイメージがあるかと思います。しかし、少額訴訟制度は意外と手軽に利用できる制度です。
(1)少額訴訟の概要
少額訴訟とは、債権回収において債務者に60万円以下の金銭の支払いを求めるときに使える訴訟手続きです。少額訴訟制度は原則として1回で審理が終わり、訴え提起から判決までおよそ2週間から1か月程度しかかからないため、スピーディーに結果が出ることが特徴です。少額訴訟手続きをとっていても、途中で和解が成立することもあります。
ただし、少額訴訟をするためには、以下の2つの条件をクリアしなければなりません。
- 被告の氏名・住所(または就業場所)などの個人情報、証拠がそろっていること
- 同じ簡易裁判所の利用回数が年10回以下であること
(2)少額訴訟のメリット
少額訴訟には、以下のようなメリットがあります。
①手続きが簡単でスピーディー
少額訴訟は通常訴訟に比べて手続きが簡単です。また、審理が1回で終了し、その日のうちに判決が出るため、原告の負担も軽減されます。
②費用が安い
少額訴訟にかかる費用相場が通常訴訟に比べて安価なのもメリットのひとつです。
少額訴訟手続きにかかる費用は主に収入印紙代、切手代および交通費です。収入印紙代は、訴額が10万円までの場合は1000円で、以後10万円ごとに1000円が加算されます。最高でも6000円で済みますので、金銭的負担も少ないと言えるでしょう。切手代は、裁判所ごとに異なりますが、東京簡易裁判所の場合は5200円です。
このように、印紙代・切手代は安く済みますが、原則として、被告の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをするため、被告が遠方に住んでいる場合は交通費が高額になることがある点に注意が必要です。
③支払いに応じない場合は債務者への強制執行が可能
少額訴訟において裁判官による判決が出ると、債務者が仮に支払いに応じない場合でも「少額訴訟債権執行」という手続きで債務者の財産(金銭の支払いを目的とする債権に限る。)を差し押さえることが可能です。「少額訴訟債権執行」では、債務者名義の預貯金や債務者が雇い主から受け取る給料も含まれます。
この制度は少額訴訟特有のもので、一般的な財産の差し押さえよりも比較的簡単な手続きで債務者の財産を差し押さえることができるのです。
この「少額訴訟債権執行」では債務者にどういった財産があるかは申立人である債権者が調査して突き止める必要がありますが、どの財産の差し押さえを申し立てるかは、申立人に決定権があります。
(3)少額訴訟のデメリット
一方、少額訴訟には以下のようなデメリットもあります。
①分割払い・支払猶予・遅延損害金免除となることがある
原告の請求が認められて勝訴しても、裁判所の判断で分割払い、支払猶予または遅延損害金免除となることがあります。分割払いや支払猶予を命じる判決が出た場合は、債権回収ができなくなるリスクもあるでしょう。
②判決に納得いかない場合でも控訴はできない
証拠が不十分だった、被告から有効な反論があったなどで敗訴することもあります。判決に納得いかない場合、不服申し立てをすることはできますが、控訴はできません。
③通常訴訟に移行することがある
被告の希望により、通常訴訟に移行することがあります。そうすると1回の期日で終わらせるために行った万全な準備が無駄になってしまう可能性もあります。
(4)少額訴訟は弁護士や司法書士に依頼すべきか
少額訴訟手続きは、もとより弁護士や司法書士に依頼することもできます。ただし、着手金や成功報酬といった費用がかかります。弁護士や司法書士に依頼する場合、訴額によっては費用倒れとなってしまうこともあるため、依頼するかどうかは慎重に判断すべきです。
ただ、弁護士や司法書士に依頼すればよりスムーズに少額訴訟の手続きが進んだり自ら手続きを行う手間が減ったりするメリットはあります。また、そもそも少額訴訟で解決できるのかを判断してもらえるので、まずは相談からしてみて実際に依頼するかを検討してもいいでしょう。
2. 少額訴訟の手続きの流れ
少額訴訟は次のような流れで進みます。
(1)訴状・証拠資料の提出
まず、訴状と証拠資料の準備からスタートします。訴状を作成するときは、裁判所のホームページにあるひな形を使うと便利です。請求金額や法的根拠など必要な内容を記載し、収入印紙を貼り、切手(予納郵券)とともに被告の住所地にある簡易裁判所に提出します。
(2)期日呼出状の受領
裁判所が原告から届いた訴状と証拠資料を審査します。裁判所で訴状が受理されると、裁判期日が指定され、原告には期日呼出状と手続き説明書、被告には期日呼出状と訴状が送付されます。
(3)答弁書受理・準備
被告に訴状が届くと、被告は裁判所の要求にしたがって答弁書と証拠資料を準備します。この段階で、被告が通常訴訟に移行するか少額訴訟のままでよいかを選択します。
作成された答弁書は裁判所を通じて原告にも送られてくるので、届いたら内容を確認して追加の証拠資料などの準備をしましょう。証人が必要であれば、連絡をとって期日に出席してもらえるよう依頼します。
(4)審理
期日では、原告・被告・裁判官がひとつのテーブルについて話し合いのような形で審理を行います。まず、原告・被告が主張を述べて証拠資料を提示し、それをもとに裁判官が争点を整理して証拠資料や証人の取り調べをします。審理自体にかかる時間は、だいたい30分から2時間前後です。
(5)判決(もしくは和解)
審理が終われば、裁判官が判決を言い渡します。なお、話し合いで決着がつくようならその場で和解が成立することもあります。判決に対し、当事者のどちらかが異議申し立てをしたときは、同じ簡易裁判所で控訴の認められない通常の審理・裁判が行われます。
- こちらに掲載されている情報は、2023年05月29日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

債権回収に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2022年05月23日
- 債権回収
-
- 2021年11月26日
- 債権回収
-
- 2021年11月19日
- 債権回収
債権回収に強い弁護士
-
寺田 弘晃 弁護士
神楽坂総合法律事務所
●東京メトロ地下鉄 飯田橋駅B3出口より 徒歩約5分
●JR飯田橋駅西口より 徒歩約6分
●都営大江戸線 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分
●東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
弊所は、1階に【 新宿神楽坂郵便局 】や【 カフェ・ベローチェ 】が所在する、オザワビルの6階です。
神楽坂のシンボル【 毘沙門天 善國寺 】がビルの目の前にございます。
▶▷▶ 事務所ホームページ↓
https://shinjuku-houritusoudan.com/現在営業中 11:00〜19:00電話番号を表示する 03-5206-3755- 休日相談可
- 夜間相談可
- 24時間予約受付
- 全国出張対応
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
▶▷▶ 土日祝日・夜間のご相談も、予めお問合せ下さい