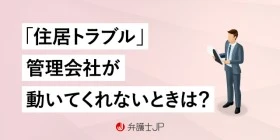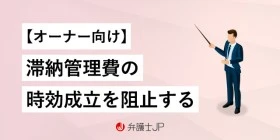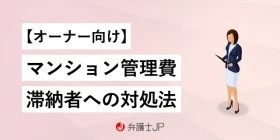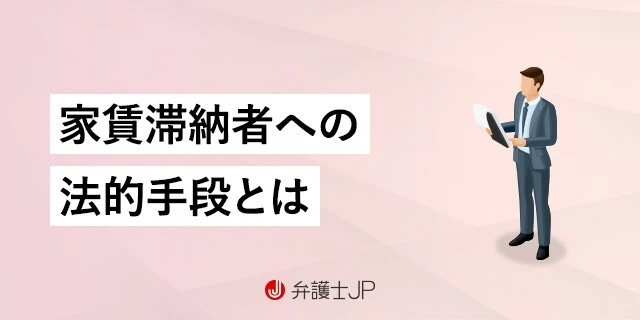
家賃滞納者へ裁判を起こせる? 督促から訴訟までの法的対策
賃貸住宅のオーナーの多くが賃借人による家賃滞納の問題を抱えています。単に期限を忘れていたというだけであれば、支払いを催促するだけですぐに入金してくれることもありますが、悪質なケースでは、何か月も家賃を滞納した状態でアパートに住み続けているということもあります。
家賃を滞納している入居者に対して督促などをしても支払いがなければ、最終的には法的手段を検討することになりますが、家賃滞納者に対する法的手段としてはどのようなものがあるのでしょうか。
今回は、家賃滞納に対して、法的には何ができるのかについて解説します。
1. 賃貸住宅における家賃滞納の実態
日本賃貸住宅管理協会が、賃貸住宅の管理会社を対象として行った「賃貸住宅景況調査」(令和2年10月から令和3年3月まで)によると、全国の月初全体の平均滞納率は、5.0%でした。滞納率が5.0%ということは、20戸に1戸の割合で家賃の滞納が発生しているということになります。賃貸住宅のオーナーとしては決して無視することができない数字といえるでしょう。
全国の2か月以上の平均滞納率は、1.1%と少なくなっていますので、引き落とし口座の残高不足や期限を忘れて滞納したという事案もそれなりにあるものと予想されます。
しかし、100戸に1戸の割合で、2か月以上の長期的な家賃の滞納が発生しており、放置しておけば家賃の滞納額はどんどん増えていくことになるでしょう。家賃の滞納が生じた場合には、早めに対策を講じることが重要となります。
2. 家賃滞納への法的手段とは
家賃を滞納する賃借人に対する裁判上の手段としては、以下のものが挙げられます。
(1)支払督促
滞納家賃の請求には、簡易裁判所の支払督促を利用することができます。支払督促は、通常の民事訴訟とは異なり、簡易裁判所書記官による書面審査のみによって、賃借人に対し滞納家賃の支払いが命じられる手続きです。
そのため、裁判所に出頭する必要もなく、迅速な手続きによって滞納家賃に関する債務名義を取得することができます。債務名義とは、給与の差し押さえなどの手続き(強制執行)の際に必要な公的な文書です。
ただし、賃借人から支払督促に対して異議の申し立てがあった場合には、請求額に応じて、簡易裁判所または地方裁判所の民事訴訟手続きに移行することになります。
(2)少額訴訟
滞納家賃の金額が60万円以下であれば、簡易裁判所の少額訴訟を利用することができます。少額訴訟は、原則として1回の期日によって審理が終結し、判決が言い渡されることになりますので、通常の民事訴訟に比べて簡易かつ迅速に解決を図ることが可能です。
しかし、少額訴訟も被告から通常の民事訴訟での審理を希望する旨の申し出があると、通常の民事訴訟手続きに移行することになります。
(3)民事訴訟
支払督促および少額訴訟では、滞納賃料の請求といった金銭の請求をする場合にしか利用することができません。
しかし、長期間賃料の滞納をしている場合には、今後も賃料を支払う意思がないことが多いため、賃貸借契約を解除して、賃貸物件からの明け渡しも求める必要があります。未払い賃料の請求とともに建物の明け渡し請求をする場合には、通常の民事訴訟を提起する必要があります。
3. 督促から裁判までの流れ
家賃の滞納がある場合には、以下のような流れで滞納している家賃の回収を図ります。
(1)滞納賃料の督促
家賃の滞納が生じた場合には、賃借人に対して家賃支払いの督促を行います。単に期限を忘れているだけということもありますので、まずは電話連絡、訪問、書面などによって支払いを催促するとよいでしょう。
連帯保証人がいる場合には、連帯保証人への請求も有効な手段となります。なお、家賃保証会社と契約をしている場合には、家賃保証会社に滞納家賃を請求することになります。
(2)内容証明郵便の送付
上記の督促にも応じない場合や長期間家賃の滞納が続いている場合には、内容証明郵便を利用して、一定期間内に滞納賃料の支払いがない場合には賃貸借契約を解除する旨の書面を送るようにしましょう。内容証明郵便自体には支払いを強制する効力はありませんが、賃貸人の本気度が伝わることで賃借人による任意の支払いが期待できます。
また、後々に契約解除まで求めて行くことや、時効の主張を封じることなどを考えると、支払いを求めた事実や、求めながら履行されなかった事実を証拠化していくことは有意義です。
(3)裁判
上記のような裁判外の交渉で解決しない場合には、最終的に未払い賃料の請求を求めて、裁判所に対して訴訟を提起することになります。この場合には、長期間の賃料の滞納を理由に賃貸借契約を解除し、建物の明け渡しも同時に求めることが多いです。
家賃滞納の事案では、請求内容自体に争いがないことや賃借人が当該物件にすでに居住していないことが多いため、実際の裁判では被告欠席のまま、判決が言い渡されることも少なくありません。そのため、一般的な金銭請求の事案に比べると裁判に要する労力は小さいといえるでしょう。
(4)強制執行
裁判所の判決が確定した後も賃借人が任意に未払い賃料の支払いを行わない場合には、強制退去や賃借人の財産の差し押さえをするために強制執行の手続きを行うことになります。
しかし、家賃を長期間滞納している賃借人だと差し押さえるべき財産がないということもありますので、強制執行をする場合には、事前に十分な財産調査を行っておく必要があります。もっとも、強制執行しようという段階で調査をすることは難しくなってくるため、滞納などの問題が生じる前から給与口座などをあらかじめ把握しておくのが、本当は望ましいです。
- こちらに掲載されている情報は、2022年03月16日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

不動産・建築・住まいに強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年12月19日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2022年05月11日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2022年04月13日
- 不動産・建築・住まい
不動産・建築・住まいに強い弁護士
-
寺田 弘晃 弁護士
神楽坂総合法律事務所
●東京メトロ地下鉄 飯田橋駅B3出口より 徒歩約5分
●JR飯田橋駅西口より 徒歩約6分
●都営大江戸線 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分
●東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
弊所は、1階に【 新宿神楽坂郵便局 】や【 カフェ・ベローチェ 】が所在する、オザワビルの6階です。
神楽坂のシンボル【 毘沙門天 善國寺 】がビルの目の前にございます。
▶▷▶ 事務所ホームページ↓
https://shinjuku-houritusoudan.com/電話番号を表示する 03-5206-3755- 休日相談可
- 夜間相談可
- 24時間予約受付
- 全国出張対応
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
▶▷▶ 土日祝日・夜間のご相談も、予めお問合せ下さい
弁護士を検索する
都道府県から検索する
相談分野から検索する
詳細分野から検索する
最近見た弁護士
-

石川 ことの 弁護士
ベリーベスト法律事務所 船橋オフィス
千葉県船橋市本町7-11-5 KDX船橋ビル6階メールでお問い合わせ電話番号を表示する 0120-047-006現在営業中 9:30〜18:00