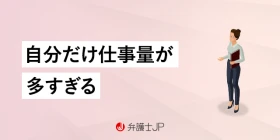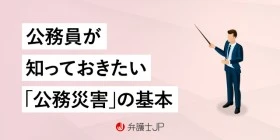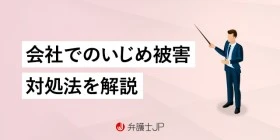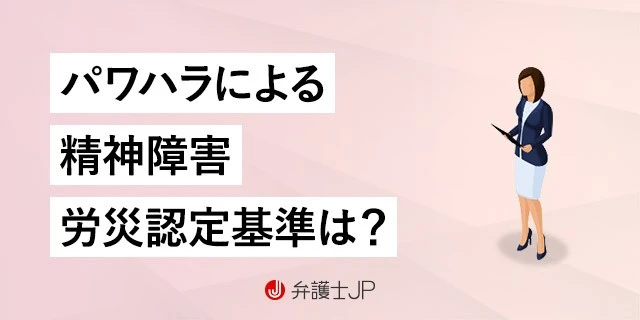
パワハラを受け精神障害に。労災認定を受けるためにすべきこと。
職場でパワハラを受けた労働者は、うつ病や急性ストレス障害などの精神障害を発病してしまうケースがあります。
職場でのパワハラにより精神障害が生じた場合は、労災認定がなされる可能性があります。行為者や会社に対する損害賠償請求を検討することと併せて、労災申請の準備を進めましょう。
今回は、パワハラにより精神障害が生じた場合の労災認定基準や、労災認定を受けるための手続きなどを解説します。
1. パワハラによる精神障害が生じた場合の労災認定基準
職場で上司などからパワハラを受け、うつ病や急性ストレス障害などの精神障害を発病した場合、労災保険給付を受けられる可能性があります。
厚生労働省の認定基準によれば、精神障害について労災保険給付を受けるためには、以下の3つの要件を満たすことが必要です。
(参考:「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(厚生労働省))
(1)認定基準の対象となる精神障害を発病したこと
精神障害のうち、労災保険給付の対象となるのは、『国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)』において、第5章「精神および行動の障害」に分類されている精神障害(器質性のもの及び有害物質に起因するものを除く)です。
そのうち、パワハラに起因して発生し得る精神障害の代表例としては、うつ病や急性ストレス障害などが挙げられます。
(2)発病前のおおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
発病前の6か月程度の間において、業務上発生した出来事から生じる心理的負荷の程度を総合的に評価し、強い心理的負荷が認められる場合に限り、労災保険給付の対象となります。
パワハラに起因する強い心理的負荷が認められる場合の主なパターンは、以下のとおりです。
- 過剰な長時間労働や連続勤務を課された
- 退職を強要された
- 左遷された
- 配置転換で全く異なる業務への従事を強いられ、対応に多大な労力を費やした
- 配置転換により、異例なほど重い責任が課される立場となった
- 人格を否定するような著しい差別が継続した
- ひどいいやがらせ、いじめ、暴行を受けた
- 重大なセクハラを受けた
など
(3)業務以外の要因による発病ではないこと
うつ病や急性ストレス障害などの精神障害が、業務以外の要因によって発病したと評価される場合には、労災保険給付の対象外となります。
具体的には、以下のいずれかの出来事が発病前の間近い時期に発生した場合、労災が認定されなくなる可能性があります。
- 離婚、夫婦の別居
- 重い病気、ケガ、流産
- 配偶者、子ども、親、きょうだいの死亡
- 配偶者、子どもの重い病気、ケガ
- 親類が世間的にまずいことをした
- 多額の財産を失った
- 突然大きな支出を強いられた
- 天災や火災などの被害に遭った
- 犯罪に巻き込まれた
など
2. パワハラ被害について労災認定を受けるための手続き
パワハラに起因してうつ病や急性ストレス障害にかかった場合には、労働基準監督署に対して労災保険給付を請求しましょう。
労災保険給付には、以下に挙げるように、さまざまな種類があります。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料(葬祭給付)
- 傷病(補償)年金
- 介護(補償)給付
- 二次健康診断等給付
各給付を請求するには、それぞれの給付に対応する請求書を労働基準監督署に提出する必要があります。
請求書は以下の厚生労働省ウェブページからダウンロードできるほか、労働基準監督署の窓口で交付を受けることも可能です。
(参考:「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」(厚生労働省))
請求書の作成は、会社の協力を得られればスムーズに行うことができます。しかし、会社が非協力的な場合でも、労災保険給付の請求は可能ですので、労働基準監督署の窓口へご相談ください。
3. 労災認定だけでは納得できない場合にとるべき対応
労災保険給付は、被災労働者に生じた損害を補塡(ほてん)するのに十分でない場合もあります。また心情的に、行為者や会社の責任を追及しなければ気が済まないというケースもあるでしょう。
パワハラに起因して労働者が精神障害を発病した場合、行為者は、不法行為責任(民法709条)に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。また、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)または使用者責任(民法第715条第1項)等に基づき、会社は被災労働者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
行為者や会社に対する損害賠償請求を行う際には、弁護士への相談がおすすめです。弁護士は、協議・労働審判・訴訟などの手続きを通じて、被災労働者の正当な権利を主張し、発生した損害の賠償を求めて戦ってくれます。
パワハラによる精神障害にお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2022年09月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年01月19日
- 労働問題
-
- 2023年11月09日
- 労働問題
-
- 2023年06月23日
- 労働問題