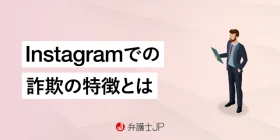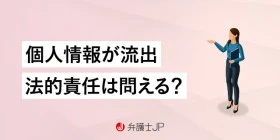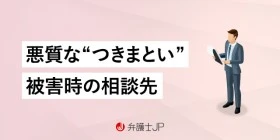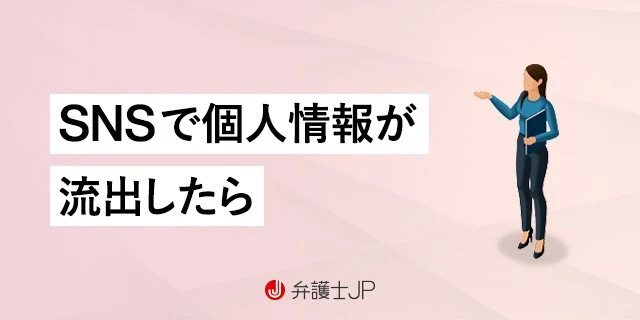
ネットでの実名晒し被害に遭ったら? 対処法を解説
SNSなど不特定多数の人が見るネット上で自分の実名を晒されることは、被害者にとって非常に不安なことです。ネット上での個人情報晒しは、プライバシーの侵害に当たり、内容によっては刑事責任を追及できることもあります。
本記事では、ネット上での個人情報晒しが該当する罪状や対応方法などについて解説します。
1. ネット上の実名(個人情報)晒し行為はどんな罪に当たる?
晒し行為の内容と定義、権利侵害の問題について解説します。
(1)晒し行為とは
個人情報の晒し行為とは、他人のプライバシーに関わる情報を、本人の承諾なくインターネット上に公開する行為を指します。この「個人情報」とは、晒されているのが具体的に誰なのか特定できる情報のことで、名前や住所、電話番号、メールアドレスなどが代表例です。
個人情報保護法では、このような情報の取り扱いに細心の注意が求められています。どのような人が見ているかもわからないネット上に個人情報が晒されることは、被害者にとって非常に怖いことです。厄介なことに、すべての晒し行為が悪意によるものとは限りません。
たとえば、子どもの運動会の様子をカメラやビデオに撮ってブログやSNSにアップロードする行為は、保護者にとって無邪気な喜びの表れかもしれません。しかし、自分の子どもだけならまだしも、他人の子どもの姿もそこに映り込んでいたとしたら、それが元で深刻なトラブルになるリスクがあります。
被写体の顔、学校指定の運動服、運動服の名札、校舎の様子、撮影日(運動会の日時)などさまざまな要素から、どこの誰なのか特定できてしまう恐れがあるためです。
(2)晒し行為は権利侵害になることがある
こうしたネット上での個人情報晒しは、プライバシー権を侵害しかねません。プライバシー権とは、自分の私的な情報を他者に勝手に公開されることなく、自由かつ安全に生活する権利のことです。
本人が知られたくないと思っている個人情報を他者が勝手に公開する行為は、このプライバシー権の侵害に当たります。また、写真などが公開される場合は、肖像権侵害の問題も無視できません。
公開された情報に公益性がある場合など、合法とみなされるケースもありますが、基本的には他人の情報を勝手にネット上で公開することには慎重であるべきです。
2. 実名晒しで名誉毀損罪にあたるケースとは?
プライバシーの侵害は不法行為ではありますが、それ単体だと刑法上の罪に問われるものではありません。しかし、発信した情報の内容によっては、刑事罰の対象になる可能性があります。具体的には、「名誉毀損罪」「侮辱罪」「脅迫罪」です。
(1)名誉毀損罪
名誉毀損罪とは、他人の名誉を傷つける行為を公然と行った場合に成立する罪です。原則として、発信した情報が真実か虚偽かは関係ありません。たとえば、「Aさんは上司と不倫している」と実名を挙げてSNSで発信することは、本当にAさんが不倫しているとしても名誉毀損罪に該当します。
被害者の社会的評価を下げるような具体的な情報を添えていることが、名誉毀損罪が成立するためのポイントです。たとえば、「Aさんは不倫している」「横領している」「刑務所に入った経験がある」などが具体例として挙げられます。ただし、公務員の汚職など公共の利益になる真正な情報発信については、それが他者の名誉を傷つけたとしても合法と認められる場合もあります。
(2)侮辱罪
侮辱罪とは、他者を蔑視するような言動を公然と行った場合に成立する罪です。名誉毀損罪とよく似ていますが、侮辱罪の場合は、事実を示さず、誹謗中傷が曖昧な内容であっても成立するという特徴があります。たとえば、「Aさんはバカだ」「デブだ」「クズだ」などの罵倒は、その根拠となるような具体的な情報が付随していないので、名誉毀損罪ではなく、侮辱罪が適用されます。
(3)脅迫罪
脅迫罪とは、対象者の命、身体、財産、名誉などに対して危害を加えると脅した場合に成立する罪です。対象者本人だけでなく、その家族などに危害を加えると脅した場合も該当します。たとえ本人に直接告知せず、ネット上の掲示板やSNSなどに「○○を殺してやる」「○○の裸の写真をネットに拡散する」などと投稿するような形でも、脅迫罪に当たる可能性があります。
3. 個人情報を晒された場合に求められる罰則
晒し行為については、その内容に応じて、以下のように刑事上または民事上の責任を問うことが可能です。
(1)刑事上の責任
先述のように、晒し行為は名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪などに該当する可能性があります。これらに対する刑事罰は以下の通りです。
- 名誉毀損罪(刑法第230条): 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
- 侮辱罪(刑法第231条):1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(1000円以上1万円未満の納付)
- 脅迫罪(刑法第222条):2年以下の懲役または30万円以下の罰金
なお、脅迫行為によって他者に無理やり何かをさせる行為は「強要罪」(刑法第223条)に当たります。この場合の刑事罰は3年以下の懲役です。
(2)民事上の責任
晒し行為に対しては民事上の責任を問うことも可能です。被害者は、晒し行為によって受けた精神的苦痛を補償するための慰謝料や、経済的損失を補償するための損害賠償を加害者に請求できます。
慰謝料の金額の大まかな目安としては、被害者が一般人の場合は数万~数十万円、企業の場合は50万~100万円程度です。被害の大きさや、行為の悪質さなどに応じて、これ以上になる場合もあります。
4. ネットで実名晒しの被害に遭ったときの対処法
自分が晒し行為の被害に遭った場合の対処方法はいくつかあります。
まずは、個人情報が晒されたSNSや掲示板、Webサイトに対して削除申請をしましょう。これらの多くでは、晒し行為を禁じているのが一般的なので、運営者に申請すれば情報を削除してもらえる可能性があります。ただし、申請しても対応が遅かったり、そもそも対応してくれなかったりすることもあるため、そのような場合は法的手段を検討しましょう。
その際は、弁護士に相談することをおすすめします。特に、加害者を特定して訴訟を起こす場合は、弁護士のサポートが必要です。弁護士に依頼し、裁判所を介して誰が晒し行為をしたのかを開示する「発信者情報開示請求」を行ってもらえば、加害者を特定できる可能性があります。加害者の刑事責任や民事責任を問う訴訟を起こす際にも、弁護士は法律の専門家として強力な味方になってくれます。
SNSなどで実名などの個人情報を晒す行為に対しては、民事上または刑事上の責任を加害者に問うことが可能です。もしもこうした被害に遭ってしまった場合は、ひとりで抱え込まず弁護士に相談してみることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2023年09月08日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

インターネットに強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年01月24日
- インターネット
-
- 2023年12月11日
- インターネット
-
- 2023年11月22日
- インターネット