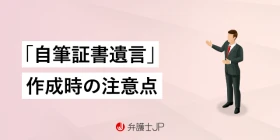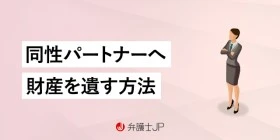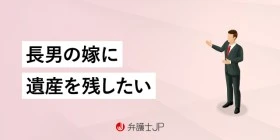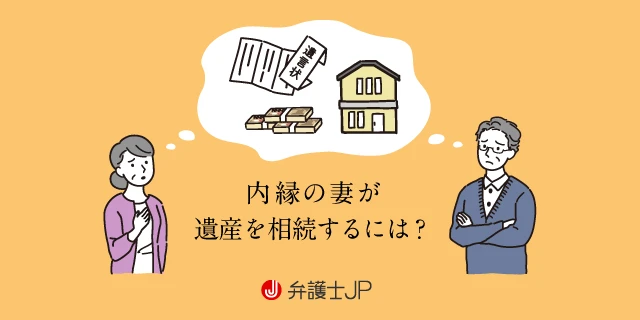
- (更新:2023年02月07日)
- 遺産相続
内縁の妻に財産を残したい。相続トラブルを避けるためにできること
戸籍上の家族ではない場合でも内縁関係があると、相続において子どもや両親、兄弟といった内縁のパートナーの血縁関係にある方とトラブルになることがあります。特に、内縁の夫の持ち家の所有権や居住権をめぐってトラブルになることが多いようです。
「内縁の妻」にまつわる相続トラブルを避けるにはどうすればよいのでしょうか。
1. 内縁の妻が直面しがちな相続トラブル事例
まず、内縁の妻をめぐる相続についてのトラブルを、その内容に基づいて3パターンに分類しました。順に見ていきましょう。
(1)持ち家の所有権で争いが起こるケース
内縁の夫が亡くなってしまった後、その持ち家に、内縁の妻が住んでいる場合、家の所有権をめぐってトラブルになることがあります。
内縁の妻には家を相続する権利はなく、家を相続する権利は法定相続人にあるためです。結果、法定相続人から家の明渡請求がなされることがあり得ます。数多くの裁判で争われ、判例が積み重なった事例ですが、現在でもなおトラブルとなる可能性があるのです。
(2)遺言で内縁の妻が受遺者になっているケース
亡くなった内縁の夫が「内縁の妻に全財産を譲る」などと遺言書を作成しておけば、内縁の妻は遺産を引き継ぐことができます。しかし、法定相続人から遺留分減殺請求や、遺贈無効の訴えが起こることも考えられます。
相続で揉めないために、内縁の夫が遺言を活用したケースに起こりがちなトラブルです。
(3)生前に婚姻届が出されたケース
生前に婚姻の届け出を行い、内縁関係から法律婚関係にしておくことは、トラブル回避のための強力な手法です。
婚姻届を提出しておけば事実婚の関係だったものが法律婚の関係になるので、夫が亡くなってしまっても妻は夫の遺産を相続することができます。しかし、婚姻は無効だという主張が他の相続人からなされてトラブルになることもあります。
2. 内縁の妻が相続するためにすべきことは?
(1)大きな効力を発揮する「遺言書」を残しておく
内縁の妻を受遺者としておくことは、内縁の夫の死後を考えたとき、特に住居を確保するためには有効な方法といえます。
内縁の妻は戸籍上の妻ではない以上、相続権はありませんので、内縁の夫の死後、相続人から住居から出ていくよう告げられるケースが少なくないためです。
住居を守る目的であれば、内縁の夫の所有物である住居を譲ると法的に適切な遺言書で示すことによって、内縁の妻の住むところは確保されます。また、相続税対策で住居を売却して住み替えることもできるでしょう。
しかし、この方法も万全というわけではありません。というのは、法律的には遺留分減殺請求権をもつ相続人を完全に排除することはできないためです。
もちろん、法定相続人が異議を唱えなければ遺言の通りに相続が実行され、故人の意思が実現します。
しかし、内縁の妻と相続人との折り合いが悪い場合などは争いになるケースも考えられます。
仮に遺言が無効になると、内縁の妻は法定相続人ではないため、相続財産はゼロになります。遺言を残す場合は無効の主張をされないよう、できれば公正証書遺言にしておくことをおすすめします。
(2)生前に「法律婚」を結ぶ
もっとも強力な対策は、法律上婚姻関係を結んでおくことです。
子どもたちなど親族が結婚に反対していたとしても、法律上においては絶対的な障害にはなりません。婚姻に必要なのは当人同士の意思のみだからです。
故人が生前、意識がはっきりした状態で、自由な意思に基づいて届出を作成していた場合には婚姻は成立します。
ただし、改めて健常な状態で入籍したという事実を証明しようとすると難しいケースが多くあります。あらかじめ疑問を持たれないよう第三者を証人にするなどして、本人同士の自由意思で婚姻を届け出たことを証明できるようにしておくとよいでしょう。
また、法律婚の関係になったと相続人に知らせておくと、トラブルになりづらいといえます。
あなたが内縁の夫であるならば、内縁関係の妻の財産保護について、生前からきちんと考えておく必要があります。特に住居については、内縁の妻が追い出されたりすることのないよう、前述したような策を講じておきたいものです。
適切な解決方法を知りたい場合は、弁護士に相談してみてください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年02月07日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年03月25日
- 遺産相続
-
- 2023年12月14日
- 遺産相続
-
- 2023年03月20日
- 遺産相続