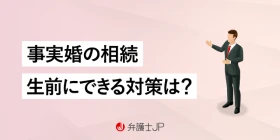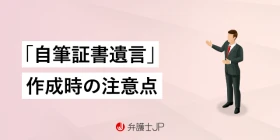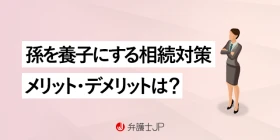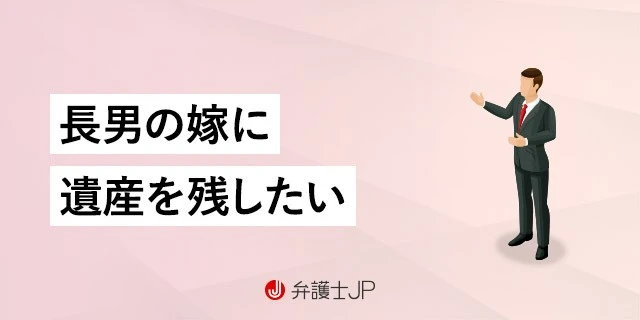
長男の嫁は法定相続人ではない? 遺産相続させる方法は?
長男夫婦と長男の親が同居をしていると、親の身の回りの世話や介護などは長男の嫁が行っているケースも多いでしょう。このように長男の嫁が献身的に介護などに尽力してくれた場合には、長男の嫁に対して、遺産を相続させたいと考える方もいると思います。
長男の嫁は、遺産を相続できる法定相続人にあたるのでしょうか。また、長男の嫁に遺産を相続させる方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
今回は、長男の嫁に対して遺産相続させる方法について解説します。
1. 長男の嫁は法定相続人に含まれる?
そもそも長男の嫁は、遺産相続できる法定相続人に含まれるのでしょうか。
(1)法定相続人の範囲
法定相続人の範囲は、民法によって以下のような範囲および順位が定められています。
- 配偶者(常に相続人になる)
- 子ども(第1順位)
- 両親(第2順位)
- 兄弟姉妹(第3順位)
(2)長男の嫁は法定相続人に含まれない
上記のとおり、長男の嫁は、法定相続人の範囲には含まれません。そのため、長男の嫁は、法定相続人として被相続人の遺産を相続することはできません。
長男が遺産相続をすることによって一緒に生活する長男の嫁にも遺産の一部が渡ることがあるかもしれませんが、長男の嫁に直接遺産を渡したいという場合には他の方法を検討する必要があります。
2. もし長男の嫁に遺産を残したい場合は?
長男の嫁に遺産を残したい場合には、以下の方法を検討しましょう。
(1)遺言
遺言がある場合には、法定相続人の遺産分割協議に優先しますので、生前に遺言を作成することによって、法定相続人以外の方に対して、遺産を相続(遺贈)させることができます。
遺言では、特定の遺産(A土地、B銀行の預貯金など)を長男の嫁に残すこともできますし、「遺産の○割を遺贈する」といった包括的な形で遺産を残すこともできます。
ただし、遺言を作成する際には、他の相続人の遺留分(一定の法定相続人に対して最低限保障された相続分の割合)に配慮する必要があります。
すべての遺産を長男の嫁に遺贈してしまうと、他の相続人の遺留分を侵害しますので、遺留分に関するトラブルが発生する可能性が高くなるでしょう。
(2)養子縁組
養子縁組をすることによって、養親と養子との間には法律上の親子関係が生じます。養子は、被相続人の「子ども」として遺産を相続する権利を取得しますので、長男の嫁に遺産を残す方法としては養子縁組も有効な方法です。
ただし、被相続人の遺産を分けるには、養子である長男の嫁も遺産分割協議に参加しなければなりませんので、他の相続人の反発が生じると、遺産分割協議が難航するおそれもあります。
(3)生命保険の受取人
生命保険を利用することによって、長男の嫁に財産を渡すことができます。具体的には、被相続人が契約者、被保険者として生命保険に加入し、生命保険の受取人を長男の嫁に指定しておく方法です。
これによって、被相続人が死亡した場合には、死亡保険金が長男の嫁に支払われることになりますので、希望を実現することが可能です。
長男の嫁に支払われる死亡保険金は、長男の嫁の固有財産として扱われ、遺産分割協議の対象外となります。そのため、生命保険の利用は、遺産相続トラブルを回避するという観点からも有効な手段といえるでしょう。
(4)生前贈与
生前に長男の嫁に財産を贈与することによって、財産を渡したいという希望をかなえることもできます。
ただし、生前贈与をする場合には、贈与額に応じて贈与税が課税される点に注意が必要です。相続税に比べて贈与税の税率は高くなっていますので、贈与額によっては長男の嫁に高額な贈与税の負担をかけるリスクもあります。
なお、贈与税には基礎控除がありますので、年間110万円までの贈与であれば、贈与税の負担なく生前贈与をすることができます。そのため、長期的な視点で長男の嫁に生前贈与を続ければ、税金の負担なく財産を移転することが可能です。
ただし、税制はしばしば変わりますから、これを行うに当たっては、税理士に有効性を確認してからにすべきでしょう。
(5)孫への遺産相続
被相続人よりも長男が先に亡くなっており、長男に子ども(被相続人の孫)がいる場合には、代襲相続によって、被相続人の孫が遺産を相続することができます。長男の嫁と孫が一緒に生活をしているのであれば、孫が遺産を相続することによって、実質的に長男の嫁にも遺産相続の恩恵を与えることができるといえます。
ただし、あくまでも遺産を相続するのは孫ですので、確実に長男の嫁に遺産を渡したいというのであれば他の方法を選択した方がよいでしょう。
(6)特別寄与料
民法改正によって、相続権のない一定範囲の親族であっても、被相続人の療養看護などに尽力した方は、特別寄与料の請求が認められるようになりました。
長男の嫁が被相続人の死後、相続人に対して、特別寄与料を請求することによって、寄与行為に応じた特別寄与料の支払いを受けることができる場合があります。
- こちらに掲載されている情報は、2023年03月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年06月13日
- 遺産相続
-
- 2024年03月25日
- 遺産相続
-
- 2024年03月08日
- 遺産相続