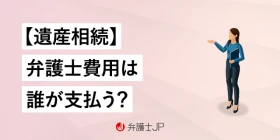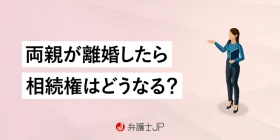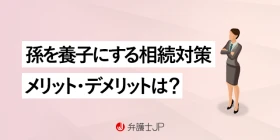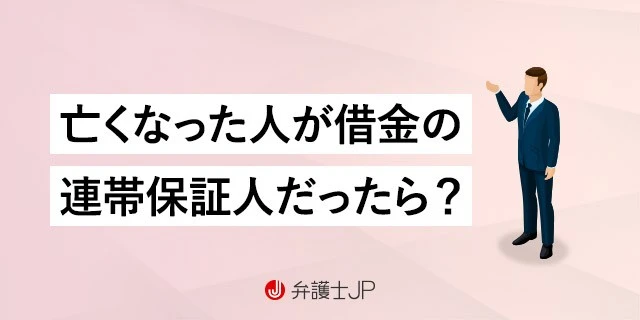
連帯保証人が死亡したら相続はどうなる? 時効はある?
家族や親族が死亡すると、死亡した人の財産を特定の人が相続します。では、連帯保証人になっていた人が亡くなった場合、債務はどうなるのでしょうか。
本コラムでは連帯保証人の時効や、連帯保証人の地位を相続してしまったときの対処法などについて解説します。
1. 連帯保証人が死亡したらどうなる?
連帯保証人とは、借金をした本人(主債務者)と連帯して債務(借金や借りたものを返す義務)を負う人のことです。主債務者と一緒に返済する義務があります。
では、主債務者が借金を完済する前に連帯保証人が死亡してしまったら、「返済する義務」はどうなってしまうのでしょうか。
(1)相続によって子や配偶者に引き継がれる
借金が未返済の状態で連帯保証人が亡くなってしまった場合には、連帯保証人としての債務(連帯保証債務)は相続によって配偶者や子などの法定相続人に引き継がれます。
保証債務とは、主債務者が返済しなかった場合に、代わりに債務の返済を行う義務です。連帯保証債務になると、主債務者が返済する、しないに関わらず、返済する義務を負います。
相続では、預金や不動産といったプラスの遺産だけではなく、借金や未払い金などのマイナスの遺産も含めて、すべてが引き継ぐ対象となります。マイナスの遺産である保証債務も、連帯保証人が亡くなると、基本的には相続人が新たな連帯保証人となります。
複数の法定相続人で遺産を分割相続する場合には、民法で定められた相続割合か、または遺産分割協議によって定められた割合や内容で相続します。しかしながら、遺言書や遺産分割協議によって、民法とは異なる相続割合を合意したとしても、連帯保証債務などのマイナスの財産は、借入先(銀行など)との関係では、法定相続分に応じて義務を負います。
(2)相続放棄によって手放すこともできる
主債務者が将来的に借金を完済できそうにないときや、借入額があまりに高額なときには、相続放棄によって(連帯)保証債務を手放すこともできます。相続放棄とは、遺産相続権を放棄することで、家庭裁判所に申し立てを行って受理される必要があります。
相続放棄は、相続の発生を知った日から3か月以内に申し立てを行わなければなりません。相続放棄してしまうと、プラスの遺産を含めすべての遺産を相続できなくなってしまいますので、慎重に検討しましょう。
2. 保証債務に消滅時効はある?
(1)保証債務の消滅時効は5年または10年
消滅時効とは一定期間、権利が行使されなかった場合に権利の消滅を認める制度で、民法第166条で規定されています。
保証債務の場合、以下のいずれか早いときで時効となります。
- (返済の)権利があることを知った時点から5年
- (返済の)権利を行使できるようになった時点から10年
本条項は2020年4月1日施行の改正民法で変更されたもので、同日以降に契約をした保証債務に適用されます。
2020年3月31日以前の保証債務に関しては、権利を行使できるようになってから10年で消滅時効となります(5年の条件はありません。ただし、民法改正前も貸金業者からの借金は5年で時効により消滅します)。
保証債務を時効により消滅させるためには、債権者に対して消滅時効の援用手続き(「時効がきたので返済の義務はなくなりました」という旨を通達すること)を行う必要があります。この手続きは一般的に内容証明郵便を債権者に郵送することで行います。
(2)消滅時効も相続人に引き継がれる
保証債務を相続した場合には、消滅時効も相続人に引き継がれます。仮に消滅時効が10年で、請求されていない期間が相続時点で7年経過しているのであれば、3年後に消滅時効の手続きを行えます。
(3)時効の中断事由によって時効がリセットされることも
請求権が消滅するまでの間に時効の中断事由が発生すると、時効期間がリセットされることがあります。時効を中断させる事由は以下の3つです。
①請求
債権者が裁判所に対して支払請求の訴訟または督促手続きを行った場合(通常の催促行為(催告)から6か月以内に行う必要がある)
②差押・仮差押・仮処分
債権者が債務者の財産の差押、仮差押、仮処分を行った場合
③承認
債務者が債権者に対して債務の承認(借金の返済をしたり、延滞の相談を持ちかけたりすることなど)を行った場合
なお、主債務者の時効期間が伸びた場合には、保証債務の時効も一緒に伸びることになります。一方で、保証債務は時効が完成していないけれど、主債務は時効が完成したという場合には、保証債務者は、主債務の時効を援用する(主張する)ことによって、債務の支払いを免れることができます。
3. 連帯保証人の地位を相続した場合の対処法は?
保証債務の存在を知らずに相続を完了してしまうと、ある日突然身に覚えのない高額請求が届くことがあります。ここでは、すでに相続してしまった保証債務の対処法を紹介します。
(1)その時点で相続放棄をする
亡くなった時点では全く知らなかった債務が、後に明らかになったという場合には、亡くなってから3か月を経過していたとしても、相続放棄ができる可能性があります。(2)以下の行動をとった後では、相続放棄をすることができなくなってしまいますので、まずは相続放棄を検討しましょう。
(2)時効が成立していないか検討し、成立しているのであれば時効を援用する
上記のとおり、時効が成立している可能性があります。時効が成立していれば、返済する必要はありませんので、時効の成立は確認しましょう。確認したところ、時効が成立しているということでしたら、債権者に対して時効を援用して(時効が成立していることを主張して)、債務を消滅させましょう。
(3)債権者に対して債務の減額や支払い方法の交渉をする
請求された金額の支払いが難しい場合、まずは債権者と債務の減額や支払い方法についての交渉をしてみましょう。債権者としては、債務者が破綻してお金をまったく回収できなくなるのは避けたいところですから、減額や支払い方法(分割払いなど)について話し合いができる場合もあります。
(4)相続分に応じた金額を返済し、主債務者に対して求償請求を行う
全額を請求されたとしても、自身の相続分に応じた金額しか支払う必要はありません。支払った後に、主債務者に求償を行うことができます。
(5)任意整理を行う
任意整理とは、依頼した弁護士や司法書士が債権者と利息の減額や分割による返済などについて交渉し、今後の返済計画について和解して、返済計画にもとづいて債務を返済することです。利息制限法で定められた利率を超える利率の債務が対象となります。任意整理後5年から10年程度は新たな借り入れなどができなくなります。
(6)個人再生を行う
個人再生は、債権者に対して債務の減額を申し出た上で、減額後の債務を原則として3年間で分割返済する計画(再生計画)を立て、裁判所が認めた場合に行える返済手続きのことです。小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続との2種類があり、債務総額が住宅ローンを除く5000万円以下であること、債務者に継続的な収入が見込めることなどの条件があります。
(7)自己破産を行う
自己破産とは、裁判所に申し立て、返済不能であると裁判所が認めた場合、一部を除いて一定以上の価値のある財産をすべて清算して返済にあてるとともに、残る債務の返済を免除してもらう手続きです。
自己破産後に手元に残せるのは20万円以下の預貯金や99万円以下の現金、洗濯機や冷蔵庫などです。債務を返済する必要はなくなりますが、一定期間、特定の職業に就けなくなったり、クレジットカードや借り入れを利用できなくなったり、官報に名前が掲載されたりと、数多くのデメリットがあります。
連帯保証人の債務を相続した場合、手続きを経ることで借金を減額したり、ゼロにしたりできる場合があります。しかし、こうした手続きには法的な判断や知識が必要です。まずは、弁護士などの専門家に相談しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2023年09月12日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年07月15日
- 遺産相続
-
- 2024年05月10日
- 遺産相続
-
- 2024年03月08日
- 遺産相続