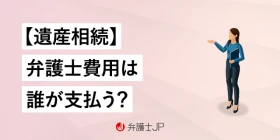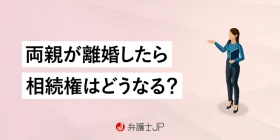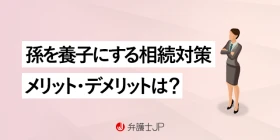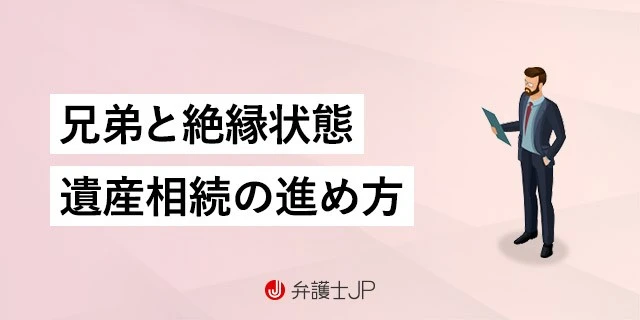
絶縁した兄弟との遺産相続で注意することは?
兄弟と絶縁しており、二度と顔も合わせたくないという方もいるでしょう。しかし、兄弟と絶縁していても、遺産相続の際には話し合いが必要です。
この記事で「絶縁した兄弟との遺産相続での関わり方」について把握し、スムーズに遺産分割ができるようにしましょう。
1. 兄弟と絶縁していたら遺産相続には関係ない?
兄弟と絶縁している場合、相続についての話し合いや財産の分配などに関係がないと思っている方もいるかもしれません。しかし、絶縁していても、兄弟が法定相続人である限りは遺産を相続する権利があります。
(1)法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。亡くなった方(被相続人)に遺言がない場合に、その方の財産(遺産)を受け取れます。法定相続人は、配偶者が優先されたうえで、そのほかの親族については次のように順位が付けられます。
- 子ども(すでに死亡している場合はその子ども)
- 直系尊属(親や祖父母)
- 兄弟姉妹(すでに死亡している場合はその子ども)
下位の法定相続人は、上位の法定相続人がいない場合に相続できます。つまり、第2順位の親や祖父母は亡くなった方に子どもや孫がいない場合に、第3順位の兄弟姉妹は亡くなった方に子どもや親・祖父母などが誰もいない場合にのみ、相続できるということです。
相続人となった親族は、亡くなった方に配偶者がいればその方と遺産を分け合い、配偶者もいなければすべて相続できます。
また、相続の対象になっている遺産は、分割が済むまではすべての相続人の法定相続分に応じた共有状態にあります。そのため、分割前に預貯金を引き出すなど財産を勝手に処分することはできません。法定相続分とは、法定相続人が受け取れる遺産の割合のことで、次のように決まります。
- 配偶者:ほかの法定相続人に応じて決まる
- 子ども:1/2(複数いる場合は均等に分ける)
- 親もしくは祖父母:1/3(複数いる場合は均等に分ける)
- 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は均等に分ける)
たとえば、相続人が配偶者と子ども1人の場合は配偶者1/2、子ども1/2です。配偶者と子ども2人の場合は、配偶者が1/2、子どもは1/4(1/2÷2人)ずつ分けます。配偶者と兄弟3人の場合は、配偶者が3/4、兄弟が1/12(1/4÷3人)ずつです。
ただし、上記はあくまで法律上の割合です。上記以外の割合で分ける場合は、相続人全員で話し合ったうえで合意する必要があります。絶縁状態の兄弟も相続人としての権利があるため、ほかの相続人の意思で勝手に相続の対象者から除外することはできません。
(2)遺言で相続の対象から外されていても遺留分がある
法定相続分は、遺言で相続人が指定されていないときにおける、遺産分割の配分です。遺言がある場合、その内容が優先されます。たとえば、遺言で「配偶者には不動産全部、長男には貯金全額、次男にはなし」という指定があれば、その通りに分割するのが基本です。
ただし、法定相続人には遺留分という最低限の取り分があります。仮に絶縁状態の兄弟が遺言で相続から排除されていても、その兄弟が亡くなった方の子どもである以上は法定相続人であることに変わりはないので、兄弟は遺留分を請求できます。
遺留分の割合は「法定相続分の半分」です。たとえば本来もらえる法定相続分が1/4であれば、その半分である1/8を遺留分として請求できます。実際に相続した人に遺留分侵害額請求を行い、現金で遺留分を支払うよう請求することができます。
以上のことから、兄弟間で絶縁しているだけでなく、兄弟の誰かが遺言によって相続の対象者から外されているような状態であっても、相続時に関わってくる可能性があります。
(3)遺言とは異なる遺産分割をしたい場合も兄弟が関わってくる
遺言があればその内容にしたがって分割するのが原則ですが、相続人全員の同意があれば、その内容とは異なる割合で分割することは可能です。その場合も、絶縁している兄弟に相続人としての権利がある限り、同意を得なければいけません。
2. 絶縁した兄弟の連絡先が分からない場合は?
遺産分割協議を行うにあたって、絶縁状態にあり連絡が取れない・連絡先が分からない場合はどのように対処したら良いのでしょうか。以下の3つの方法が考えられます。
(1)戸籍の附票を取り寄せる
戸籍の附票は、戸籍に載っている人の、戸籍が作成されてから現在までの住所が記録されている書類です。本籍地で戸籍原本と一緒に保管されています。戸籍の附票を取り寄せることで、絶縁した兄弟の現在の住所を調べられる可能性があります。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に出向くか、郵送やインターネットで申請することで取得が可能です。原則として戸籍の附票に記載されている本人が直接申請するか、配偶者や直系親族(親や子ども)、または委任状を持った代理人が申請する必要があります。
(2)不在者財産管理人を選任する
不在者財産管理人とは、所在不明な人がいる場合に、その人の財産を管理するために家庭裁判所が選任した人のことです。不在者財産管理人は、裁判所から権限外行為許可を得ることで遺産分割協議に同意できるため、「遺産分割協議をしたいけど兄弟と連絡が取れない」という問題を解決できます。
ただし、不在者財産管理人の選任は家庭裁判所への申し立てが必要であるため、手続きに手間と時間がかかります。
(3)失踪宣告の申し立てを行う
失踪宣告とは、家庭裁判所に対して、一定期間連絡が取れない・消息が分からない人について「死亡した」と宣告してもらう手続きです。生死が7年間明らかでないときや、震災などで生死が1年以上不明なときに利用できます。
家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、調査官による調査が実施されます。その後、「生存している場合は届け出ること」という催告を官報などで行い、しかるべき期間が過ぎても届け出がない場合、失踪宣告がなされます。
失踪宣告が行われると、その方は死亡したものとして扱われます。被相続人の死亡よりも前に亡くなったものとして扱われると相続権がなくなるため、ほかの相続人だけで遺産分割が可能です。
ただし、失踪宣告の申し立てから確定まで1年ほどかかるため、相続税が発生する場合は納付期限(10か月)に間に合いません。また、失踪宣告された方に子どもがいれば、子どもに相続権が発生します。このように失踪宣告には留意点があるため、まずは(1)や(2)の方法を検討するのが一般的です。
絶縁状態であっても、遺産分割協議はすべての相続人が参加していないと成立しません。また絶縁状態にある兄弟と遺産分割協議を行う場合、話し合いのなかで衝突してしまうなどトラブルが悪化する可能性があります。
そのため、絶縁状態の兄弟がいる場合の相続については、弁護士への相談がおすすめです。弁護士は、遺産分割協議の進め方や手続きの方法などを専門的にアドバイスしてくれます。また、絶縁した兄弟の連絡先を調査して兄弟とやり取りしたり、不在者財産管理人や失踪宣告の申し立てを代行したりすることも可能です。
- こちらに掲載されている情報は、2023年08月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年07月15日
- 遺産相続
-
- 2024年05月10日
- 遺産相続
-
- 2024年03月08日
- 遺産相続