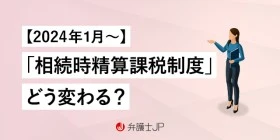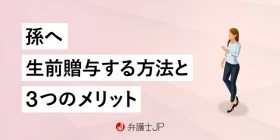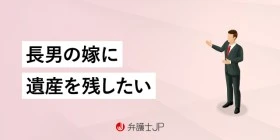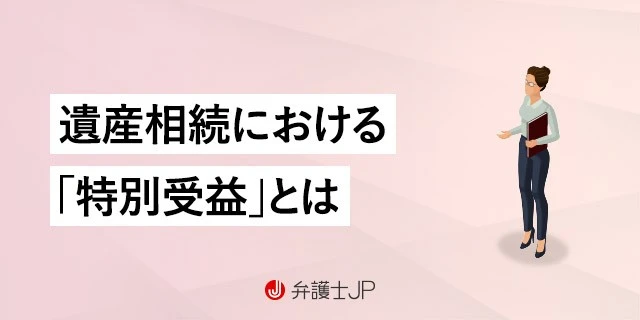
特別受益とは? 生前贈与との違いや対象者について解説
一部の相続人が被相続人によって優遇され、遺贈・生前贈与を受けた場合には、特別受益が認められることがあります。
特別受益が認められるかどうかは、各相続人の相続分に直結するため、遺産分割において揉めやすいポイントです。必要に応じて弁護士にご相談のうえ、特別受益の問題の円満な解決を目指しましょう。
今回は特別受益について、生前贈与との関係性や対象者の範囲、相続分の計算方法、相続人間の話し合いがまとまらない場合の対処法などを解説します。
1. 特別受益とは? 対象・生前贈与との関係性
「特別受益」とは、被相続人から相続人が特別に受けた遺贈(遺言による贈与)・生前贈与を意味します(民法903条1項)。
特別受益に該当するのは、相続人に対する以下の遺贈・贈与です。
- すべての遺贈
- 以下のいずれかに該当する贈与(死因贈与・生前贈与)
・婚姻のための贈与
・養子縁組のための贈与
・生計の資本としての贈与
生前贈与については、そのすべてが特別受益に該当するわけではありません。
特別受益に該当する生前贈与は、相続人(法定相続人・推定相続人)を受贈者とするものに限られます。特別受益は相続人間の公平を図ることを目的とした制度であるため、特別受益者が相続人に限定されているのです。
さらに、特別受益に該当する生前贈与は「婚姻のための贈与」「養子縁組のための贈与」「生計の資本としての贈与」に限定されており、それ以外の目的の生前贈与は特別受益に該当しません。しかし、「生計の資本としての贈与」の範囲は広く解されているため、相続人に対する生前贈与であれば、実務上はほとんどすべて特別受益に該当すると考えられます。
2. 特別受益がある場合の相続分の計算方法
一部の相続人に特別受益が認められる場合、「持ち戻し計算」を行って各相続人の相続分を計算します。
ただし、被相続人による「持ち戻し免除」の意思表示がある場合には、特別受益を考慮せずに相続分を計算する点にご注意ください。
(1)「持ち戻し計算」を行う
「持ち戻し計算」とは、特別受益の対象である遺贈・贈与の金額が相続財産に含まれていると仮定して、各相続人の相続分を計算することを意味します。
具体例を用いて、実際に持ち戻し計算を行ってみましょう。
(例)
- 相続財産の総額は3000万円
- 相続人は子A、子Bの2人
- Aは被相続人から1000万円の生前贈与を受けていた(=特別受益)
Aの特別受益1000万円を相続財産3000万円に持ち戻して、4000万円を基準にA・Bの暫定的な相続分を計算します。A・Bはいずれも被相続人の子なので、法定相続分は2分の1ずつです。したがって、A・Bの暫定的な相続分は、各2000万円となります。
しかし、Aにはすでに1000万円の特別受益があるため、Aの相続分から1000万円を控除します。よって、最終的な相続分は、Aが1000万円、Bが2000万円です。
(2)持ち戻しの免除について
特別受益の「持ち戻し」は、被相続人の意思表示によって免除することが認められています(民法903条3項)。持ち戻しの免除が認められているのは、遺産分割の方法について、被相続人の意思を最大限反映させるためです。
持ち戻し免除の意思表示について、特に方式は定められていません。したがって、遺言書をはじめとする書面のほか、口頭での持ち戻し免除も認められます。ただし実際には、持ち戻し免除があったことの証明が必要になるため、書面で意思表示を行うことが望ましいでしょう。
なお、被相続人との婚姻期間が20年以上である配偶者が、被相続人から居住用建物・敷地の遺贈・贈与を受けた場合、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます(同条4項)。この推定規定は、相続手続きにおいて配偶者の住居を確保するため、2019年7月1日施行の改正相続法により新たに設けられたものです。
3. 特別受益についての話し合いがまとまらない場合の対処法
相続開始後、特別受益について相続人間で揉めてしまい、話し合いがまとまらない場合には、以下のいずれかの方法により解決を図りましょう。
(1)弁護士による遺産分割協議の調整
客観的な立場である弁護士が調整を行うことにより、すべての相続人が納得できる解決の実現が近づきます。
(2)遺産分割調停
家庭裁判所の調停委員による仲介の下、冷静な話し合いを行って遺産分割の合意を目指します。
(3)遺産分割審判
家庭裁判所が審判によって結論を示し、強制的に遺産分割トラブルを解決します。
いずれの手続きによる場合でも、弁護士と協力して法的に根拠のある主張を行うことが、有利な結果の獲得に繋がります。特別受益など、遺産分割に関するトラブルにお悩みの場合は、お早めに弁護士までご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2022年11月04日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年10月05日
- 遺産相続
-
- 2023年08月24日
- 遺産相続
-
- 2023年03月20日
- 遺産相続