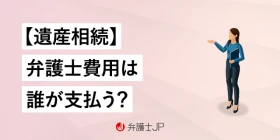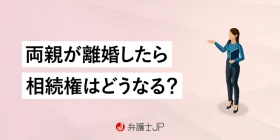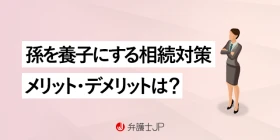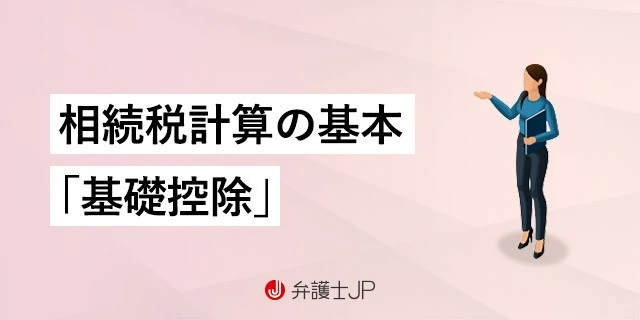
相続の基礎控除とは? 計算方法をわかりやすくご紹介します
相続によって多額の遺産を取得することになった方は、「高額な相続税を支払わなければならないのではないか」と不安に感じていることもあります。相続が開始した場合には、相続税の基礎控除を正確に理解し、相続税の申告が必要なケースかどうかを判断することが重要です。
今回は、相続税の基礎控除について計算方法などを挙げながらわかりやすく解説します。
1. 相続の基礎控除とは
平成27年の税制改正によって相続税の基礎控除額が減額され、相続税の課税対象となるケースが増えています。相続税の基礎控除は、相続税計算の基本になりますので、きちんと理解しておくことが重要です。
(1)基礎控除額の範囲内なら相続税は非課税
相続によって被相続人の相続財産を相続することになった場合には、相続税が課税されることになります。しかし、相続税を計算する際には、課税対象となる相続財産が一定の金額以下であれば、相続税は課税されず、相続税申告も不要になります。この相続税が非課税となる一定の金額のことを「基礎控除額」といいます。
(2)相続税の基礎控除の計算方法
相続税の基礎控除額は、以下のように計算します。
相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、被相続人が死亡し、相続人が被相続人の子ども3人だった場合には、4800万円が基礎控除の金額になります。そのため、課税対象の遺産の合計額が4800万円以下であれば相続税は非課税となり、相続税申告も不要です。
(3)相続税の基礎控除の注意点
相続税の基礎控除額を計算する際には、以下のような点に注意が必要です。
①相続放棄をした相続人がいる場合
相続放棄をすることで、遺産相続の手続き上は、当初から相続人ではなかったものとみなされます。しかし、相続税の基礎控除の計算上は、相続放棄をしたとしても、法定相続人の数に含めて計算することになります。
また、相続放棄をしたことによって、次順位の法定相続人に相続権が移ったとしても、基礎控除を計算する際の法定相続人の数は、当初の法定相続人を基準にします。
②代襲相続が発生した場合
被相続人が亡くなる前に、被相続人の子どもが亡くなり、被相続人に孫がいた場合には、代襲相続によって孫が被相続人の遺産を相続することになります。そして、相続税の基礎控除の計算上は、本来の相続人ではなく代襲相続人の数を基準に計算します。そのため、代襲相続人として、被相続人に孫が2人いた場合には、法定相続人の数は1人ではなく、2人を基準として計算することになります。
③法定相続人以外の受遺者がいる場合
相続税の基礎控除の計算となる人数は、あくまでも「法定相続人の数」です。遺言書を作成することによって、相続人以外の第三者に対しても遺産を渡すことができますが、このような受遺者は、法定相続人にはあたりませんので、基礎控除の計算上は考慮しません。
④被相続人が養子縁組をしていた場合
被相続人が養子縁組をしていた場合には、遺産相続の手続きにおいては、養子にも実子と同様に相続権が認められます。しかし、養子の場合には、相続税の基礎控除を計算する際の法定相続人の数に含めることができる人数に、以下のような上限が定められています。
- 被相続人に実子がいる場合……1人まで
- 被相続人に実子がいない場合……2人まで
相続税対策として養子縁組を利用される方もいますが、上限を超える養子縁組には節税の効果はありませんので注意が必要です。
2. 基礎控除の計算例
法定相続人が被相続人の妻、長男、長女、次男の4人で、被相続人の遺産が9000万円であったというケースで相続税の金額を計算してみましょう。
(1)課税財産を計算
まずは遺産総額から法定相続人の数に応じた基礎控除の額を差し引いて課税財産を計算します。上記の例では、被相続人の数は4人ですので、基礎控除の額は5400万円となります。したがって、上記の例での課税財産は、以下のとおり3600万円となります。
相続税の課税財産=遺産総額(9000万円)-基礎控除額(5400万円)
(2)課税財産を法定相続分で分割
相続税の課税財産の計算ができたらそれを法定相続分で分割します。遺産分割協議に基づく相続割合ではなく、「法定相続分」ですので注意しましょう。
妻:1800万円
長男:600万円
長女:600万円
次男:600万円
(3)相続人別で相続税を計算
相続税の課税財産を法定相続分割合で分割したら、次は、各相続人の税額を計算します。
各相続人の税額の計算方法は、以下の計算式に基づいて行います。
各相続人の税額=各相続人の課税財産×税率-控除額
妻:1800万円×15%-50万円=220万円
長男:600万円×10%=60万円
長女:600万円×10%=60万円
次男:600万円×10%=60万円
(4)相続税の総額を計算
相続人別で計算した相続税を合算したものが、被相続人の相続財産に課税される全体の相続税となります。
220万円+60万円+60万円+60万円=400万円
(5)相続人ごとの納付税額を計算
次に全体の相続税を遺産分割協議や遺言書による実際の取得割合に基づいて、各相続人の納付税額を計算します。今回は、実際の取得割合が法定相続分と同じものとして計算します。
妻:400万円×1/2=200円
長男:400万円×1/6≒66万6666円
長女:400万円×1/6≒66万6666円
次男:400万円×1/6≒66万6666円
(6)税額控除を適用
上記で算出した各相続人の納付税額に対して各種税額控除を適用して最終的な納付税額を算出します。上記例では、配偶者控除を利用することができますので、最終的には、以下のような相続税額になります。
妻:0円
長男:66万6666円
長女:66万6666円
次男:66万6666円
- こちらに掲載されている情報は、2022年06月17日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年07月15日
- 遺産相続
-
- 2024年05月10日
- 遺産相続
-
- 2024年03月08日
- 遺産相続