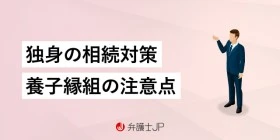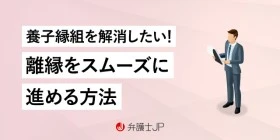特別養子縁組が成立するための条件とは?
子どもがいない夫婦にとって、特別養子縁組によって子どもを迎えることは人生の光ともいえるでしょう。養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、特別養子縁組のほうが厳しい条件が設定されています。
本記事では、特別養子縁組を検討している方のため、普通養子縁組との違いや縁組の条件についてご紹介します。
1. 普通養子縁組と特別養子縁組の違い
養子縁組とは、血縁関係のない子どもと法的な親子関係を構築するための民法上の制度です。家名や財産の承継、親を亡くした子どもの養育、相続税対策など、さまざまな目的で行われます。
養子縁組には、「特別養子縁組」と「普通養子縁組」があります。それぞれ、どのような違いがあるのでしょうか。
(1)普通養子縁組とは
「普通養子縁組」も「特別養子縁組」も、養親となった親と養子との間に法律上の親子関係が生じる点では同じです。
ただし、普通養子縁組では、子どもと実親(生物学上の親)との法的な親子関係は消滅せずに維持されます。
つまり、養子縁組をした子どもには、実親と、養親の2組の親が存在することになります。
したがって、普通養子縁組の場合、実親と養親の双方に対して法定相続人となる権利を有します。
普通養子縁組には養子縁組の届出が必要です。
普通養子縁組の養親となるには、20歳以上、もしくは婚姻している必要があります。
婚姻している人が未成年者を養子にする場合は夫婦一緒に養親にならなければなりません。
普通養子縁組の養子に年齢制限はありません。
ただし、養親より年上であってはならず、また、養親の叔父や叔母より年上であってもなりません。
養子になる子どもが未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。15歳未満の場合は、法定代理人による本人に代わる縁組の承諾も必要です。
普通養子縁組を解消したい場合は、養親と養子の同意があれば、離縁届を提出することで離縁できます。協議しても同意できない場合は、調停や裁判で離縁する方法もあります。
養子は養親の戸籍に入り、養親の氏になります(結婚時に氏を変更した養子は除く。)。戸籍には、養親とともに実親の名前も記載され、養子の続柄は、単に「養子(養女)」 となります。長女、次男といった記載にはなりません。
(2) 特別養子縁組とは
特別養子縁組は、いろいろな事情で実親と生活をすることができない子どものために、新たに養親子関係を構築し、子どもの健全な養育を図ることを目的とする制度です。
普通養子縁組とは異なり、特別養子縁組では、実の親(生物学上の親)との法的な親子関係が解消されます。子どもにとっての親は養親だけとなり、実の親とは法律上の他人となります。
そのため特別養子縁組では、実親が亡くなってもその遺産を相続することはできず、養親の遺産に対する相続権のみ有することになります。
特別養子縁組では、親と子の合意だけでは成立せず、家庭裁判所の審判による決定が必要です。また、特別養子縁組をするためには、実父母の同意が必要です(ただし、実父母が意思表示できない場合、養子となる者の利益を著しく害する理由(虐待など)がある場合は除く。)。
養親は25歳以上(夫婦のどちらかが25歳以上ならば他方は20歳以上でも可)、そして、既婚者であることが条件です。
養子になれるのは15歳未満の子どもです。
特別養子縁組ができるのは、実親の監護が著しく困難等の場合で、あくまで子どもの利益のために特に必要がある場合に限られます。
特別養子縁組を解消は原則できません。離縁ができるのは、養親による虐待がある場合など、養子の利益のため特に必要があるときに限られます。その場合は、例外的に家庭裁判所の審判により特別養子縁組が解消できます。
戸籍には、実親の名前は記載されず、養親との関係は「長女」、「次男」などと続柄が記載されます。
(3)里親について
なお、養子縁組に似た制度として里親制度があります。いろいろな事情で実親と暮らせない子ども(原則18歳まで)を、都道府県知事の委託により、一時的あるいは継続的に、他の家庭(里親)が預かり育てる行政上の制度です。養子縁組とは異なり、里親は子どもとの間に法律上の親子関係はなく、親権者は実親で、戸籍も変わりません。
2. 特別養子縁組の条件
特別養子縁組は実親(生物学上の親)との親子関係を解消してしまう制度ですので、要件が厳しく定められています。養子になれるのは15歳未満の子どもに限られますし、特別養子縁組をするためには養親となる者から家庭裁判所に審判の請求をし、親の側が次のすべての要件を満たさなければなりません。
(1)夫婦が共同で養親になること
未婚者は特別養子縁組で子どもを迎えることができません。
(2)養親が25歳以上であること(夫婦の一方が25歳以上ならばもう一方が20歳以上でも可能)
年齢制限を満たさない場合は、年齢に達してから申し立てをするしかありません。
(3)実の両親の同意を得ること
ただし、実親の意思表示ができない場合や、虐待や悪意の遺棄など、子の利益を著しく害する事情がある場合は不要となることがあります。
(4)子の利益のため特に必要があること
実父母による監護が著しく困難または不適当である場合を指します。具体的には、親からの虐待や育児放棄を受けて児童養護施設や里親のもとで暮らしている場合や、実親が行方不明で児童相談所に保護されている場合、実親が病気などで子どもを育てることができず親せきや知人に養育されている場合などが該当します。
(5)6か月以上の監護実績(一緒に暮らして親子としての生活を実際に行った実績)があり、その期間の監護状況からして特別養子縁組を成立させるにふさわしいといえること
3. まとめ
養子縁組は、さまざまな事情で実の親と暮らせない子どもが、新しい家族の愛情を受けて育つことができる制度です。養親にとっても養子にとっても、新しい家族関係が生まれることは大きな喜びです。特別養子縁組制度を検討している方は、まずは、養子縁組あっせん事業者などへ相談してみることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2021年06月18日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

家族・親子に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年06月08日
- 家族・親子
-
- 2023年05月09日
- 家族・親子
-
- 2021年08月12日
- 家族・親子