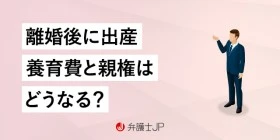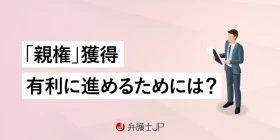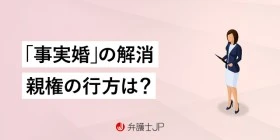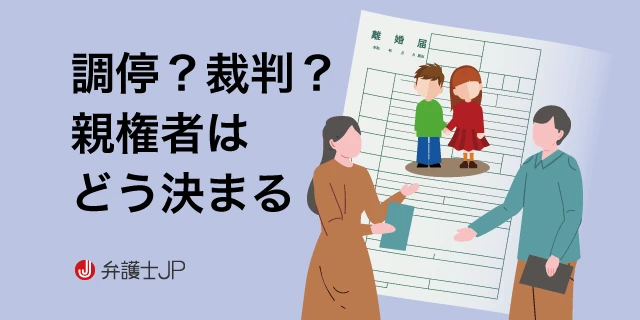
親権争いを有利に進めるためには? 重視される事情を解説
離婚を検討する夫婦の間に未成年の子どもがいるときには、父親と母親のどちらが親権者になるかを決めなければ、離婚することはできません。
父母双方が親権の獲得を希望して譲らない場合には、裁判所の手続きのなかで親権者を決めることができます。そのため親権を獲得したいのであれば、裁判所での親権争いではどのような事情が有利に働くのかを理解しておくことは非常に重要です。
1. 親権争いで有利になる事情とは
裁判所は、「父親と母親のどちらが親権者になることが子どもの利益や幸福にかなうのか」を判断基準にして、次のような事情を総合的に考慮して親権者を決めます。
もっとも、具体的にどのような事情が親権獲得に有利に働くかは、ケースに応じた判断が必要になるため、弁護士などに相談することがおすすめです。
(1)親側の事情
親権者を判断する上では、
- 子どもへの愛情の深さ(親権者になることへの意欲の強さ)
- 親権者として子どもを育てる能力や条件(親の年齢や心身の健康状態、時間的な余裕、経済力、実家などの援助の有無)
- 離婚後の生活環境(住環境、学校環境)
などの父母それぞれの事情が考慮されます。これらの事情が子どもにとって好ましい方が、親権獲得に有利になるといえます。
なお経済力に関しては、収入の多い親から少ない親に養育費が支払われることになるため、低いからと諦める必要はありません。そのため専業主婦(主夫)だからといって、親権の獲得に不利になるというわけではないことを知っておきましょう。
(2)子ども側の事情
親側の事情だけでなく、
- 子どもの年齢や性別
- 子どもの意向
- 兄弟姉妹の関係
- 心身の発育状況
などの子ども側の事情も考慮されます。
(3)特に重視される事情
特に重視される傾向にあるのは、次のような事情です。
①監護の実績・継続性
これまで子どもを主に養育してきた親が継続して養育することが子どもにとってのぞましいという考え方です。この考え方によると、現在子どもと暮らす親が有利になる可能性が高くなります。
②子どもの意思の尊重
子どもが幼いうちは、その意思はあまり重視される事情にはなりません。しかし15歳以上の子どもに関しては、子どもの意思を確認し尊重することとされています。実際には、10歳頃から子どもの意思を反映した判断になることも少なくないようです。
③兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹がいるときには、基本的に同じ親のもとで一緒に暮らせるようにするという考え方がなされます。
④母性優先の原則
子どもと心理的に強い結びつきが強い親を優先するという考え方がなされます。母性とありますが、必ずしも母親が父親に優先するということではありません。
⑤面会交流への寛容性
親権者になったときに、元配偶者と子どもとの面会交流に寛容であることも重要だという議論があります。いわゆる、フレンドリーペアレントルールです。この点については、千葉家庭裁判所松戸支部平成28年3月29日判決を端緒に、最高裁まで争われたりもしました。
2. 調停? 裁判? 親権者を決める方法
親権者は、以下のような方法で決めることになります。なお親権のなかに監護権(子どもと一緒に暮らし身の回りの世話をする権利)が含まれますが、親権者と監護権者を父母それぞれで分ける決め方もできます。
(1)父母で話し合い決定する
父母の協議で離婚することに合意できた場合には、どちらが親権者になるかについても話し合う必要があります。話し合いで親権者を決定できた場合には、離婚届に親権者を記載して提出することによって協議離婚が成立します。
(2)離婚調停で話し合い決定する
父母の話し合いで離婚に合意できない場合や親権争いがある場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用して解決を図ることができます。
調停では、父母のどちらが親権者としてふさわしいかを判断するために、家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります。調停は、調停委員を交えて夫婦が話し合う手続きなので、調査官の調査結果などをもとに話し合って合意できれば親権者が決定することになります。
(3)離婚裁判で裁判所が決定する
調停での話し合いがうまくいかないときには、離婚裁判を起こしてその判決で親権者についても決定することができます。裁判所が親権者を決定する上では、先ほどご説明した事情などが総合的に考慮されることになります。
3. 親権者になれなくても面会交流はできる
「親権争いに敗れたら子どもと会えなくなってしまう」と思っている方もいらっしゃるようです。しかし親権者になれなかったとしても、子どもの親であることは離婚後も変わりはありません。
そのため、離れて暮らす子どもと定期的に連絡を取り合ったり直接会ったりする「面会交流」が認められています。これは、特別な事情がない限り、子どもにとっては、父母双方と交流を持つことが健全な成長につながると考えられているためです。
面会交流の内容については、父母の話し合いや調停、審判で取り決めることができます。調停や審判においては、自分がどのように子どもと付き合っていけるかについて、複数の可能性を考えて、いずれにしても子どもとの関係を望ましい形で続けていく方法を、模索していく姿勢が有益かもしれません。
- こちらに掲載されている情報は、2022年01月14日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年07月24日
- 離婚・男女問題
-
- 2022年11月18日
- 離婚・男女問題
-
- 2022年11月10日
- 離婚・男女問題