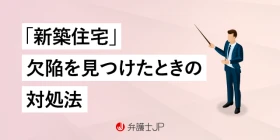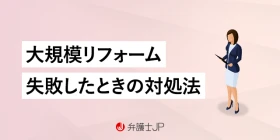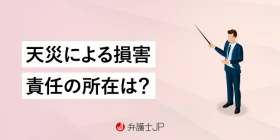- (更新:2021年07月15日)
- 不動産・建築・住まい
購入した家が欠陥住宅だったとき、損害賠償請求はできるのか?
新築戸建てを購入後に欠陥が見つかったものの、業者の対応がなされずに困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では、欠陥住宅の売り主に対して損害賠償請求する方法について解説していきます。
1. 欠陥(瑕疵)とは?
まずは、欠陥住宅の損害賠償請求の際に必ず登場する、「瑕疵(かし)」という言葉の意味や判断基準について解説します。
(1)法律上の「瑕疵」とは
住宅における瑕疵とは、売買契約に従って住宅の引き渡しや工事の完了をしたものの、約束どおりの「性能」「品質」が確保できていない状態を意味します。
たとえば、「住宅が傾いている」、「屋根の防水処理が誤っていたために引き渡し当日に雨漏りが発生した」というケースは「瑕疵がある」と判断される可能性が高い例です。
また、「トイレが設置されていなかった」というように、あらかじめ決めておいた設備が取り付けられていなかった場合も、瑕疵といえるでしょう。
ただし、「自分の想像していたイメージと違った」という個人の主観的な意見の場合は瑕疵に該当しない場合があるので注意が必要です。
(2)民法で規定された契約不適合責任を負う
前述したような瑕疵があった場合、民法上、売り主は「契約不適合責任」を負います。令和2年4月に施行された民法(債権法)改正までは、瑕疵担保責任と呼ばれていたものです。内容も改正前とは大きく異なる点があります。
改正民法における契約不適合責任については、「契約の内容に適合しない」とき、追完請求、代金減額請求、損害賠償、解除が可能とされています(改正民法562~564条)。また、買い主が契約不適合を知ったときから1年以内に通知をすれば、権利行使を行えることになっています(改正民法566条)。
なお、改正前民法では、契約締結時に買主にはわからない状況にあった瑕疵を「隠れた瑕疵」といい、売り主に瑕疵担保責任がありました。改正民法では、瑕疵があること自体が「契約の内容に適合しない」とされ、売り主に契約不適合責任が生じることになります。
(3)住宅の品質確保の促進等に関する法律
新築住宅の瑕疵担保責任については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定されています。同法において、原則として新築住宅は売り主が10年間「瑕疵担保責任」を負うことが規定されているのです。
なお、民法改正に伴い、同法は瑕疵の定義規定が新設され、「「瑕疵」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう」(第2条5項)と明記されました。
2. 欠陥住宅だった場合、誰に損害賠償請求できる?
購入した住宅に欠陥があった場合、「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」は、ケースにもよりますが、売り手・請負人の両方が責任を負うことなります。瑕疵があった場合には、住宅を建築した施工業者や外注業者、ハウスメーカーや建築会社、不動産会社など、どこへ損害賠償請求を行うべきなのか、慎重に見極めることが大切です。
ハウスメーカーや建築会社などが「住宅瑕疵担保責任保険」に加入している場合は、保険会社が修理費用を保険金として支払うケースもあります。また、中古住宅でも加入している場合がありますので契約の際に確認しておきましょう。
不動産会社等が賠償責任を果たさない場合は、宅地建物取引業保証協会に苦情を申し立てることも可能です。
3. 生命や財産に危険が及ぶ瑕疵の場合は不法行為による損害賠償請求を検討
「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合」(最判平19.7.6)は「不法行為」に基づく損害賠償請求が認められる可能性がありあます。
この場合は、不法行為に基づく損害賠償請求となりますので、時効は欠陥を知ってから3年、もしくは工事完了から20年です(民法724条)。
不法行為に該当する場合は、売り主だけでなく、建築会社や施行した業者、工事の監督者などにも損害賠償を請求することができます。
購入後に自分の家が欠陥住宅であるとわかった場合は、そもそも、欠陥住宅といえるのかどうかなど、建物の調査については建築士に依頼をしたほうがよいでしょう。そのうえで、欠陥住宅であることが明らかにできた場合は、基本的には売り手に対して損害賠償請求などを行うことになります。
その場合、まずは話し合いが行われ、そこで結論を出せなければ調停、訴訟と進むことになるでしょう。とはいえ、売り手のほうが法律に詳しいなど、個人で対応するには限界があると考えられます。交渉の負担を少しでも軽減し、トラブル解決を目指すのであれば、弁護士に相談したうえで進めたほうがよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2021年07月15日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

不動産・建築・住まいに強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年02月22日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2024年02月14日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2024年02月06日
- 不動産・建築・住まい
不動産・建築・住まいに強い弁護士
-
寺田 弘晃 弁護士
神楽坂総合法律事務所
●東京メトロ地下鉄 飯田橋駅B3出口より 徒歩約5分
●JR飯田橋駅西口より 徒歩約6分
●都営大江戸線 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分
●東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
弊所は、1階に【 新宿神楽坂郵便局 】や【 カフェ・ベローチェ 】が所在する、オザワビルの6階です。
神楽坂のシンボル【 毘沙門天 善國寺 】がビルの目の前にございます。
▶▷▶ 事務所ホームページ
https://shinjuku-houritusoudan.com/電話番号を表示する 03-5206-3755- 休日相談可
- 夜間相談可
- 24時間予約受付
- 全国出張対応
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
▶ ▷ ▶ 土日祝日・夜間のご相談は、予めお問合せ下さい