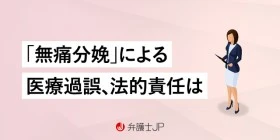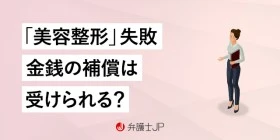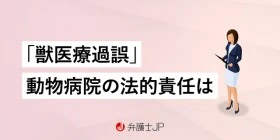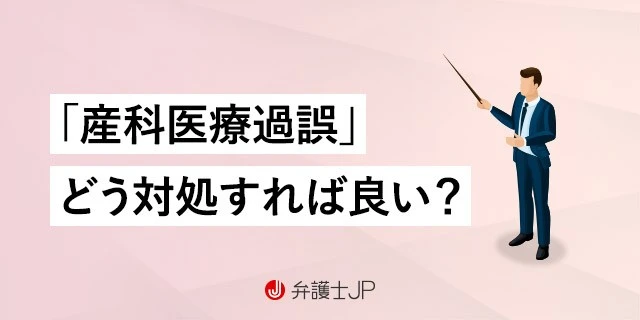
妊婦が医療過誤に遭ったらすべきことは?
母親が新生児を分娩(ぶんべん)する際には、医療過誤(医療事故)が発生するケースがあります。
もし医療過誤により、母親または胎児(新生児)が死亡し、または障害が残ってしまった場合は、医療機関側に対する損害賠償請求をご検討ください。
今回は産科医療過誤の例や、妊婦が医療過誤に遭ってしまった場合の対処法などを解説します。
1. 産科医療過誤とは
産科医療過誤とは、新生児の分娩に際して行われる医療行為につき、医療機関側のミスが介在した結果、母体や胎児の死亡・障害が発生することを意味します。
たとえば、以下に挙げる事例が産科医療過誤に該当します。
<母体に関する産科医療過誤の例>
- 分娩中の切開ミスに起因する出血多量により、母体が死亡した
- 分娩中に発生した心不全への処置ミスにより、母体が死亡した
- 分娩中に発生した心不全の回復が医療機関側のミスによって遅れ、母体に障害が残った
など
<胎児に関する産科医療過誤の例>
- 娩出直前に臍帯(さいたい)圧迫による急激な徐脈が行われた結果、新生児が胎便吸引症候群に陥って死亡した
- 分娩中に母体へ投与した薬剤が原因で、新生児の循環不全が起こった結果、新生児に脳性まひが残った
- 分娩時に無理な牽引を行った結果、新生児が重要な神経を損傷した
など
2. 妊婦が医療過誤に遭ったらどうすればよい?
出産に関する医療過誤の被害に遭った場合、子どもが脳性まひになったケースでは「産科医療補償制度」を利用できる可能性があります。
また、医療過誤による障害・死亡などによる損害全般については、医療機関側に損害賠償を請求できます。
(1)産科医療補償制度を利用する
新生児の脳性まひの場合
「産科医療補償制度」とは、医療過誤が原因で重度の脳性まひになった子どもについて、総額3000万円の補償金が支払われる制度です。
以下の要件を満たす子どもの保護者は、原則として子どもの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日まで、補償申請を行うことができます。
①加入分娩機関で出生したこと
②出生日に応じて、以下の要件を満たすこと
- 2022年1月1日以降に出生した場合
在胎週数28週以上であること - 2021年12月31日以前に出生した場合
以下のいずれかを満たすこと
(a)出生体重1400g以上、かつ在胎週数32週以上であること
(b)在胎週数28週以上であり、かつ特定の所見が認められること
③脳性まひの原因が、以下のいずれかの除外基準に該当しないこと
- 先天性の要因(遺伝子異常など)
- 新生児期の要因(分娩後の感染症など)
- 妊娠・分娩中における妊産婦の故意または重大な過失
- 地震・噴火・津波等の天災または戦争・暴動などの非常事態
④身体障害者障害程度等級の1級または2級に相当する脳性まひであると認定されること
産科医療補償制度を利用する際の具体的な手続きについては、以下のページをご参照ください。
(参考:「産科医療補償制度の補償申請について」(公益財団法人日本医療機能評価機構))
(2)医療機関側に損害賠償を請求する
産科医療過誤により、母体や胎児に障害や死亡の結果が発生した場合、本人や遺族は医療機関側に対して損害賠償を請求できます。
治療費や慰謝料などを合わせると、非常に高額の損害賠償が認められる可能性がありますので、弁護士のアドバイスを求めることをおすすめいたします。
3. 医療機関に対する損害賠償請求の手続き
医療過誤の損害賠償請求は、原因の調査・証拠保全など十分な準備を整えたうえで行うことが大切です。
(1)医療過誤原因の調査・証拠保全
医療過誤に関する損害賠償請求のポイントは、障害や死亡などの結果が、医療機関側の過失によって引き起こされたと証明することです。
そのためには、医療過誤の原因を調査したうえで、医療機関側の過失を基礎づける証拠を集める必要があります。
たとえば以下の証拠は、医療過誤の原因や医療機関側の過失を立証するために役立つ可能性があります。
- カルテ
- レセプト(診療報酬明細書)
- 専門家の意見書
- 関係者の証言
など
ただし、医療機関側が証拠開示を拒否したり、悪質なケースでは証拠を改ざんしたりすることもあるので注意が必要です。
医療過誤の重要な証拠を確保するためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめいたします。
(2)医療機関側との和解交渉・ADR・訴訟など
原因調査・証拠保全などの準備が整ったら、実際に医療機関に対して損害賠償を請求しましょう。
医療過誤の損害賠償請求は、まず医療機関側との和解交渉から始めます。和解の合意が成立すれば、早期に損害賠償を獲得できます。
ただし、医療機関側の態度が強硬な場合には、和解交渉が決裂してしまうことも想定されます。
その場合は、日本弁護士連合会の医療ADRや裁判所の訴訟手続きを通じて、損害賠償を求めましょう。
(参考:「医療ADR」(日本弁護士連合会))
医療ADRや訴訟は専門性が高い手続きであるため、弁護士を代理人として対応するのが安心です。
- こちらに掲載されている情報は、2022年12月23日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

医療に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年12月26日
- 医療
-
- 2023年11月29日
- 医療
-
- 2023年11月01日
- 医療