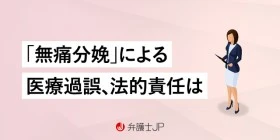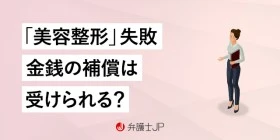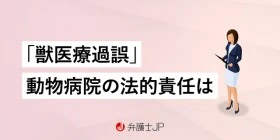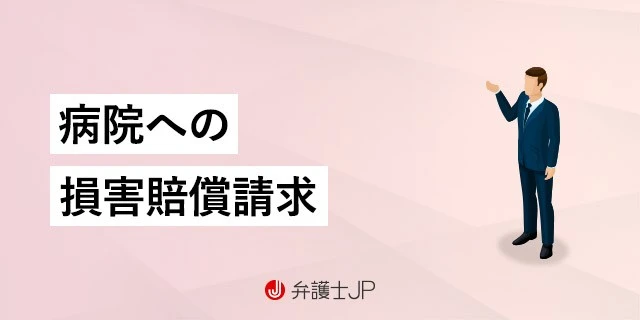
医療過誤事件で損害賠償請求できるものと手続きの流れ
医師や病院の過失によって患者の生命が奪われたり、障害が残ったりした場合には、医療過誤であるとして民事上の責任を追及していくことになります。被害を被った患者としては、肉体的・精神的に相当な苦痛を被ることになりますので、その苦しみを金銭に換算して請求していくことになりますが、具体的にどのような損害を請求することができるのでしょうか。
今回は、医療過誤事件における損害賠償の内容と流れについて見ていきましょう。
1. 医療過誤の損害賠償の内容
医療過誤によって患者の命が奪われたり、障害を負ったりした場合には医師、医療従事者、病院に対して損害賠償請求をすることができます。その場合に請求することができる損害としては、以下のものになります。
(1)治療費
治療費とは、医療過誤よって生じたケガなどの治療に要した費用のことをいいます。治療を継続してもこれ以上改善する見込みがない状態を「症状固定」といいますが、治療費は、症状固定時までに生じたものを請求していくことになります。
(2)入院雑費
医療過誤によって入院をすることになった場合には、日用品などの購入でお金を支出することになります。そのため、入院雑費として、1日あたり1500円以上を請求することができます。
(3)付き添い看護費
入院や通院にあたって付添人が必要な場合には、付き添い看護費として、付添人がプロであるか近親者であるかの別や、付添を要する程度に応じて、入院1日につき、あるいは通院1日につき一定額を請求することができます。付添人の要否については、被害者の症状の程度や年齢などを踏まえて判断されることになりますので、付き添いをしたからといって必ず認められる損害ではありません。
(4)休業損害
医療過誤が起きた場合には、就労が困難になり仕事を休まなければならないこともあります。仕事を休んだ場合には、その分収入が減少することになりますので、休業損害として減少した収入分を請求することができます。休業損害は、1日あたりの基礎収入×休業日数という計算式によって算定します。
(5)逸失利益
逸失利益とは、医療過誤によって将来得られるはずであった収入を失ったことによる損失のことをいいます。逸失利益には、医療過誤によって患者に障害が残った場合の後遺障害逸失利益と患者が死亡した場合の死亡逸失利益があります。それぞれの金額については、以下のように算定します。
①後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数
②死亡逸失利益
死亡逸失利益=基礎収入×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数×(1-生活費控除率)
(6)慰謝料
慰謝料とは、医療過誤によって被害者が被った精神的苦痛を賠償するものをいいます。慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。医療過誤の事案では、患者側にも病気やけがなどによって元々万全の健康状態ではなかったという事情がありますので、交通事故の場合と異なり慰謝料の金額は、一定程度減額されることもあります。
(7)葬儀費
医療過誤によって被害者が死亡してしまった場合には、被害者の葬儀を執り行うために要した費用として葬儀費の請求をすることができます。葬儀費用としては、原則として150万円が支払われ、事情によっては増減することになります。
2. 損害賠償請求の流れと難しさ
医療過誤事件に関して損害賠償請求を進めていく場合には、医療過誤事件特有の難しさがありますので、早期に医療過誤に詳しい弁護士に相談をすることをおすすめします。
(1)損害賠償請求の流れ
医療過誤による損害賠償請求をする場合には、以下のような流れで進んでいきます。
①医療過誤の証拠の収集
医療過誤を理由に損害賠償請求をしていくためには、患者側において、病院側に当該医療事故の発生について過失があったこと、その過失によって結果が生じたこと(因果関係)などを立証していかなければなりません。そのための証拠としては、病院側が保有している診療記録(カルテ)を入手するのが証拠収集の第一歩となります。
②証拠に基づく検討
入手した証拠をもとにして、病院側の過失や因果関係を立証することができるのかを検討します。証拠の検討にあたっては、弁護士だけでなく協力医のサポートも必要になってきます。
③病院側との話し合い
証拠を検討した結果、損害賠償請求が可能であると判断した場合には、損害賠償額を算定したうえで、病院に対して損害賠償請求を行います。いきなり訴訟提起をするのではなく、まずは病院側との話し合いの機会を持つのが一般的です。話し合いの結果、賠償額について合意が得られた場合には、和解によって終了となります。
④訴訟提起
話し合いで解決することができない場合には、裁判所に対して訴訟を提起します。訴訟では、証拠に基づいて適切に主張立証を行っていかなければなりませんので、素人では対応が難しいといえます。特に、医療過誤事件では法律上の知識だけでなく医学上の知識も要求されますので、専門家である弁護士の協力を得ることが不可欠です。
(2)医療過誤事件は早期に弁護士に相談を
医療過誤を疑ったとしても、患者側にはそれが本当に医療過誤であるのかを判断する知識はありません。証拠として診療記録(カルテ)などを入手しようとしても、病院側によって改ざんや隠匿される危険がある場合には、証拠保全の手続きも検討していかなければなりません。
医療過誤事件では、法律の知識だけでなく医学的知識も求められますので、通常の損害賠償請求に比べて、解決するにあたって非常にハードルの高い事件であるといえます。そのため、医療ミスかもしれないと疑った場合には、早期に医療過誤に詳しい弁護士に相談をするようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年03月10日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

医療に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年12月26日
- 医療
-
- 2023年11月29日
- 医療
-
- 2023年11月01日
- 医療