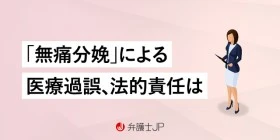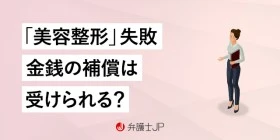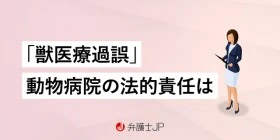帝王切開で医療事故......。医療過誤を疑うときできることとは?
出産は母親にとっても生まれてくる赤ちゃんにとっても一大事です。父親としては、無事に生まれてくることを必死で祈るばかりです。そして、帝王切開が予定されている場合は、万が一のことがあったらどうしようと不安になる方も多いでしょう。実際、過去の事例では、帝王切開によって母親が死亡したり、子どもに重い障害が残ったりしたケースもあります。万が一医療事故が疑われるような場合、家族としては病院や医師に対してどんな対応ができるのでしょうか。
1. 帝王切開の医療ミス事例
帝王切開は自然分娩(ぶんべん)と異なって手術によって出産するものです。手術に伴って、麻酔薬や子宮収縮剤などの薬品が投与されるため、妊婦や赤ちゃんにとってのリスクが高まります。過去に、帝王切開で重篤な医療事故が発生した事案には次のようなものがあります。
(1)帝王切開で生まれた長女に重度障害が残り、3歳で死亡したケース
出産した長女が脳に重度の障害を負ったのは医療ミスが原因だとして、2017年に、京都府に住む夫婦が府内の産婦人科病院を相手に、慰謝料など約1億円を求めて京都地方裁判所に提訴しました。
出産した女性は当時35歳で、2011年4月に京都府内の産婦人科医院で長女を出産しました。妊婦検診では何の異常もありませんでした。出産時には、分娩監視装置を装着せずに子宮収縮剤を投与して帝王切開手術が行われ、長女は仮死状態で生まれました。その後、脳性まひなどと診断され、3歳で死亡しました。
この事件では、2018年、裁判所で和解が成立し、医院が遺族に対して解決金を支払うことになりました。
元気に生まれてくるはずの子どもに重い障害が残り、その後わずか3歳で死亡したという、胸が痛む事件です。
(2)帝王切開で男児を出産した母親が死亡したケース
2012年に宮崎市の産婦人科医院で、帝王切開手術で男児を出産した当時35歳の女性が、出産後に容体が急変し、出産の4日後に死亡しました。遺族は、医療ミスが原因だとして、当該医院を相手に、約1億6000万円の損害賠償を求め宮崎地方裁判所に提訴しています。
女性は、帝王切開の手術から数日後に致死性の肺血栓塞栓(そくせん)症を発症しました。これは、手術後、肺血栓塞栓症を発症する前の時点において、女性の身体に兆候があったにもかかわらず、医院が必要な治療を怠り、高度な医療機関への転院措置もとらなかったために起こったものです。これについて、裁判所は、病院側の医療機関としての注意義務違反を認めて請求認容のうえ、遺族らに対して約1億3000万円の支払いを命じました。
判決文では、「高度な医療を受けられる医療機関に早期に転院していれば、女性を救命できた可能性が高かった」旨述べられており、突然に妻を亡くした夫、生まれて4日で母親を亡くした子ども、残された遺族の無念さがうかがわれます。
(3)帝王切開で出産した母親と長女の両方が植物状態になったケース
京都府内の産婦人科医院で行われた帝王切開手術での麻酔のミスで、40歳の母親と生まれてきた長女が2人とも植物状態になりました。
母親は、帝王切開のための硬膜外麻酔によって意識不明となり、首から下が動かない状態となりました。長女も出産直後から意識不明で回復困難な重い脳障害が残ったものです。
女性の夫を含む家族らは、当該医院を相手に、約3億3000万円の損害賠償を求めていました。その後、裁判所で和解が成立し、医院側が家族に謝罪し解決金を支払っています。
この産婦人科医院は、➀で紹介した、帝王切開手術後に子どもが重度障害を負った医療ミスを起こしたのと同じ医療機関です。この医院は、これ以外にも複数の医療過誤事件を起こし、その後、閉院しています。
これほどまでに重大な医療ミス事件をたびたび起こしながらも、何も知らない妊婦を相手に診療を続けていたという実態に、衝撃を受ける方も多いのではないでしょうか。
2. 医療事故だと思ったら患者ができること
帝王切開による出産を控えている場合、そして、実際に医療事故だと思った場合は、患者側としてどんなことができるのでしょうか。
(1)出産までの出来事をできるだけ記録しておく
帝王切開は、手術という大きな医療行為である上に、母親と赤ちゃんというふたつの命がかかっています。万が一に備えて、できるだけ出産前から記録を取るようにしましょう。たとえば、出産前には次のような点を記録することが重要です。
- 妊娠前の母親の健康状態(持病など)
- 妊娠中の母親の体調や経過
- 妊婦検診時の医師とのやりとりのメモ
- 最後の妊婦検診の詳しい説明
- 帝王切開にあたっての説明や麻酔、副作用などへの説明同意の経緯
- 帝王切開で入院してからの妊婦の様子や状態の変化
- 入院中の看護体制のメモ
- 帝王切開に入った時間と直前の妊婦の様子
- 手術直前の説明の内容
- 手術中に医師側から家族に対して説明があればその詳しい内容
次に、手術後に医療事故ではないかと疑った場合に、患者側がとっておきたい記録です。
- 何かおかしいと思った時間とそのきっかけ
- 事故が発生したときの状況、医師側の対応や詳しい発言内容
- 出産後の母親の様子、会話内容など
- 出産後の子どもの状態の推移
- 医師だけでなく、看護師や助産師など医療スタッフの態度ややりとり
記録は、出来事があった時にこまめに残すことが大事です。たとえ走り書きでもいいので、日時と場所(病室、分娩手術室前廊下など)を必ず記載して、できるだけ細かいやりとりまで記録しておくようにしましょう。
(2)医師に説明を求めること
医療ミスが疑われるときは、医師に説明を受ける必要があります。患者側だけでは、手術室で何が起きたか知ることはできないからです。
医師から説明を受けるとき、家族としては、怒りや疑念から強い口調になりがちです。
しかし、患者側から不信感をあらわにしてしまうと、病院側が裁判などを恐れてカルテを改ざんする、医療スタッフに口止めをするなどの対応に出る可能性があります。
もちろん、このような不正行為は許されませんが、いったんカルテが改ざんされると、患者側が医療ミスの立証に苦労することにもなりかねません。
初期段階では、とにかく冷静に医師側の説明を聞いて、すべてをメモに取ることを心がけましょう。また、早い段階でカルテの開示を求めて、改ざんされないようにすることも重要です。
3. まとめ
出産は、母子にとっても夫にとっても、人生の大切な出来事です。そして、医療水準の高い現代の日本でも、残念ながら帝王切開手術に伴う医療事故が発生しているのも事実です。医療事故は、医療と法律という専門性の極めて高い事件です。もしも、医療事故が疑われる場合は、早めに弁護士に相談することも検討するとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2021年06月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

医療に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年12月26日
- 医療
-
- 2023年11月29日
- 医療
-
- 2023年11月01日
- 医療