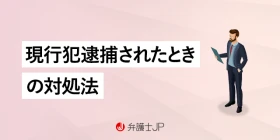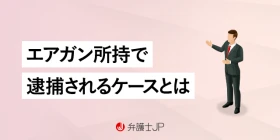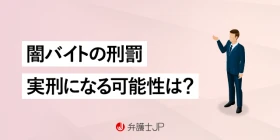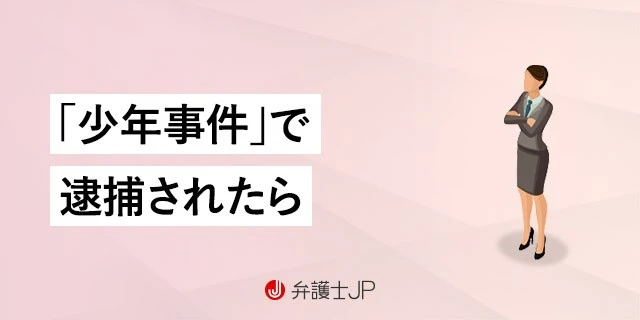
【犯罪・刑事事件】少年事件の流れと、弁護士に依頼するメリット
20歳未満の人が起こした事件を「少年事件」といい、成人と異なった扱いを受けます。
しかし、テレビニュースや新聞では少年が犯した罪についても刑事裁判が開かれて刑罰が科せられているものもあり、少年事件と成人事件をどのように区別しているのか、取り扱いにどのような違いがあるのか、わからない点が多いのも現実です。
事件を起こしてしまった少年自身や、わが子が事件を起こしてしまった親・保護者の方は、これからどうなってしまうのか、強い不安を抱えているでしょう。
少年事件の流れと、事件解決に向けて弁護士がサポートできる内容を解説します。
1. 「少年事件」とは?
少年事件とは、刑法などの刑罰法令の定めに触れる行為をした少年について、その真相を究明したり、事件の背景や少年自身の性格などから、少年の更生に向けて最適な処分を施したりする手続きです。「少年が加害者となった事件」と考えれば大筋で間違いないでしょう。
まずは少年事件の基本的な考え方を確認していきます。
(1)少年とは? 法的な区別のしかた
少年事件における「少年」とは、少年法第2条1項において「20歳に満たない者」と定義されています。
少年といえば一般的には男子を指しますが、法律上では男子・女子を区別していないので男女に関係なく「少年」です。
同じ少年法第3条1項には、少年事件の対象となる少年の種類が挙げられています。
- 犯罪少年
14歳以上で、刑法などの刑罰法令の定めに触れる行為をした少年 - 触法少年
14歳未満で、刑法などの刑罰法令の定めに触れる行為をした少年 - 虞犯(ぐはん)少年
保護者の監護に服しない、家庭に寄り付かない、犯罪性のある人との交際があるなどの事由があり、本人の性格や環境に照らして将来罪を犯すおそれのある少年
刑事処罰を受けるかの大きな基準となるのは「14歳以上か、14歳未満か」です。刑法第41条にも「14歳未満の者の行為は罰しない」と明記されているので、14歳以上であれば処罰されるおそれがあり、14歳未満なら処罰されないと区別できます。
(2)18歳・19歳は「特定少年」として扱われる
令和4年4月に施行された民法改正による成年年齢の引き下げによって、満18歳からは成人、つまり「大人」として扱われることになりました。
この改正は、少年法における「少年」の扱いを変更するべきかどうかの激しい議論を巻き起こしたので、記憶に新しい方も多いでしょう。
たしかに、民法が改正されたからといって、18歳・19歳にあたる人がこれまでは受けられていた利益をいきなり奪われることになるのは大きな問題です。
そこで、令和4年4月からは、18歳・19歳の年齢にあたる者を「特定少年」として扱うことになりました。
特定少年は、少年法における少年としての扱いを受けられるという利益が守られるものの、後述する「逆送」により大人と同様の刑事罰を科される犯罪の基準が広く設定されており、また、実名報道の規制も緩和されます。
少年でありながら「大人」として一定の責任を負うという特殊な立場だといえるでしょう。
2. 逮捕されるとどうなる? 少年事件の流れ
少年が事件を起こした場合でも、「逃げたり証拠隠滅を図ったりする恐れがある」という状況があれば逮捕される可能性があります。
では、少年が逮捕されると、その後はどうなるのでしょうか?
(1)身柄拘束を受けるのは成人と同じ
警察に逮捕されると、警察の段階で48時間以内、検察官へと引き継がれて24時間以内、合計すると72時間以内の身柄拘束を受けます。これが「逮捕」の効力による身柄拘束です。ここまでは、成人と少年の扱いに差はありません。
警察から引き継がれた少年の身柄拘束について、検察官がさらなる身柄拘束の継続が必要と判断した場合は、裁判官に「勾留」という長期の身柄拘束を請求します。
裁判官が勾留を許可すると、初回で10日間、延長請求で10日間以内、合計で最大20日間の身柄拘束を受けることになりますが、この点も成人・少年の扱いは同じです。もっとも、少年法では、少年の身柄拘束は成人よりも厳しく制限されており、少年を勾留することは、「やむを得ない場合」にしか認められません。
また、少年の場合は検察官が「勾留に代わる観護措置」を請求することがあります。これは、10日間にわたって少年を少年鑑別所に収容する措置で、勾留と違い延長がありません。
身柄拘束を受けている期間は、少年にとって強い不安を感じる時間であると同時に、学校・職場・家庭・友人といった社会への復帰を難しくしてしまうおそれがあります。
一刻も早い釈放が望ましいので、弁護士による捜査機関や裁判所へのはたらきかけが重要です。
(2)原則として全件が家庭裁判所へと送致される
警察・検察官による捜査が終わると、成人の場合は検察官が起訴・不起訴を決定しますが、少年事件では扱いが異なります。
警察や検察官は「捜査」をつかさどる機関ですが、少年の特性に配慮した調査や処分には長(た)けていません。
そこで、少年が罪を犯した疑いがあると判断した場合、処分の権限を検察官に委ねるのではなく、全件を家庭裁判所に引き継いで調査・処分を委ねることになります。
なお、家庭裁判所が「刑罰を科すのが適当だ」と判断したとしても、家庭裁判所には刑罰を科す機能がありません。このようなケースでは、事件が家庭裁判所から検察官へと戻されます。
これを「検察官から引き継がれた事件を再び検察官へ戻す」という意味で「逆送」と呼びます。16歳以上の少年が殺人など故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合や、特定少年による一定の重大な犯罪については、原則として逆送がなされ、刑事罰が科されることになります。
(3)刑事裁判ではなく「少年審判」で処分が決まる
少年事件の送致を受けた家庭裁判所では、少年について調査を尽くしたうえで「少年審判」を開くべきかどうかを判断します。
少年審判とは、成人事件における刑事裁判と同じ位置づけにある手続きですが、有罪・無罪や刑罰を決めるのではなく、少年の更生に必要な処分を決める場です。
審判の結果次第では、少年院に収容されたり、保護観察がついて不自由な生活を強いられたりします。
進学や就職などの面で不利益が生じないようにするには、少年審判を開かない「審判不開始」や、少年審判のなかで処分を課さない「不処分」を目指すのが最善でしょう。
少年にとって有利な事情を集めたうえで家庭裁判所の裁判官や調査官にはたらきかける必要があるので、弁護士のサポートは欠かせません。
- こちらに掲載されている情報は、2022年12月16日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

犯罪・刑事事件に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年07月26日
- 犯罪・刑事事件
-
- 2024年06月19日
- 犯罪・刑事事件
-
- 2024年06月08日
- 犯罪・刑事事件