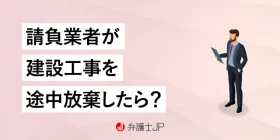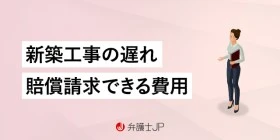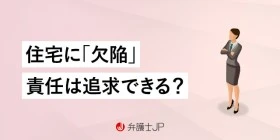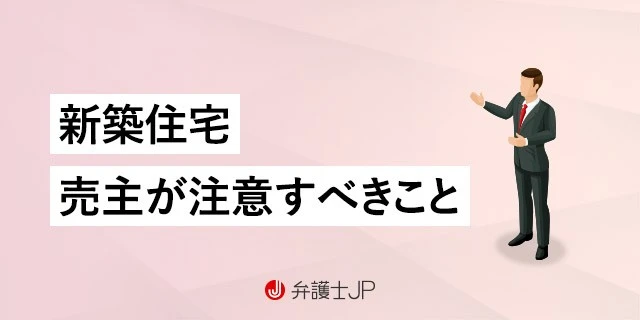
契約不適合責任とは? 売主(請負人)が認識すべき基本事項
新築住宅の施工不備などが判明した場合、買主(注文者)は売主(請負人)の「契約不適合責任」を追及できます。
新築住宅の売主(請負人)としては、契約不適合責任を追及されて甚大な損失を被らないように、契約に沿った施工・点検等に努めましょう。
今回は契約不適合責任について、発生要件・瑕疵担保責任との違い・買主(注文者)による請求の種類・売主の注意点などを解説します。
1. 契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売買や請負の目的物に契約との不適合があった場合に、売主(請負人)が買主(注文者)に対して負担する責任です。
(1)契約不適合責任の発生要件
契約不適合責任が発生するのは、売主から買主に対して引き渡した目的物が、種類・品質・数量のいずれかについて契約内容に適合していない場合です(民法第562条第1項本文)。
新築住宅の施工不良(ひび割れ・雨漏り・耐震性不足など)や、契約とは異なる建築部材の使用などは、いずれも契約不適合責任の発生原因となります。
(2)契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い
契約不適合責任は、2020年4月1日の民法改正によって新しく設けられた制度で、改正民法の施行以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものです。
「瑕疵担保責任」の名称で呼ばれていた時期は、責任の法的性質について争いがあったほか(法定責任説vs契約責任説)、責任追及の手段が損害賠償請求と契約の解除のみに限定されていました。
民法改正によって「契約不適合責任」と改められて以降は、同責任は契約責任であることが明文化されました。
さらに後述のとおり、履行の追完請求と代金減額請求が新設され、買主側の救済手段の充実も図られました。
(3)品確法上の瑕疵担保責任について
「瑕疵担保責任」の名称は、改正民法の施行後も「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく瑕疵担保責任の規定に残されています。
品確法上の瑕疵担保責任は、新築住宅の請負契約・売買契約において、住宅のうち以下の部分につき、構造耐力または雨水の浸入に影響する欠陥があった場合に発生します(同法第94条、第95条)。
- 住宅の基礎
- 基礎ぐい
- 壁
- 柱
- 小屋組
- 土台
- 斜材(筋かい、方づえ、火打材など)
- 床版
- 屋根版
- 横架材(はり、けたなど)
※住宅の自重、積載荷重・積雪・風圧・土圧・水圧、地震その他の震動や衝撃を支えるものに限ります。
品確法に基づく瑕疵担保責任の追及手段は、契約不適合責任と同様です。
ただし以下の2点において、品確法上の瑕疵担保責任の方が、通常の契約不適合責任よりも重い責任となっています。
①責任期間が引渡しから10年
通常の契約不適合責任の期間は、原則として買主が不適合を知った時から1年です(民法第566条)。
これに対して、品確法上の瑕疵担保責任の期間は、住宅の引渡しから10年とされています(品確法第94条第1項、第95条第1項)。
②特約による軽減・免除不可
通常の契約不適合責任は、原則として特約による期間の短縮や免除等が認められます(民法572条)。
これに対して、品確法に基づく瑕疵担保責任は、特約による期間の短縮や免除等が一切不可とされています(品確法第94条第2項、第95条第2項)。
2. 契約不適合責任に基づき、買主(注文者)ができる請求の種類
新築住宅について、売主(請負人)の契約不適合責任(品確法上の瑕疵担保責任を含む)が発生する場合、買主(注文者)は売主(請負人)に対して以下の請求を行うことができます。
(1)履行の追完(修補)請求(民法第562条)
不適合部分を修補して、完全な住宅を引き渡すように請求できます。
ただし、当該不適合が買主(注文者)の責めに帰すべき事由による場合には、上記請求はできません。
(2)代金減額請求(民法第563条)
不適合の程度に応じて、売買代金・請負代金の減額を請求できます。
売主が修補に応じない、修補が不可能であるなどの条件を満たすことが必要です。また、(1)と同様、当該不適合が買主(注文者)の責めに帰すべき事由による場合には、上記請求はできません。
(3)損害賠償請求(民法第564条、第415条第1項)
不適合によって買主(注文者)が被った、身体・財産等に関する損害の賠償を請求できます。
(4)契約解除(民法第564条、第541条、第542条)
売買契約・請負契約を解除し、支払い済みの代金があれば返還を請求できます。
売主が修補に応じない、修補が不可能であるなどの事情があり、かつ不適合の程度が契約・取引上の社会通念に照らして軽微でないことが解除の条件です。
3. 契約不適合責任に関する新築住宅の売主(請負人)の注意点
買主(注文者)から契約不適合責任を追及されると、新築住宅の売主は甚大な損失を被ってしまいます。
そのため、契約書の内容に沿って施工されていることを逐一チェックしながら、新築住宅の工事を進めることが大切です。
下請けの工務店などに工事を再委託する場合には、再委託先の監督にも十分に注意を払いましょう。
万が一、買主(注文者)から契約不適合責任を追及された場合には、法的な観点から責任の有無や解決の落としどころを検討する必要があります。
対応の是非によって結果が大きく左右されますので、お早めに弁護士までご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2022年11月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

不動産・建築・住まいに強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年07月16日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2023年02月20日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2023年01月12日
- 不動産・建築・住まい
不動産・建築・住まいに強い弁護士
-
寺田 弘晃 弁護士
神楽坂総合法律事務所
●東京メトロ地下鉄 飯田橋駅B3出口より 徒歩約5分
●JR飯田橋駅西口より 徒歩約6分
●都営大江戸線 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分
●東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
弊所は、1階に【 新宿神楽坂郵便局 】や【 カフェ・ベローチェ 】が所在する、オザワビルの6階です。
神楽坂のシンボル【 毘沙門天 善國寺 】がビルの目の前にございます。
▶▷▶ 事務所ホームページ↓
https://shinjuku-houritusoudan.com/現在営業中 11:00〜19:00電話番号を表示する 03-5206-3755- 休日相談可
- 夜間相談可
- 24時間予約受付
- 全国出張対応
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
▶▷▶ 土日祝日・夜間のご相談も、予めお問合せ下さい