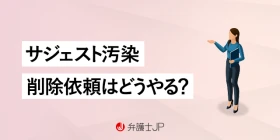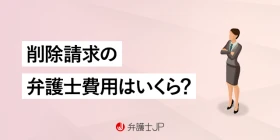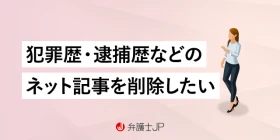誹謗中傷に対してできることはある? 泣き寝入りしないための対処法
インターネットサービスを提供している企業のグループ会社が、30~40歳代の男女544名を対象に行った調査によると、3人に1人がインターネット上のトラブルを経験していると回答しています。
ここでいうインターネットトラブルには、ネットショッピングでのトラブルや架空請求などの他に、会員制交流サイト(SNS)での誹謗中傷も該当します。
SNS上で根も葉もない誹謗中傷や心ない暴言が投稿されてしまった場合は、どのような対策が有効なのでしょうか?
泣き寝入りをしないための対処法をお伝えします。
1. 個人で対応できる誹謗中傷対策
誹謗中傷への対応は、個人でもできることがあります。
ただし、対処法を間違えてしまうと被害がさらに深刻化してしまうおそれがあるので、慎重に対応しましょう。
(1)反論・反撃は避ける
まず心得ておくべきなのが、誹謗中傷や暴言を投稿されても「反論・反撃はしない」ということです。
加害者はあなたの反応を楽しんでいます。
「きっと反論してくるだろう」「反撃してきたら次はこのネタで攻撃してやろう」と身構えているので、反論・反撃は事態を悪化させてしまいます。
腹立たしい気分になったとしても、加害者の挑発は無視したほうが賢明です。期待していたような反応がなければ、それだけで「面白くない」と攻撃が止むケースも少なくありません。
(2)必ず証拠を残しておく
誹謗中傷や暴言にあたる投稿は、必ず証拠を残しておきましょう。
SNSでの投稿を証拠に残すためには、スマートフォンやタブレットならスクリーンショット(スクショ)、パソコンなら印刷機能やプリントスクリーンを活用すると良いでしょう。
証拠を残す際のポイントは、次の4点です。
- 誹謗中傷や暴言にあたる投稿だけでなくその前後の投稿もすべて記録する
- 投稿した年月日・時間が確認できるように記録する
- 投稿のURLもあわせて記録する
- 証拠を残した年月日・時間も記録する
誹謗中傷や暴言にあたる部分だけをピックアップして記録しても、前後の投稿を見ないと権利侵害があると判断できないことが多いです。関係する投稿はすべて記録しておいたほうが良いといえます。
また、サイトによっては投稿日時が「◯日前」といったかたちでしか表示されないこともあるので、詳細表示で投稿の年月日・時間もしっかり記録しておいたほうが良いでしょう。
さらに、投稿には必ず個別の「URL」があるので、URLが表示された状態で記録するのがベストです。
最後に、忘れてはならないのが「その証拠を記録したのは、いつなのか?」という点です。
スクリーンショット・プリントスクリーンでは画像データが作成された日時が記録されますが、印刷機能を使う場合はヘッダー部分に出力した日時が印刷されるように設定しておくことをおすすめします。
(3)サイト管理者に削除を依頼する
SNSにおける誹謗中傷や暴言は、「拡散されてしまう」というリスクをはらんでいます。
たとえば、根も葉もない誹謗中傷の投稿を信じてしまった別のユーザーが、友だちやフォロワーに拡散してしまうと、収拾のつかない事態に発展してしまいます。
被害を最小限に抑えるためには、一刻も早く問題の投稿を削除する必要があります。
SNSには「通報」や「削除依頼」の機能があるので、それらを利用してサイト管理者に削除を依頼しましょう。
2. 弁護士がサポートできること
SNSで誹謗中傷や暴言を受けてしまい「どのように対応すれば良いのか?」と迷っている場合は、ぜひ弁護士に相談してください。
(1)削除に向けたサポート
SNSの運営サイドは、基本的に投稿の削除に対して消極的な姿勢をもっています。
削除依頼があった場合は、各サイトが定めたガイドラインやポリシーに従って厳格に審査するため「違反にあたらない」と判断されると、たとえ自身にとって不利益な内容だとしても削除はしてくれません。
弁護士は、サイト管理者に対する削除依頼の代行が可能です。
ガイドラインやポリシーに従い、サイト管理者が納得しやすい根拠を提示した上で削除を依頼するので、管理者が削除に応じる可能性が高まるでしょう。
また、管理者が任意の削除に応じてくれない場合は、裁判所の「仮処分」を活用した法的手段による削除も可能です。裁判所に対する手続きや証拠資料の収集などを個人で対応するのは難しいので、弁護士のサポートは必須でしょう。
(2)加害者特定に向けたサポート
誹謗中傷や暴言の投稿をした加害者に対して損害賠償を請求するには、加害者が「どこの誰なのか」を特定する必要があります。
ところが、運営サイドがユーザーの個人情報を開示してくれることは皆無と言えるでしょう。
そもそも、サイトやSNSは、氏名・住所・生年月日といった個人情報の登録を求めていないので、確かな情報を把握していないことも多いです。
そのため、加害者がどこの誰なのかを知るためには、裁判所を活用した法的手段である「発信者情報開示請求」によって特定するしか方法がありません。
弁護士へご依頼いただければ、発信者情報開示請求の一切を対応できるのはもちろんのこと、加害者へ損害賠償を求める交渉や訴訟のサポートも行えます。
弁護士は、トラブルを法的に解決する専門家です。泣き寝入りしないためにも、誹謗中傷で悩まれている場合は、ぜひご相談いただければと思います。
- こちらに掲載されている情報は、2021年07月14日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

インターネットに強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年06月11日
- インターネット
-
- 2024年05月26日
- インターネット
-
- 2024年05月13日
- インターネット