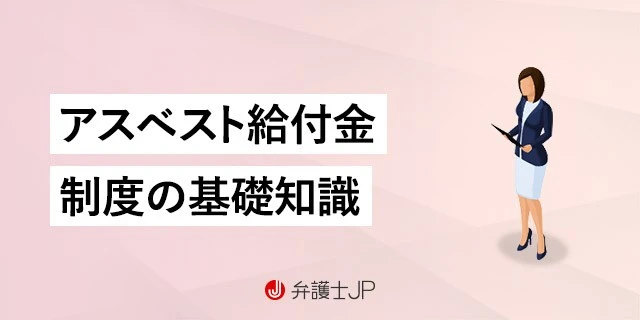
アスベスト給付金を受け取るには? 手続きの流れや対象者を紹介
令和4年1月に建設アスベスト給付金法が施行され、対象者はその症状などに応じて救済給付を受けられるようになりました。
アスベストは時間がたってから健康被害が出ることが多く、今後も石綿関連病を発症する方は出てくるでしょう。
そこで今回はこの給付金制度の概要と対象者、手続きの流れをご説明します。
1. アスベスト給付金制度とは
アスベスト被害では、長期間健康被害に苦しめられてきた方が少なくありません。アスベスト給付金制度は550万円〜1300万円の給付金を受け取れる可能性があり、被害者にとって非常に大事な補償です。
(1)建設アスベスト給付金制度とは
建設アスベスト給付金制度とは、建設現場などで働くなかでアスベスト(石綿)の健康被害を受けた方やその遺族に対して給付金を支給する国の制度です。
アスベストは繊維状の鉱物で、熱などに強く軽く使い勝手がよいため、かつては断熱材などとして建設現場で広く利用されていました。
ですが発がん性があることが発覚し、平成18年に製造・使用が全面的に禁じられました。ただ建設業界で働く多くの方がすでにアスベストを吸い込んでしまっていて、中皮腫などにより亡くなる方も相次いでいました。
そこでアスベストで健康被害を受けた方々が立ち上がり、「国は危険性を認識していたのに、規制をしてこなかった」と国を相手取って裁判を起こしました。10年以上の争いの後、最高裁は令和3年に国やメーカーの責任を認め、賠償金の支払いを命じる判決を言い渡しました。
令和3年6月に「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(建設アスベスト給付金法)」が成立、翌年1月に施行され、これに基づき給付制度がスタートしました。
2. 対象者と給付金の内容
石綿関連病は、アスベストを吸ってから数十年たってから発症する傾向があります。そのため今は建設業で働いていなくても、今後石綿関連病になる可能性があります。
ここでは給付金の対象者と金額などをご紹介しますので、心当たりのある方は、自分が当てはまるかどうか調べてください。
(1)給付金の対象者
建設アスベスト給付金で補償の対象となるのは、以下の条件を満たした方です。
- 「昭和50年10月1日〜平成16年9月30日の間に、屋内の建築作業現場で働いていた」または「昭和47年10月1日から昭和50年9月30日の間に、アスベストの吹き付け作業をしていた」
※大工や左官、溶接工、内接工、解体工、空調設備工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督などの職種が該当する可能性があります。 - 石綿関連病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、管理2〜4の石綿肺、良性石綿胸水)の患者またはその遺族
- 労働者、中小事業主、一人親方とその遺族
(2)給付金額
給付金の金額は、病態や結果によって異なります。
- 石綿肺(石綿肺管理2、じん肺法所定の合併症なし):550万円
- 石綿肺(石綿肺管理3、じん肺法所定の合併症なし):800万円
- 上記2つのいずれかで死亡した場合:1200万円
- 石綿肺(石綿肺管理2、じん肺法所定の合併症あり):700万円
- 石綿肺(石綿肺管理3、じん肺法所定の合併症あり):950万円
- 中皮腫、肺がん、著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(石綿肺管理4)、良性石綿胸水:1150万円
- 上記3つのいずれかで死亡した場合:1300万円
なお喫煙習慣の有無やばく露期間によっては、給付金が減額されることがあります。
(3)請求期限
給付金の請求には「アスベスト関連疾患にかかったことを証明する医師の診断日または石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(アスベスト関連疾患で死亡した場合は死亡日)から20年」という期限があります。
これを超えると原則として請求できなくなりますので、注意してください。
3. 請求手続きの流れ
給付金を受け取るためには、次のような流れで手続きをしてください。
- 本人または遺族が厚生労働省に必要書類を郵送
- 認定審査会が審査
- 認定者に「労働者健康安全機構」から給付金支給
請求時に必要な主な書類は以下の通りです。
- 給付金請求書
- 住民票の写し
- 遺族が請求する場合は戸籍謄本、死亡届の記載事項証明書
- 就業歴・石綿ばく露作業歴のわかる資料
- アスベスト関連疾患であることがわかる資料
- 金融口座の通帳やキャッシュカードの写し
なお別に労災認定を受けている場合、特別遺族給付金を受けた場合には、無料の「労災支給決定等情報提供サービス」が利用可能です。
申請し、認められれば、労災保険給付の際に利用された情報が活用されるため、被害者が提出しなければいけない書類の数が少なくなり、申請の負担が軽くなります。審査もスムーズに進むでしょう。
またアスベスト関連疾患の症状が重くなるなど状況が変わった場合には、追加給付も申請可能です。
「自分が給付金の対象者かわからない」「請求に必要な資料がない」「労災認定を受けていない」など、給付金請求で困りごとがある場合には、厚生労働省が設置する電話相談窓口か弁護士に相談しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年11月11日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

行政事件に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?




