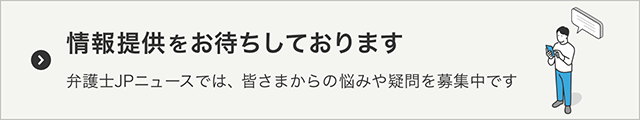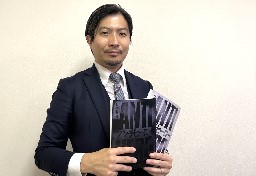「草津町長と性行為をした」元町議の証言が虚偽認定 「性加害の告発」の際に人々が持つべき“無知の知”という視点

4月17日、群馬県草津町の黒岩信忠町長が元町議の新井祥子氏に対して名誉毀損の損害賠償を求めた訴訟の判決で、前橋地裁は新井氏の証言を「虚偽」と認定した。
「セカンドレイプの町」と誹謗中傷を受ける
新井氏は2019年に「町長室で黒岩信忠町長と性行為をした」という内容の電子書籍を配信し、その後の記者会見やメディア取材などでは強制的な性被害を受けたと述べていた。新井氏の告発を受け、多数の団体や著名人が新井氏を支持して黒岩町長を批判する意見を発信したことで、注目度も高まっていったと言えるだろう。
これに対し、2020年8月頃から複数の町議が「新井祥子の解職を求める会」を組織して解職請求(リコール運動)を開始。200人を超える町民が署名集めを担う受任者として活動に参加し、必要数を大幅に上回る署名が集められた。そして同年12月に住民投票が行われ、賛成多数により新井氏へのリコールが成立した。
2021年1月には、インターネットを中心に「セカンドレイプの町」などと誹謗中傷を受けたとして、草津温泉のイメージを回復するための対策を求める請願が町議会で採択されている。一方で、同年2月には中沢康治町議を代表とする「新井祥子元草津町議を支援する会」が立ち上げられた(2023年2月に解散)。
先月30日に掲載された産経新聞のインタビューで、黒岩町長は「特にフェミニストたちの主張は私や草津町を一方的に加害者扱いするものだった」と語った。

「二次加害」の予防と「推定無罪」の原則
一般的には、「性被害を受けた」と告発した人の主張を疑うことや告発した人を非難することは「二次加害」を生じさせる危険があるとされている。
また、「被害を受けた」という告発に同情や共感を抱いて、「告発した人への応援や連帯の意思を示したい」と考える人もいるだろう。
一方で、今回の事件のように、裁判によって告発が虚偽と認定される可能性もある。
有罪が確定するまでは、告発された人であっても「罪を犯していない人」として扱うべきだとする「推定無罪」の原則は、刑事事件の手続やメディアによる報道に限らず、一般人が事件についてインターネット上などでコメントを投稿する際にも意識すべきかもしれない。
二次加害の予防や告発した人への共感・連帯と、推定無罪の原則は両立するのか。杉山大介弁護士に聞いた。
草津町に関する一連の経緯について、どう考えられますか?
杉山弁護士:今回の問題は、私は特殊なケースだと思っています。
事件が話題になり、報道やネットでのコメントなどがピークになった時点では、真偽は客観的には不明でした。
そのような状況のなか、リコールという多数決の原理で被害側を封じにいったのは、町長側が「勝ちを急ぎ過ぎた」と思っています。
リコールは「やり過ぎ」だった?
杉山弁護士:当時は、被害が真実である可能性も存在していました。
そして、被害を訴える側に味方する町議もおり、その背後には少数派の町民たちがいました。
狭い枠で多数派が少数派を力で制した時、外圧に頼るのは正当なことです。
また、暫定的な「バランス・オブ・パワー」の措置として、外部の人間が連帯を表明して肩入れすることにも正当性があったと思います。
私としては、町長側は町民の多数派から信頼を得ていたのですから、裁判によって民事的・刑事的にも対抗するまでで止めるのが正解だったと考えます。
少なくとも、リコールなどは、裁判の結果という客観的な評価を得てから行うべきだったでしょう。
この種の問題はあくまでケース・バイ・ケースで考える必要がありますが、たとえば、3月、性加害を行ったとして「準強制性交罪」などで刑事告訴されたサッカー選手の伊東純也氏が、告訴した女性を「虚偽告訴罪」で逆告訴して、2億円の賠償を求める民事訴訟を起こしました。伊東選手の対応には、特に問題はないと考えます。
「無知の知」を自覚する必要
性被害事件や性被害の告発について、一般の人々が注意すべき点や取るべき適切な態度とは、どのようなものでしょうか。
杉山弁護士:まずは、事件の経過を見守ることです。
性被害が存在するのが事実なら、いたましいことです。しかし、同時に、冤罪もまたひどいことであります。
性被害は存在するのか、それとも告発された人は冤罪なのか、その分水嶺(れい)は、非常に繊細で曖昧な事実にかかっています。
裁判では「小さな真実」のために、一年以上の年月をかけて細かく事実を確認していくことになります。
一方で、事件報道とは、一部のマスメディアが特定のソースから聞き出した、一部の情報にすぎません。
こういった限られた情報のみをもって、裁判に勝る判断をできる人はいないでしょう。人々は「無知の知」(※)を自覚すべきです。
※「自らの無知」を自覚することの困難さを説いた古代ギリシャの哲学者ソクラテスの言葉とされている。
裁判の前に「民主的な力」が必要な場合
杉山弁護士:政治的な力は、ときに法廷で事実認定を行うような正当な手続の機会を奪うこともあります。
「推定無罪の原則」は、公権力や多数派といった「強者」による、弱者への蹂躙(じゅうりん)を防ぐための原理です。
被害の訴えがあろうと、告発を受けた者は捜査機関に対し反論し、あるいは黙秘しそして強制的に事実を決められないよう対抗しても良い。
ただ、逆に自らが力を用いて訴えを事実認定以外の手段で潰したりと、力で制することを肯定するものではないです。
基本的には、厳粛な事実認定の手続である裁判などを見守ることが理想です。しかし、裁判に至る前に、政治的な力がはたらく場合もあります。また、単に検察などの公的な機関の怠慢などにより、裁判への道が開かれない場合もあります。
そのような場合には、被害者への共感や連帯といった、民主的な力で対抗する必要も出てきます。しかし、それは「真実を知るために、裁判などの正当な手続への道を開く」ことを目的にした手段であることも意識しておく必要があります。歪みを正す以上の力を加えて、歪みを生んでしまってはいけません。
上記のような主張は、必ずしも弁護士としての一般論や「法律家ならかくあるべし」というものではありませんが、事件に直に接し、報道との差異をいつも感じている者として私が抱いている考えです。
- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。
関連ニュース
-
蓮舫氏「ブラックボックスを開けたい」 都知事選向け“神宮外苑再開発”“政治とカネ”問題などへ今後の対応を語る
2024年06月14日 18:18
-
長谷川博己演じる“アンチヒーロー”が話題! ドラマ監修の弁護士が尽力するリアルとエンタメの「いい塩梅」
2024年06月08日 09:47
-
障害者に対する「合理的配慮」に“限度”は存在するのか 改正法が企業・事業者に課す「義務」を弁護士が解説
2024年06月07日 10:19