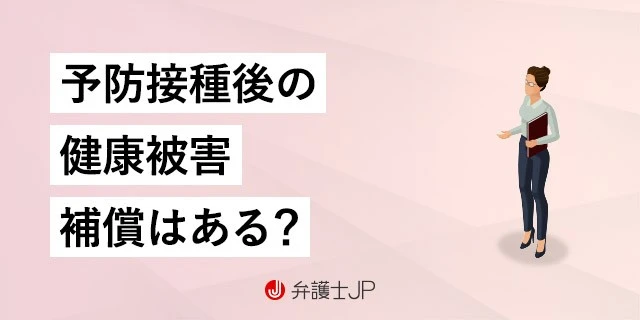
予防接種で健康被害! 給付金が受け取れる『予防接種健康被害救済制度』とは?
予防接種の副反応により健康被害が生じた場合、「予防接種健康被害救済制度」により給付金を受け取れます。
予防接種を受ける前に、万が一重篤な副反応が起こってしまった場合に備えて、救済制度に関する知識を備えておきましょう。
この記事では、予防接種健康被害救済制度の概要や、給付までの流れについて解説します。
1. 予防接種で健康被害が生じた場合、誰が責任を負う?
予防接種による健康被害については、医師・ワクチン製造業者・医療機関が法的責任を負う場合もありますが、誰にも法的責任を問えない場合もあります。
(1)医師が問診義務違反等の責任を負う場合がある
一般にワクチンは、既往症などとの関係で、投与してはいけない「禁忌者」が存在します。
医師が問診義務を怠った結果、被接種者が禁忌者に当たることを見落としてワクチンを接種し、結果的に健康被害が発生した場合、医師は問診義務違反等による不法行為責任を負います(民法第709条)。
(2)ワクチンの欠陥は製造業者や医療機関が責任を負う
ワクチン自体に腐食などの欠陥が存在し、その欠陥によって健康被害が発生した場合、製造業者やワクチン保管先の医療機関が法的責任を負います。
欠陥がどのタイミングで発生したかによって、法的責任の主体は異なります。すなわち、製造段階で欠陥が発生したのであれば製造業者が、温度管理の不備など保管段階で欠陥が発生したのであれば保管者である医療機関が、それぞれ法的責任を負います。
(3)誰にも法的責任がない場合もある
不法行為責任を追及するには、加害者に「故意または過失」があることが必要です。
この点、ワクチンの副反応による健康被害は、一定の確率で不可避的に発生するものです。もしワクチンの性質上不可避的に発生する副反応によって健康被害が発生した場合、医師・製造業者・医療機関などのいずれの主体についても、不法行為における「故意または過失」が認められません。
2. 予防接種健康被害救済制度とは?
予防接種による健康被害について、医師・ワクチン製造業者・医療機関など、どの主体にも不法行為責任が成立しない場合、被害者は誰にも損害賠償等を請求できません。
そのため、別のルートで被害者救済を図る必要があります。
また、医師・ワクチン製造業者・医療機関などに対して、予防接種に関する法的責任を追及した場合、長期にわたる裁判などが必要となり、被害者にかかる時間的・経済的負担は計り知れません。そのため、通常の民事訴訟等の枠外で、迅速な被害者救済を図ることの要請が強く存在します。
上記の問題意識を受けて、国によって「予防接種健康被害救済制度」が設けられました。
予防接種健康被害救済制度は、予防接種法に基づく予防接種(定期予防接種)の副反応によって健康を害した被害者を迅速に救済するため、医療費・医療手当・障害年金・死亡補償などを画一的に支給する制度です。
被害者は、後述する手続きに沿って給付の申請を行うことにより、裁判などによらず、迅速に健康被害に対する救済給付を受けることができます。
(参考:「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省))
なお、定期接種とは異なり、予防接種法に基づかない任意予防接種については、別途独立行政法人が運営する独自の救済制度が存在します。
(参考:「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構))
3. 予防接種健康被害救済制度による給付の流れ
予防接種健康被害救済制度に基づく給付は、以下の流れで決定・実施されます。
(1)市町村への給付請求
まず、予防接種を実施した市町村に対して、該当する給付の請求を行います。
市町村に対する請求の際には、上記の厚生労働省のページで様式をダウンロードできる請求書のほか、予防接種を受ける前後のカルテなどの必要書類を添付する必要があります。請求方法の詳細は、予防接種を受けた際に住民登録をしていた市町村にご相談ください。
(2)疾病・障害認定審査会による審査
市町村に対して提出された請求書は、厚生労働省に送付されたうえで、外部有識者で構成される「疾病・障害認定審査会」で審査されます。
審査の対象事項は、「健康被害がワクチン接種によって発生したものかどうか」という点です。言い換えれば、ワクチン接種と同時期に、別の原因によって偶然健康被害が発生したものではないかどうかが、疾病・障害認定審査会による審査対象となります。
(3)市町村による支給可否についての通知・実際の給付
疾病・障害認定委員会による審査結果を受け、厚生労働省が給付認定または否認を行います。厚生労働省は、認定または否認の判断を市町村に通知し、市町村は、その内容を被害者に通知します。
給付認定がなされた場合には、市町村から被害者に対して、該当する給付が行われます。
- こちらに掲載されている情報は、2022年04月28日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

医療に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?




