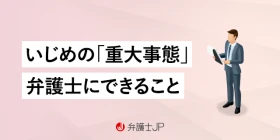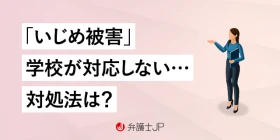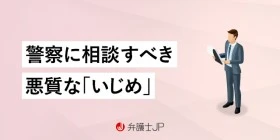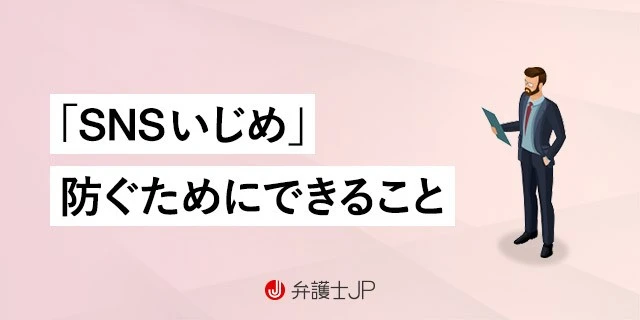
子どものSNSいじめ被害。対処法は? 保護者がとるべき行動
SNSは友達やさまざまな人たちと関わりを持てる重要なコミュニケーションツールですが、最近はこれを不適切に使った「SNSいじめ」が問題化しています。自分の子どもがSNS被害を受けていることに気づいたとき、保護者はどのように対応すればよいのでしょうか。
1. SNSいじめの事例と原因
SNSいじめとは、特定の個人に対してSNS上で行われるいじめ行為です。
(1)SNSいじめの事例
SNSいじめの具体的内容としては、以下の事例が挙げられます。
- 集団で暴言を浴びせたり、メッセージを無視したりする
- 悪口やデマ、個人情報を拡散する
- 本人になりすまして社会的評価を落とす
- クラス全員が参加しているSNSグループからその子だけ仲間外れにする
つまり、「誹謗(ひぼう)中傷する」「仲間外れにする」「無視する」など、実際の学校でも起こりがちな精神的いじめ行為がSNS上でも行われます。ただし、SNSいじめの主体は学校関係者に限られず、不特定多数の見知らぬユーザーによって行われることもあります。
SNSへのなじみが薄い親からすれば、学校におけるいじめに比べて、SNSいじめに大した実害はないように思われるかもしれません。ですが、いまや暇さえあればスマホなどでSNSをチェックしてしまう人は、大人でも珍しくありません。
つまり、SNSいじめに遭っている子どもは、自分がいじめられているつらい現実から、片時も離れられない精神的状況に追い込まれやすいことです。そのため、SNSいじめは決して軽視できる問題ではありません。
(2)SNSいじめがまん延している原因
SNSいじめが社会で広がっている原因は、さまざまに考えられます。
たとえば、SNSの匿名性や非対面性が、いじめ行為に対する罪悪感や自制心を希薄にしやすい面があります。SNSで暴言を吐いても、傷つく被害者の顔は見えません。また、「匿名での投稿ならば、責任を問われないだろう」という打算も働きやすくなります。その結果、その場の感情や雰囲気などに流されて、安直にいじめへ加わってしまいかねません。
物理的被害が出にくいSNSいじめの特性が、かえっていじめの秘匿性を強めてしまうことも問題です。「持ち物を隠された」「暴力を振るわれた」などの物理的・身体的な被害であれば、親がいじめに気がつくヒントは比較的多く見つけられます。しかし、SNSいじめでは目に見える被害が出にくく、第三者がいじめの事実に気がつくのは容易ではありません。
このように、いじめの事実が隠蔽(いんぺい)されやすいのもSNSいじめの厄介な点です。
(3)子どものSNSいじめに気がつくためのポイント
上記のとおり、SNSいじめを子どもの物理的・身体的な被害から発見するのは困難です。そのため、子どもがSNSいじめを受けているかどうか判断するための兆候は、子どもの態度や行動から読み取らなければなりません。具体的には、子どもが以下の様子を見せていたら要注意です。
- 突然スマホやPCの使用をやめる・避ける
- SNSの着信などを異常に気にする
- SNSのメッセージ画面などを親に見られないように隠す
- 登校や外出を嫌がる
- 以前より思い悩んだり、ふさぎこむ、上の空になったりしていることが増える
こうした場合、SNSいじめに限らず子どもは何か問題を抱えている可能性があります。親としては、子どもの不自然な変化に素早く気づき、相談しやすい態度で振る舞い、いつでも寄り添える関係を普段から築くことが非常に重要です。
2. SNSいじめが発覚した場合の対処法
自分の子どもがSNSいじめに遭っていた場合は、以下の対処が有効です。子どもに安心感を与えられるように、冷静な行動を心がけましょう。
(1) いじめの証拠を確保する
まずは、いじめを受けたSNSのスクリーンショットやメッセージログを保存しましょう。これらはいじめの事実を証明したり、加害者を特定して交渉したりするための重要な証拠資料です。
(2)学校や公的機関などに相談する
SNSいじめが学校内の人間関係で行われている場合、まずは担任の先生やスクールカウンセラーなどに相談しましょう。学校側が親身になってくれない場合は、警察の少年相談窓口や法務省の「子ども人権110番」などの公的機関への相談も検討する価値があります。また、SNSに投稿された誹謗中傷などの削除申請や、加害者の特定をしたい場合は、弁護士に相談することも考えられます。
(3)加害者の特定および交渉
学校側の指導で改善が期待できない場合や、直接相手に苦情や要望を告げたい場合は、加害者本人およびその保護者と交渉する必要があります。被害の程度やいじめの悪質さ次第では、治療費や慰謝料などの損害賠償請求も視野に入れましょう。相手方の保護者は、自分の子どもがいじめ加害者であると認めたがらない可能性が高いので、いじめの証拠資料を準備しておくことも重要です。
(4)訴訟を起こす
いじめ被害の大きさや、加害者家族の対応によっては訴訟を起こすことも検討する必要があります。訴訟手続きや、裁判での弁論や証拠資料集めなどを効果的に行うには、弁護士によるサポートが非常に重要です。
3. SNSいじめを防ぐためにできること
SNSいじめは容易に加担してしまう特性があるので、自分の子どもがいじめ加害者になる可能性もゼロではありません。また、SNS上での不適切な投稿がSNSいじめとなる可能性もあります。SNSいじめの被害者にも加害者にもならないためには、以下の対策が重要です。
(1)ネットリテラシーの教育
炎上しやすい投稿例や、SNS投稿がきっかけで起こったトラブル例などを挙げながら、SNSのリスクについて教育します。ネット上での個人情報の扱いについてもしっかり教えましょう。また、現実世界でもSNSでも、他人を傷つける言動をとらない、自分の発言には責任を持つなど、日頃から道徳教育を行うことが重要です。
(2)ネットやSNS利用状況の把握
使用しているSNSの種類や、日頃からどれだけネットやSNSを利用しているのかを、普段から気にかけておくことも重要です。子どもが普段からどのようにネットやSNSを利用しているのか把握しておけば、何か異常が見られたときに気づきやすくなります。
(3)ネットやSNSの利用制限
子どもが過度にSNSにのめりこんだり、有害なサイトやアプリを利用したりしないように一定の利用制限を設けることも考えましょう。具体的には、「ペアレンタルコントロール」や「フィルタリング」などの機能を使ったり、親子間でルールを決めたりします。
たとえば、不適切な投稿が行われやすい深夜帯にネットやSNSの利用を禁じれば、SNSいじめに巻き込まれるリスクを減らせます。また、こうした制限はネット・SNS依存や寝不足などの予防にも効果的です。
子どもが適切にSNSを利用できるようにするためには、保護者のサポートと指導が重要です。そして、何よりも子どもと普段から良好な信頼関係を築くことが、SNSいじめの発見や防止にとって非常に大切な要素であると考えられます。
- こちらに掲載されている情報は、2024年01月04日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

学校問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年04月03日
- 学校問題
-
- 2024年03月13日
- 学校問題
-
- 2023年09月22日
- 学校問題