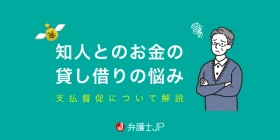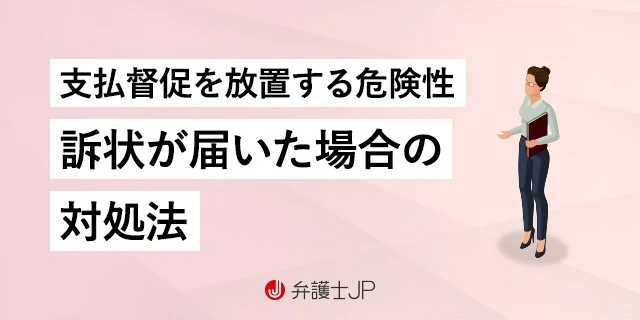
裁判所から支払督促・訴状が届いたらどうしたらいい?
借金の返済が滞っていると、ある日突然配達員から直接、裁判所から送られてきた郵便を渡されることがあるかもしれません。
郵便物が届いた場合は、すぐに封を開けて、中身をよく確認しましょう。もし支払督促の通知や訴状が入っていたら、適切な対処が必要です。
本コラムでは、特に借金の返済に関する支払督促や訴状への対処法を解説します。ぜひ参考にしてください。
1. 支払督促・訴状が届いたら
簡易裁判所から差し出された支払督促通知や訴状は、封筒に「特別送達」と書かれた書留郵便の形で届けられます。まずは支払督促や訴状がどのような書類で、これらの書類が届いたら何を確認すべきなのかを押さえておきましょう。
(1)支払督促・訴状とは
お金を貸した後に返してもらえてなかったり、給料が未払いだったりして、お金を受け取る権利があるにもかかわらず、支払ってもらえない人(債権者)は、自分のお金を回収するために法的な手続きをとることができます。
支払督促とは、お金を受け取る権利(債権)を持つ人が申立人となって裁判所に申し立てを行うことにより、申し立てを受け付けた簡易裁判所の書記官が、お金を支払う義務のある人(債務者)に対して、支払いを催促する制度です。
申し立てが行われると、支払い義務があると指名された人に支払督促という書類が送られます。
一方、訴状とは裁判で問題を解決しようとする際に、訴訟を起こす側が言い分を書いて裁判所に提出する書類で、これを受理した裁判所は、訴訟を起こされた人に訴状を送付します。
(2)確認するべきこと
裁判所からの特別送達が届いたら、すぐに封筒の中に入っている書類を確認しましょう。訴状の場合は呼出状等、支払督促は督促異議申立書がそれぞれ入っているかと思います。
書類に書かれている相手の主張を熟読し、訴状が入っていた場合には、答弁書の提出期限と第1回口頭弁論期日を確認しなければなりません。
2. 支払督促・訴状が届いた後の流れ、対処法
支払督促や訴状への対応は、パニック状態になって自分に不利な行動をとらないよう、冷静に行うことが何よりも大事です。以下の流れに沿って、しっかりと対処しましょう。
(1)支払督促が届いた場合
支払督促を受け取り、相手の主張に対して何か反論がある場合には、同封されている督促異議申立書に必要事項を記入して、所定の手数料と郵便切手とともに2週間以内に簡易裁判所へ提出します。
ただし、特殊詐欺が疑われるような怪しい書類を受け取った場合には、裁判所の連絡先を自分で調べて、詐欺師が作成した偽物の書類ではないことを確認しましょう。
書類が本物であり、そこに身に覚えのない金銭トラブルが記されていたら、督促異議申立書の提出は必須です。なぜなら、督促異議申立書を提出しなければ、たとえ相手が詐欺師で、ありもしない契約をねつ造していたとしても、強制執行が法的に認められてしまうからです。
督促異議申立書が裁判所に受理されると、裁判を行って金銭トラブルを解決することになります。その後の流れは、次に説明する「訴状が届いた場合」と同様です。
(2)訴状が届いた場合
訴状を受け取ったら、提出期限に間に合うように答弁書を提出し、呼出状で指定された日時に裁判所へ出向いて、裁判に出席しなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、裁判に無断で欠席した場合、相手の主張する事実を認めたことになってしまうということです。
そのため、もし裁判所が遠方にあったり、スケジュール調整が不可能だったりして、指定の日時に出頭できない場合には、裁判所への相談が必要です。
相手の言い分に納得して、これからお金を支払おうと考えているのであれば、和解に向けて交渉をしていくことになります。しかし、訴えてきた相手の主張を容認できず、裁判で争う場合には、自分の反論をしっかりと用意していかなければなりません。
3. 支払督促・訴状を放置したらどうなる?
支払督促や訴状を受け取ったにもかかわらず、何の対応もせずに放置するのは大変危険です。それは以下のような多大な不利益を被るリスクを自ら高めることにつながります。
(1)差し押さえや強制執行のリスク
支払督促や訴状の中身を確認せずに放置していた場合、ある日突然、財産の差し押さえや強制執行を受ける可能性があります。督促異議申立書や答弁書を提出しなければ、「相手の言い分に対して何も反論がない」という意思表示をしたことになり、裁判が開かれても無断欠席で敗訴となるでしょう。
その後、支払督促の場合は、お金を強制的に支払わせる強制執行を予告する仮執行宣言付支払督促が届き、そこでも異議を唱えずに2週間放置すると「強制執行しても構わない」という意思表示とみなされるため、債権者は強制執行ができるようになります。
また、訴状の場合には、放置し続けると自動的に敗訴の判決が確定してしまい、債権者は預貯金や不動産などを差し押さえて、債務者にお金を支払わせることが考えられます。
(2)弁護士、司法書士へ相談することのメリット
弁護士や司法書士は、さまざまな支払督促や訴状を日々扱っている専門家です。専門家に相談することで、以下のようなメリットが挙げられます。
①返済を回避できる可能性がある
たとえば借金をした場合には、原則として5年を経過すると時効が成立し、それ以降は時効を主張することで返済を回避できます。しかし、支払督促や訴状を受け取った後に相手と接触して返済の意思を示してしまうと、時効の成立が認められません。
弁護士や司法書士に相談することで、このような事態を防ぐことができます。
②督促状が届かなくなる
また、貸金業者などからの督促に悩んでいる場合、弁護士や司法書士に対応を任せることで、督促が来なくなるのもメリットとして挙げられます。貸金業法という法律で、弁護士や司法書士が着手した場合、債務者への取り立てが禁止されているためです。
③書面を書く際に手助けをしてもらえる
弁護士や司法書士は常に依頼者の利益を考え、依頼者が有利になるように対応してくれます。
督促異議申立書や答弁書には提出期限があり、期限が切れてしまったり提出できなかったりした場合には不利な状況に立たされるので、書き方がわからないなどの悩みがあれば、迷わず専門家に依頼しましょう。
特に、相手の言い分に対して異議がある場合には、専門家に依頼してその助けを借りることをおすすめします。
4. まとめ
裁判所から支払督促や訴状が届いたら、すぐに中身を確認し、裁判所へ書類を提出したり裁判へ出席したりといった対応をしなければなりません。一定の期限もあるため、何をすればよいのかわからない場合や対応に悩む場合には、弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2023年06月22日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

裁判・法的手続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2021年04月05日
- 裁判・法的手続