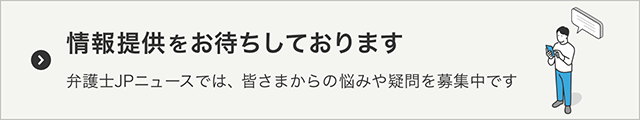WEBサービスの“利用規約”読まないリスクはある? 「一切責任を負いません」注意すべき3つの言葉
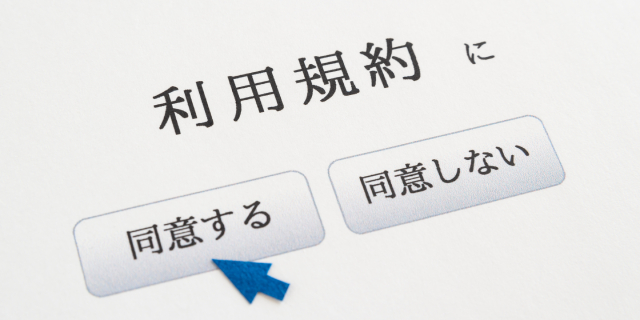
WEBサービスやスマホアプリを利用する際など、誰もが目にしたことがある「利用規約」。サービスを提供する事業者が「利用に関するルール」を一方的に示したもので、ユーザーは利用規約の内容に同意すればサービスを受けられる。他方、同意すれば利用規約は契約の一部となり、利用者を法的に拘束することになる。そんな“契約書”の一種ともいえる「利用規約」だが、長くて難しいため「読むのが面倒」と感じる人が多いのではないだろうか。
実際に、プライバシー保護を目的とするプライバシーテックに取り組む「株式会社Acompany」(愛知県名古屋市)が300人を対象に行った調査によれば、サービスを購入・利用する際に、利用規約を「毎回必ず読んでいる」人は6.3%にとどまることがわかった。残り93.7%の内訳は「サービスによっては読んでいる」72.7%、「読んでいない」21%だった。
では、利用規約を読まないことで何か不利益はあるのだろうか。
弁護士が「利用規約」を読まない理由
金融企業の法務コンプライアンス部で働いていた経歴を持つ藤澤周平弁護士に、自身がサービスを利用する際、利用規約を必ず読んでいるのか聞くと、「まったく読んでいません」と思いがけない答えが返ってきた。読まない理由について、藤澤弁護士は以下のように語った。
「よほどおかしな利用規約でない限り、サービスの良しあしには直結しないと考えているからです。正直、利用規約は、何かしらのトラブルが生じた際に問題となるものですから、危ないサービスには登録しないことが最大のリスク管理です。また、利用規約が素晴らしいからといって、提供されるサービスが優れていることにはなりませんし、中には、利用規約の内容とそのサービスが一致していない場合もあります」
なぜそのようなことが起こるのか。藤澤弁護士によれば、利用規約は一般的に企業の法務部や総務部が作成しており、外部のコンサルや弁護士に委託することも少なくないという。一方でユーザーに提供されるサービスは、社内のクリエイティブが企画・立案から設計、実装などを行う。
「つまり担当者がそれぞれ異なるため、サービスの内容が利用規約に反映されていないということが起きてしまうのです。また、最初は両者が一致していたとしても、サービスの変更時に、利用規約の変更が漏れてしまう ことも少なくありません。
とはいえ、利用規約の内容がおかしなサービスは、得てしてサービスにも問題があることが多いので、利用規約を確認することは良いことだと思います」(藤澤弁護士)
日本語に違和感=「カスタマー部門も弱い」
自身がサービスを利用する際には利用規約の内容を「読んでいない」と話す藤澤弁護士だが、これまで前職の法務コンプライアンス部の経験や、弁護士の士業として、さまざまなサービスの利用規約に目を通してきたという。弁護士として印象に残っている利用規約や、利用規約の読むべきポイント、利用規約に含まれていたら要注意の“文言”などを聞いた。
- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。
おすすめ記事