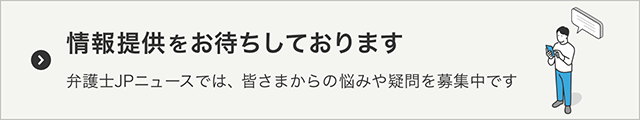“入管施設”で起こった「カメルーン人男性死亡事件」 高裁判決でも「国の過失」が認められる

5月16日、入管施設に収容中のカメルーン人男性が死亡した事件について、男性の母親が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が出された。東京高裁は国の過失を認めた水戸地裁の一審判決を支持しながら、原告と被告の双方の控訴を棄却した。
事件と判決の概要
2014年3月29日、東日本入国管理センター(茨城県牛久市)に収容されていたカメルーン人男性は夕方から夜中にかけて体調不良を訴えていたが職員に放置され、翌日の早朝に心肺停止状態で発見される。病院に救急搬送されたが、心拍の再開がなく死亡が確認された。
本訴訟は、男性が死亡したことは放置した施設側に責任があるとして、国に1000万円の損害賠償を求めたもの。
地裁判決は、死亡の約1か月前から男性が胸の痛みを訴え医師から薬を処方されていた点などをふまえ、遅くとも死亡前夜に男性が体調不良を訴えた時点で「救急搬送を要請すべき義務があった」としながら、前日に搬送されていれば男性が生存できた「相当程度の可能性」があったと判断した。
一方で、男性の死因は断定できないため、職員らが救急搬送を要請しなかったことと死亡との「因果関係」は認められない、とも判断。国に命じられた損害賠償の金額は総計165万円であった。
今回の高裁判決も、相当程度の可能性は認めるが因果関係は認めない地裁判決を支持。損害賠償の金額も変わらなかった。
「半ばほっとし、半ば残念」
判決後の記者会見で、児玉晃一弁護士は「半ばほっとし、半ば残念というのが正直なところ」と心境を述べた。
入管関連の死亡事件で国の責任を認めた判決は、本訴訟の一審判決が初めて。
名古屋地裁では、2021年3月に名古屋出入国在留管理局でスリランカ女性が死亡した事件、通称「ウィシュマさん死亡事件」の訴訟が進行している。国の控訴を棄却して水戸地裁の判決を支持した高裁判決は、同様の事件を担当している各地裁の裁判官に勇気を与えるものだ、と児玉弁護士は語った。
一方で、事件が起こってから高裁判決が出されるまで10年が経っていること、その間にウィシュマさん死亡事件が起こったことなどに触れながら、遺憾の意も示した。
「本来なら、シンプルな事件であるはずだ。施設には男性の家族も友人もおらず、助けられるのは入管の職員だけだったが、男性の声は無視された。高裁判決でも死亡の因果関係が認められなかったことは残念だ」(児玉弁護士)
「ブラックボックス」の施設で起こった事件
死亡前夜、男性は「要件あり」と記載されたボードを監視カメラの前に掲げて、職員に対応を求めた。その後、ベッドの上で体を反転させながら「アイムダイイング(私は死にかけている)」「マイハートエイク(心臓が痛い)」と声を発した。
当日は入管から委託された警備員が施設内の各部屋の状況をモニター越しに観察していた。しかし、36個の画面が順々に切り替わるモニターであったうえ、入管側が音声を切っていたために、警備員は男性の異常に気付かず。
高裁では国側の要請により警備員の証人尋問も行われた。この際、原告側は当日の男性の様子を収めた監視カメラ映像を法廷で流すことを要請。国側は反対したが、裁判所は反対を却下して、実際に映像が流された。
男性は搬送されていた時点で死亡していたために、カルテなどの医療記録は残っていない。生田庸介弁護士は「かろうじて国の過失が認定されたのは、モニターの映像があったおかげ」としながらも、今後、入管側が映像すらも記録しなくなる可能性について危惧を示した。
「入管に限らず、刑務所などの内部の状況がブラックボックスになっている施設で起こった事件で、立証責任が原告側に押し付けられることに問題がある。今回の事件のような場合、施設の管理者側に立証責任を課されるべきではないか」(生田弁護士)
- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。
関連ニュース
-
「韓国人・中国人おことわり」大久保・飲食店の“差別的”SNS投稿が物議 弁護士が指摘する明確な“違法性”とは?
2024年07月24日 09:48
-
“えん罪”「大川原化工機事件」の国賠訴訟控訴審 証人尋問の実施が決定される
2024年07月23日 18:08
-
内部通報後に誹謗中傷、パワハラ…勤務先を訴えた女性の主張、二審も認める「同様の事例でも参考に」代理人弁護士が語る“意義”
2024年07月19日 19:19
おすすめ記事