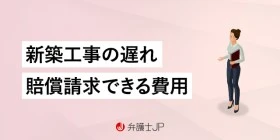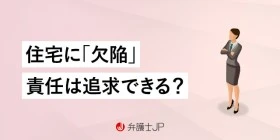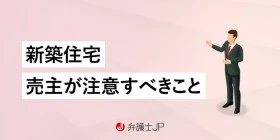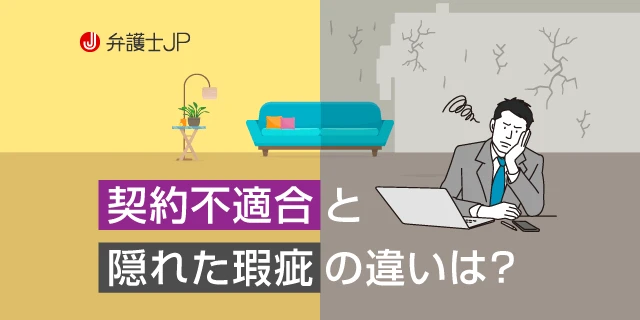
不動産売買における契約不適合責任とは何か
令和2年4月の民法改正により売買契約の「瑕疵担保責任」が、「契約不適合責任」という名称に変わりました。単なる名称変更だけでなく、責任の内容なども大幅に変更されています。これによって不動産売買に携わる会社は、大きな影響を受けることになりますので、改正のポイントを理解しておくことが重要です。
今回は、不動産売買における契約不適合責任について解説します。
1. 瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い
民法改正によって新たに契約不適合責任が導入されることになりました。従前の瑕疵担保責任とは、どのような違いがあるのでしょうか。
(1)「隠れた瑕疵」と「契約不適合」
旧民法では、「隠れた瑕疵」(瑕疵とは欠点、傷のこと。)があったときに瑕疵担保責任を追及することができるとされていました。
しかし、「瑕疵」という概念が一般的に見てわかりにくいものであることや、旧民法では外から見て明らかに瑕疵があったとしても、買主が瑕疵担保責任を追及した場合には、修理を請求することやその他の追完請求による解決ができない、とされていました。
そこで、改正民法では、「契約の内容に適合しない」場合に契約不適合責任を追及することができるようになり、修補請求やその他追完請求も認められるようになったのです。
契約に適合するかどうかは、契約において予定されていた品質、性状を有しているか、目的物が通常有すべき品質、性状を有しているかという観点から判断します。
(2)「特定物」と「種類物」
旧民法では、瑕疵担保責任は、売買の目的物が特定物である場合に限り、適用されるものとされていました。しかし、改正民法では、売買の目的物が特定物だけでなく種類物(たとえば「ビール10本」など、欲しいものの種類と数量だけ指定すること)の場合にも適用されるようになりました。
(3)買主がとり得る手段の違い
瑕疵担保責任と契約不適合責任では、買主がとり得る手段についても、以下のような違いがあります。
①追完請求
旧民法では、目的物に瑕疵があったとしても修補などによる追完請求は認められていませんでした。しかし、改正民法では、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しを求めることが認められるようになりました。
追完請求の方法について、売主と買主の主張が対立する場合には、原則として買主の主張する追完請求の方法が優先されます。しかし、売主の提案する追完方法が契約内容に適合し、かつ買主に不相当な負担を負わせるものでないときには、売主が提案する追完方法を用いることができます。
②代金減額請求
旧民法では、目的物に瑕疵があったとしても代金減額請求は認められていませんでした。しかし、改正民法では、目的物に契約不適合があった場合に代金減額請求が認められるようになったのです。
代金減額請求は、債務不履行に基づく損害賠償請求と異なり、売主の帰責事由(免責事由)の有無に関係なく、用いることができるという特徴があります。
③解除
旧民法では、解除の要件として「契約をした目的を達することができない」ことが要求されていました。しかし、改正民法では、解除についても債務不履行の一般準則に従うことになった結果、この場合に限らず、解除が認められるようになりました。
また、改正民法では、旧民法のような買主の善意(瑕疵を知らなかった)・無過失であることは、解除の要件から外されています。
④損害賠償請求
旧民法では、瑕疵担保を理由とする損害賠償請求については、売主の帰責事由は不要でした。しかし、改正民法では、契約不適合を理由とする損害賠償請求についても債務不履行の一般準則に従うことになった結果、売主が責められるべき理由が必要となっています。
また、改正民法では、旧民法のような買主の善意(瑕疵を知らなかった)・無過失は、損害賠償請求の要件から外されたことにも注意が必要です。
2. 契約不適合責任で認められた権利に対応するには
民法改正によって契約不適合責任が導入されたことを受け、不動産会社としては、以下のように不動産売買契約書の変更を行う必要があります。
(1)契約書の文言を「瑕疵」から「契約不適合」へ変更すること
民法改正によって「瑕疵担保責任」は名前が「契約不適合責任」に変更されています。そのため、まずは、契約書の文言を変更する必要があります。
また、契約に適合しているかは、契約の目的、経緯なども考慮して判断されます。将来の紛争防止のため、契約書には契約の目的、経緯なども記載しておくようにしましょう。
(2)買主の救済手段の追加
契約不適合責任が導入されたことによって、新たに買主には追完請求や代金減額請求という救済手段が追加されることになりました。
そのため、新たに追加された救済手段を含めた条項となるよう、契約書の見直しが必要になるでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2021年06月07日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

不動産・建築・住まいに強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年02月20日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2023年01月12日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2022年11月13日
- 不動産・建築・住まい