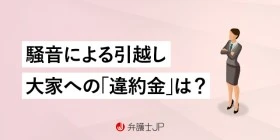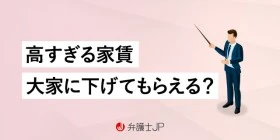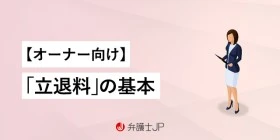入居者と敷金トラブルに!知っておきたい適切な対処法とは
敷金の返還に関してはトラブルになりやすく、国民生活センターなどに多くの相談が寄せられています。
敷金は賃貸借契約から賃借人に生じる一切の債務を担保するため賃借人から賃貸人に交付される金銭ですが、賃貸借契約終了時に生じる原状回復費用を「どこまで借主負担として敷金から差し引くか」という場面でトラブルに発展することが多いです。借主がどこまでの原状回復義務を負うかが一義的に明確ではなく、借主側と貸主側で原状回復義務の範囲についての認識が異なるためです。
2020年4月には、原状回復義務や敷金のルールなどを明確に定めた改正民法が施行されており、特に貸主側には、正確な知識を得てトラブルに対応する必要性が高まっています。
1. 敷金から差し引く原状回復費用の範囲
(1)敷金とは
敷金は、賃借人が賃貸借契約にもとづいて支払わなければならないお金(賃料や原状回復費用など)を担保するために、賃借人が賃貸人に支払うお金です。「権利金」や「保証金」などという名目でも、実質的に「敷金」といえるものであれば、「敷金」のルールに従います。
賃貸人が受け取った敷金については、契約が終了して入居者が賃貸住宅を退去したときに、賃借人に返還する義務が生じます。
返還する金額は、入居時に敷金として受け取った金額から、未払い家賃などを差し引いた金額とされます。
(2)敷金返還時には原状回復費でトラブルになりやすい
賃貸借契約が終了したときには、入居者は、物件を原状に戻して返還する必要があるとされています(原状回復義務)。
一般的に、原状回復は賃貸人が行い、その費用を敷金から差し引いて賃借人に返還する取り扱いがなされています。しかし「部屋をきれいに使っていたのに、敷金が思ったより返還されないのはおかしい」などと入居者から不満がでて、トラブルになることも少なくありません。
そのため賃貸人側は、原状回復費用として請求できる範囲について、正確に知っておく必要があります。
(3)原状回復の範囲
改正民法では、入居者は、賃貸物件が引き渡された後に生じた損傷は原状回復する必要があるものの、通常損耗や経年変化については原状回復する必要がないことを明記しています。
つまり通常の使い方で部屋を使っていれば、入居者は、原状回復義務を負わないといえます。
たとえば次のようなものは通常損耗・経年変化にあたり、原状回復の範囲に含まれないとされています。
- 家具を置いたことによって生じる床やカーペットのへこみや跡
- テレビや冷蔵庫を設置した後ろの壁面にできる黒ずみ
- 地震で割れた窓ガラス
- 鍵のつけかえ(鍵を破損・紛失していない場合)
一方、たばこのヤニやにおい、ペットのにおい、ペットがつけた柱のキズ、引っ越し作業中についたキズ、不適切な手入れや使用によって生じた設備などの損傷などは、原状回復の範囲に含まれます。
詳しくは、民法改正に先駆けて国土交通省がとりまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに、原状回復の範囲を判断していくことになります。
2. 入居者から納得がいかないと言われた場合の対応方法
敷金の返還額について、入居者から納得がいかないと言われたときには、次のような対応策で解決を図ることができます。
(1)ガイドラインをもとに話し合う
国土交通省のガイドラインには、賃借人の原状回復の負担について、事例ごとに詳しく解説がなされています。ガイドラインはあくまで一般的な基準を示すものですが、裁判例などを考慮して作成されているので、当事者が話し合って解決するための大きな柱となることでしょう。なおガイドラインは、国土交通省のホームページなどで公開されています。
(2)行政機関などに相談する
都道府県などでは、敷金トラブルを相談できる窓口を設置しているところもあります。そういった相談窓口を活用して、アドバイスを受けて解決を図ることもひとつの方法です。
(3)裁判外紛争処理制度を利用する
消費生活センターなどの紛争解決機関の相談やあっせんを利用して、解決を図る方法もあります。また裁判所の民事調停を利用して、当事者が話し合い合意を目指すこともできます。
そのほか弁護士会などが行う仲裁の制度を利用するなどの方法もあります。
(4)少額訴訟を利用する
少額訴訟は、訴える額が60万円以下の場合に利用でき、原則として1回の審理で紛争の解決を図る制度です。賃借人が少額訴訟を提起したような場合には、そのなかで解決を目指すことができます。
(5)弁護士に相談する
敷金トラブルは、弁護士に相談する方法もあります。
弁護士は、代理人として入居者との話し合いをすることができます。そして裁判所を利用した法的手段を利用するときにも、裁判所に根拠を示しながら、的確に主張をつたえることができます。
また同じような敷金トラブルが他の入居者との間で起きないように、賃貸借契約書などをチェックしアドバイスすることもできます。
- こちらに掲載されている情報は、2021年06月07日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

不動産・建築・住まいに強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年02月02日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2023年01月27日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2022年11月24日
- 不動産・建築・住まい