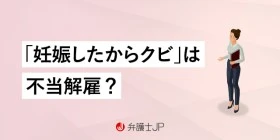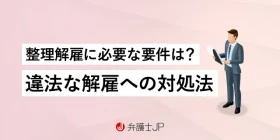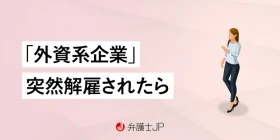- (更新:2021年07月15日)
- 労働問題
会社からの解雇予告は拒否できる? 対処法を解説
使用者からの解雇は、労働者にとって一大事です。
本コラムでは、労働者として解雇に納得できないため拒否しようとする場合の対処法についてご説明します。
1. 解雇が法的に無効であれば拒否できる
労働者の解雇について、労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しています(「解雇権濫用法理」と呼ばれます)。
つまり、同条に該当するような解雇は法律上無効であるわけですから、その解雇について労働者は当然に拒否できるのです。
問題となる解雇に、「客観的に合理的な理由」があるかどうか、「社会通念上相当」といえるかどうかについて、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇のケースに分けて見てみましょう。
(1)普通解雇
普通解雇とは、能力や勤務態度などを理由とする解雇をいいます。たとえば、労働者が以下のようなケースに該当する場合には、普通解雇が行われる可能性があります。
- 病気や負傷をした場合
- 能力不足の場合
- 勤務態度の不良、業務上の失敗がみられた場合
など
もっとも、1.の場合には、病気やケガ負傷のため、労働能力に重大な影響を及ぼすかどうか、長期にわたって回復が期待できるかどうか、他の業務への配置転換が可能かどうかなどを考慮して、「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」な解雇といえる場合にのみ、その解雇は有効なものと判断されることになります。
2.の場合には、能力などがどの程度不足しているか、向上や改善を見込めるかどうかなどを考慮して、「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」な解雇といえる場合にのみ、その解雇は有効なものと判断されることになります。
3.の場合には、使用者がどの程度の注意や指導をしたか、労働者の職歴はどのようなものか、使用者の事業規模はどの程度かなどを考慮して、「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」な解雇といえる場合にのみ、その解雇は有効なものと判断されることになります。
(2)整理解雇
整理解雇とは、使用者側の経営事情などの理由に基づき労働者を解雇することをいいます。いわゆる、「リストラ」のことです。
整理解雇が「客観的に合理的な理由」があるかどうか、「社会通念上相当」といえるかどうかについては、以下の4要素に基づいて判断されます。
①人員削減の必要性があること
人員削減の必要性があるか否かについては、使用者の経営判断を基本的に尊重し、判断される傾向にあります。
②解雇回避努力が尽くされたこと
解雇回避努力が尽くされたか否かについては、残業の削減、新規採用の中止、配転、出向、希望退職募集などの手段をとって、解雇を回避する真摯な努力を行ったか否かにより判断されます。
③人選の合理性があること
人選が合理的であるか否かについては、勤務地、勤務成績、勤続年数、扶養家族の有無及び数などを考慮した合理的な人選基準を定め、その基準が公正に適用されているか否かにより判断されます。
④手続きが妥当であること
手続きが妥当であるか否かについては、使用者が、労働者や労働組合に対して、人員削減の必要性、時期、規模、方法などを説明を行い、労働者側の納得を得られるよう努力したか否かによって判断されます。
(3)懲戒解雇
懲戒解雇とは、職務懈怠、勤怠不良、業務命令違反、職場規律違反などの企業秩序違反行為に対する懲戒処分として行われる解雇のことです。
懲戒解雇については、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」という労働契約法15条の制限を受けます(「懲戒権濫用法理」といえます)。
なお、懲戒解雇の場合にも、労働契約法16条の解雇権濫用法理が適用されるのですが、労働契約法15条の懲戒権濫用法理の判断に吸収されることになります。
以上の3つの解雇が言い渡された際には、その解雇が無効であるか否かを判断するために、使用者に対して、解雇理由証明書の交付を請求してください(労働基準法第22条)。
2. 解雇を拒否するためにすべきこと
繰り返しになりますが、法的に無効な解雇は拒否できます。しかし、解雇が言い渡されたときには、すでに使用者側が解雇の目的を達成するために入念な準備を行っている可能性があります。
そのような状況のなかで対応を間違えたことにより、労働者がさらに悪い状況となってしまったケースも少なくないようです。
そのような事態を避けるためにも、弁護士に相談しながら対応することをおすすめします。弁護士は法律の専門家であるだけではありません。法律上、依頼者の法定代理人になることが認められています。
依頼を受けた弁護士は直ちにあなたの代理人として動き、解雇の無効性を訴え、使用者と交渉してくれます。また、使用者との交渉が決裂した場合であっても、弁護士は、労働審判や裁判における手続きを代行してくれます。
まずは、労働問題の解決に実績と知見のある弁護士に相談し、サポートを受けながら対処することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2021年07月15日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年06月14日
- 労働問題
-
- 2023年04月24日
- 労働問題
-
- 2023年02月28日
- 労働問題