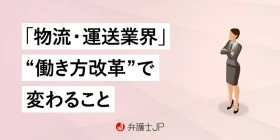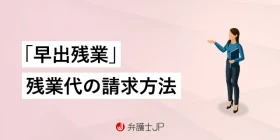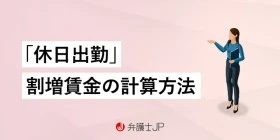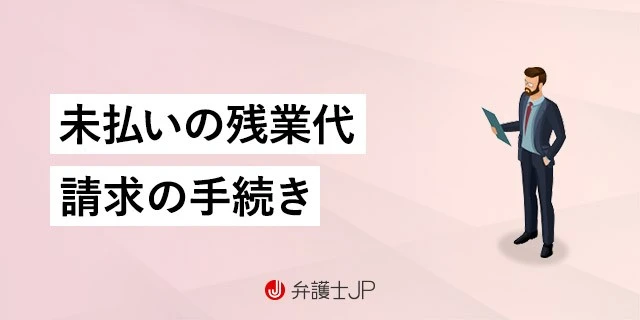
割増賃金が未払い! その請求方法は?
労働者が時間外労働・休日労働・深夜労働のいずれかを行った場合、原則として割増賃金が発生します。
もし割増賃金が未払いとなっている場合には、弁護士のサポートを受けながら会社に請求を行いましょう。
今回は、割増賃金に関する労働基準法のルールや、未払い賃金(未払い残業代)を請求する方法などを解説します。
1. 残業に対する「割増賃金」とは?
労働基準法に基づき、残業に対しては割増賃金が発生することがあります。割増賃金が発生する場合、使用者は労働者に対して、通常の賃金に割増率を乗じた賃金を支払わなければなりません。
(1)割増賃金が発生する労働の種類
割増賃金が発生するのは、以下の3種類の労働です(労働基準法第37条第1項、第4項)。
①時間外労働
法定労働時間(1日8時間・1週間40時間。労働基準法第32条)を超える労働を意味します。なお、労働契約や就業規則で定められる所定労働時間を超えたとしても、法定労働時間の範囲内であれば、原則として割増賃金は発生しません(通常の賃金による残業代は発生します)。もっとも、就業規則で割増率が定められている場合には、就業規則の定めに従うことになります。
②休日労働
週1回の法定休日(労働基準法第35条)における労働を意味します。週休2日以上の場合、労働契約または就業規則で定められた1日のみが法定休日となります。労働契約・就業規則に定めがない場合、日曜から土曜までを1週間として、もっとも遅く到来する曜日が法定休日です。
③深夜労働
午後10時から午前5時までに行われる労働を意味します。
(2)労働の種類別
割増賃金率
時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金率は、それぞれ以下のとおりです。
| 労働の種類 | 割増賃金率 |
|---|---|
| 時間外労働 |
125%(大企業の場合、1か月当たり60時間を超える部分については150%) ※中小企業であっても、令和5年4月1日以降は、1か月当たり60時間を超える部分については150% |
| 休日労働 | 135% |
| 深夜労働 | 125% |
| 時間外労働かつ深夜労働 |
150%(大企業の場合、1か月当たり60時間を超える部分については175%) ※中小企業であっても、令和5年4月1日以降は、1か月当たり60時間を超える部分については175% |
| 休日労働かつ深夜労働 | 160% |
(3)割増賃金が発生しないケース
以下のいずれかに該当する場合には、時間外労働・休日労働の割増賃金が発生しません。なお、深夜労働の割増賃金は、いずれの場合についても発生します。
①裁量労働制
専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)または企画業務型裁量労働制(同法第38条の4)の適用を受ける労働者については、時間外労働・休日労働の割増賃金が発生しません。
②管理監督者・機密事務取扱者
待遇・裁量・権限の観点から、経営者と一体的立場と評価できる管理監督者については、時間外労働・休日労働の割増賃金が発生しません(同法第41条第2号)。経営者や管理監督者と密接不可分の機密事務を取り扱う労働者(秘書など)についても同様です(同法第41条第2号後段)。
③監視・断続的労働に従事する者
守衛・学校の用務員・団地の管理人・専属運転手など、手待ち時間が長い労働者については、使用者が労働基準監督署の許可を受けることを条件として、時間外労働・休日労働の割増賃金の支払い義務が免除されます(同法第41条第3号)。
2. 未払いの割増賃金を請求する手続き
労働基準法に基づいた適正な割増賃金の支払いが行われていない場合、労働者は会社に対して、未払いの割増賃金の支払いを請求できます。
未払いの割増賃金を請求する手続きの流れは、以下のとおりです。
(1)残業の証拠を集める
会社との協議・労働審判・訴訟を有利に進めるため、残業の証拠を集める必要があります。
(例)
- タイムカードの記録
- オフィスの入出館記録
- 会社システムへのログイン履歴
- 交通系ICカードの乗降車履歴
- 業務メールの送信日時
- 業務日誌
など
(2)会社と割増賃金の精算について協議する
残業の証拠を提示して、会社に適正額による割増賃金の支払いを求めます。弁護士を代理人として協議を行うことで、会社が未払い賃金の存在を認め、早期に任意の支払いを受けられる可能性が高まります。
なお、協議の開始に当たっては、残業代請求権の時効完成を阻止するため、会社に対して内容証明郵便を送付しておきましょう。
(3)労働審判を申し立てる
労働審判は、労使間の紛争を早期に解決することを目的とした法的手続きです。原則として3回以内に審理が終了するため、迅速な解決が期待できます。
ただし、労働審判の結果について、当事者のいずれかが異議を申し立てた場合には、自動的に訴訟手続きへ移行します。
(参考:「労働審判手続」(裁判所))
(4)訴訟を提起する
裁判所の公開法廷において、未払い賃金請求権の存在を立証し、裁判所に支払いを認める旨の判決を求めます。判決によって支払いが命じられれば、最終的にその判決の内容に従って、強制執行により未払い賃金を回収できます。
協議・労働審判・訴訟のいずれの手続きによる場合でも、弁護士を代理人として対応することで、スムーズに未払い賃金の支払いを受けられる可能性が高まります。
未払い賃金・残業代請求をご検討中の方は、お早めに弁護士までご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2022年09月30日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年01月03日
- 労働問題
-
- 2023年08月17日
- 労働問題
-
- 2023年07月12日
- 労働問題