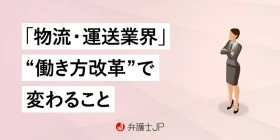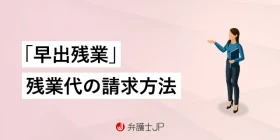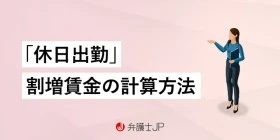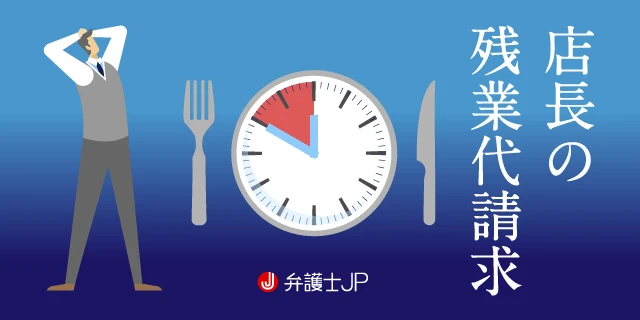
店長でも残業代が発生する判断基準とは? 未払い残業代を会社に請求する方法
飲食店や小売業などの現場では、「忙しい時期にはどうしても働かざるをえず、残業になってしまう」などといった声が聞こえてくるものです。とくに店長という立場で働く場合には、長時間働いても「店長は管理職だから残業代はでない」などと本社から言われて、残業代の支払いがなされないケースもあるのです。
しかし、店長であっても、未払いの残業代を請求すれば支払われる可能性があります。本記事では、残業代の請求が認められる場合や、請求するための方法を紹介します。
1. 飲食店や小売店の店長に多い「未払い残業代」
(1)「管理監督者」は残業代を請求できない
一般的に、労働者には、労働基準法における労働時間や休憩、休日の規定が適用されます。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超す労働をした場合は、時間外労働として割増賃金(残業代)を請求できることを規定しています。ところが、例外的に労働基準法が適用されず、残業代請求などが認められない場合があります。
たとえば労働者が、経営者と一体的にある「管理監督者」にあたる場合です。「管理監督者」と言えるかどうかは、職務と職責、勤務態様、地位にふさわしい待遇がなされているかなどの実態から判断されます。
(2)「名ばかり管理職」の可能性あり! 飲食店や小売店の店長は要注意
店長とは、一般的に、その店舗で働く社員やアルバイトの労務管理などを行ったり、まとめたりする立場にある者を指す言葉です。しかし、店長という肩書があるからといって、必ずしも「管理監督者」にあたるとは限りません。
もし会社が店長を管理職と定めていたとしても、管理監督者の実態がない「名ばかり管理職」である可能性があります。「名ばかり管理職」である場合には、労働基準法が適用されるために、残業代を請求することが可能になるのです。
(3)「名ばかり管理職」かどうかを判断するポイント
大手飲食チェーンの店長が管理監督者にあたるかが裁判で争われた「名ばかり管理職」問題は、社会的に大きな注目を集めました。そこで、厚生労働省によって、多店舗展開する小売業・飲食業の店舗の管理監督者性を否定する判断要素についての通達が出されたのです。
通達では、たとえばアルバイト・パートの採用や解雇に実質的に関与しない場合や、自身の労働時間に関する裁量が実質的にない場合、基本給や役職手当などの優遇措置が十分でない場合などには、管理監督者性が否定される可能性があるとしています。
そのほかにも様々な判断要素が示されています。そのため、実際に「名ばかり管理職」であるかを確実に判断する際には、労働基準監督署や弁護士などに相談してみることをおすすめします。
2. 未払い残業代を会社に請求する方法は?
店長であっても管理監督者でない場合には、未払い残業代を会社に請求する権利があります。具体的な請求方法は、下記の通りです。
(1)会社に直接請求する
未払いになっている残業代を会社に請求して、支払いを受けることができれば、問題は解決します。
しかし、個人で残業時間や残業代を計算し、証拠をそろえて会社に請求して主張を通すことには、多大な手間がかかります。弁護士に依頼すれば、請求を手伝わせることができます。
なお請求するときには、請求した証拠を残すためにも内容証明郵便などを利用することがポイントになります。
(2)労働審判で請求する
会社が請求に応じない場合などには、裁判所の「労働審判」を利用する方法があります。
労働審判は、裁判官や労働審判員が会社と労働者の間に入ってくれて、話し合いを重ねながら問題解決を目指す手続きです。原則として3回以内の審理でも話し合いがうまくいかなければ、審判が下されます。審判が確定すれば、判決と同様に強制執行できる効力をもつ審判書が作成されるのです。
なお審判に対して、当事者から異議申し立てがあった場合には、審判の効力はなくなります。
(3)訴訟で請求する
審判に異議申し立てがあった場合や、事情が複雑で労働審判には向かない事案などの場合には、訴訟を提起する方法があります。
訴訟では、当事者双方が主張・立証を重ねて争点を明らかにしていきます。そして最終的には、裁判官が言い渡す判決によって、残業代請求の可否や金額などについて決まることになります。判決が確定すれば判決書が作成され、残業代の不払いなどがあれば会社の財産に強制執行できるようになります。
訴訟は長期に及ぶことも多く、法的な専門知識が必要不可欠になります。そのため、通常の場合、訴訟を提起する際には弁護士に依頼することになります。
今回ご紹介したいずれの方法についても、個人で請求するよりも弁護士などに相談しながら進めた方が、問題を解決できる可能性は高くなるでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2021年10月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年01月03日
- 労働問題
-
- 2023年08月17日
- 労働問題
-
- 2023年07月12日
- 労働問題