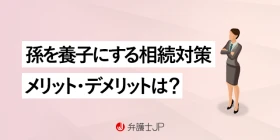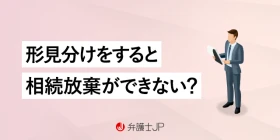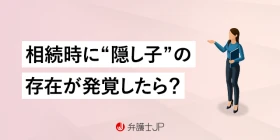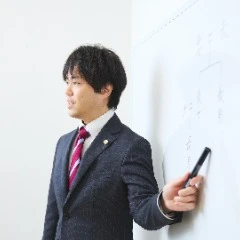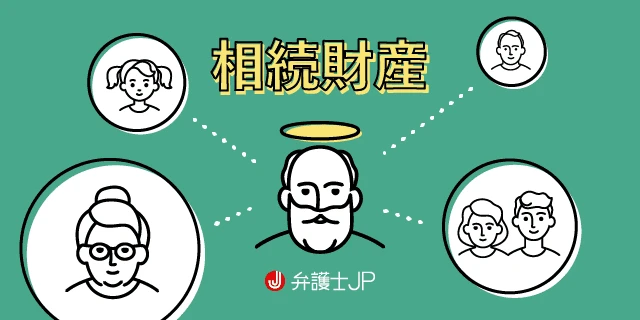
- (更新:2023年02月03日)
- 遺産相続
相続における法定相続分とは? 遺留分との違いも分かりやすく解説
相続が開始したときに誰がどのような割合で遺産を取得することができるかについては、民法で規定されています。
民法で定められた相続人のことを「法定相続人」、民法に定められた相続割合を「法定相続分」といいます。
被相続人が遺言書を遺すことなく亡くなった場合には、原則として法定相続人が遺産分割協議を行い法定相続分に従って遺産を分けることになります。
今回は、相続における法定相続分や遺留分との違いについて確認していきましょう。
1. 法定相続分とは?
法定相続人には、民法が定める一定の割合の法定相続分が認められています。以下では、法定相続分の基本的な事項と間違いやすい遺留分との違いについて説明します。
(1)法定相続人の範囲
法定相続人とは、相続が開始したときに遺産を相続できる相続人のことをいいます。
法定相続人の範囲および相続順位について、民法は以下のとおり規定しています。
①配偶者
被相続人に配偶者がいる場合には、その配偶者は常に相続人になります(民法890条)。
直系尊属、兄弟姉妹は、先順位の相続人がいない場合に限って相続人となることができますが、配偶者は、第1順位から第3順位までの相続人がいたとしても常に相続人になることができます。
②被相続人の子ども(第1順位)
被相続人の子どもは、第1順位の相続人です。なお、被相続人の子どもが被相続人よりも先に亡くなり、被相続人の子どもに子ども(被相続人の孫)がいる場合には、孫が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
さらに孫が亡くなり、ひ孫がいるときには、再代襲相続によってひ孫が相続人になります。
③被相続人の直系尊属(第2順位)
被相続人に子ども(第1順位の相続人)がいない場合には、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が相続人になります。
④被相続人の兄弟姉妹(第3順位)
被相続人に第1、第2順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
(2)法定相続人の相続割合
法定相続人の相続割合については、誰が相続人になるかによって、以下のとおり異なってきます。
①相続人が配偶者のみ、子どものみ、親のみ、兄弟姉妹のみのケース
このケースでは、各自が遺産のすべてを取得することになります。同順位の相続人が複数いるときには、相続人の数で割って遺産を分けることになります。
②相続人が配偶者と子ども(第1順位)のケース
このケースでは、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の相続割合になります。子どもが複数いるときには、2分の1の相続割合を子どもの数で割った割合となります。
③相続人が配偶者と親(第2順位)のケース
このケースでは、配偶者が3分の2、親が3分の1の相続割合になります。父母がともに存命している場合には、父母の相続割合は、6分の1ずつの割合になります。
④相続人が配偶者と兄弟姉妹(第3順位)のケース
このケースでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続割合になります。兄弟姉妹が複数いるときには、4分の1の相続割合を兄弟姉妹の人数で割った割合となります。
(3)遺留分との違い
遺留分とは、民法によって最低限保障されている遺産の取得割合のことをいいます。被相続人が特定の相続人にすべての遺産を相続させる旨の遺言書を残していた場合でも、他の相続人の遺留分を奪うことはできません。
具体的な遺留分の割合としては、以下のとおりです。
- 父母などの直系尊属のみが相続人である場合
法定相続分×3分の1 - 1.以外が相続人の場合
法定相続分×2分の1
なお、兄弟姉妹については、遺留分は認められていませんので注意が必要です。
2. 法定相続分の注意点
法定相続分には、以下の注意点があります。
(1)兄弟姉妹の父母が異なる場合
被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、父母が両方同じ兄弟姉妹と一方のみが同じ兄弟姉妹がいる場合には、一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母が両方同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
たとえば、被相続人に弟と妹がいて、弟は父母が同じであるのに対して妹は母のみ同じという場合には、弟の法定相続分は3分の2、妹の法定相続分は3分の1になります。
(2)内縁の配偶者や再婚相手の連れ子
法定相続人となる資格のある「配偶者」とは、被相続人と法律婚をしている配偶者をいいます。そのため、内縁の配偶者については、相続権はありません。
また、再婚相手の連れ子については、再婚をした事実だけでは法定相続人にはなり得ませんが、被相続人と再婚相手の連れ子が養子縁組をした場合には、法定相続人となります。
- こちらに掲載されている情報は、2023年02月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年03月08日
- 遺産相続
-
- 2024年02月19日
- 遺産相続
-
- 2024年02月08日
- 遺産相続