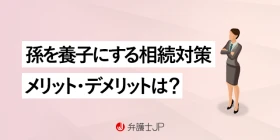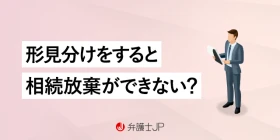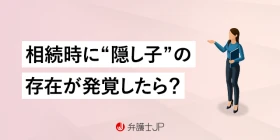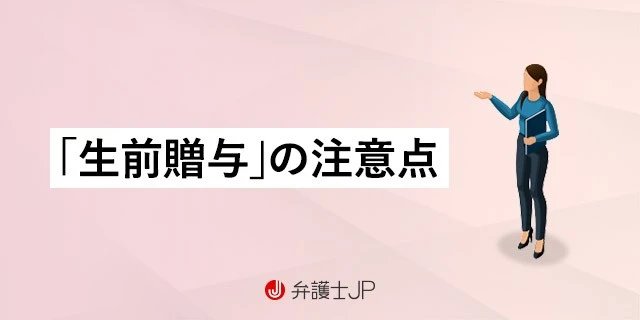
生前贈与の手続きとは? 専門家に頼むべき理由
相続対策として「生前贈与」という方法があります。生きている間に財産を渡すことで、相続発生時の相続財産を減らすことができ、相続税の負担を抑えるという効果が期待できます。ただし、生前贈与された財産に対しては贈与税の負担が生じることがありますので、贈与税も考慮した上で相続対策を考えていく必要があります。
今回は、相続対策として利用される生前贈与の手続きについて解説します。
1. 生前贈与とは
生前贈与とは、本人が生きている間に財産の一部または全部を特定の誰かに贈与することをいいます。なお、財産を贈与する側を「贈与者」、財産を受け取る側を「受贈者」といいます。相続対策として利用される生前贈与では、配偶者、子ども、孫などに対して、生前に財産の贈与が行われます。
2. 生前贈与のメリット・デメリット(注意点)
生前贈与には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
(1)生前贈与のメリット
生前贈与には、以下のようなメリットがあります。
①相続税の負担を軽減することができる
生前贈与をすることによって、将来相続が発生した場合の相続財産が減り、相続税の負担を軽減できます。
②年間110万円までは贈与税は非課税
生前贈与をした場合には、贈与額に応じて、受贈者に対して贈与税が課されることになります。しかし、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額が110万円以下であれば、贈与税が課されることはありません。なぜなら、贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を引いた残額に、税率を乗じて計算されるからです(暦年課税)。
これを利用して、長期的な視点で財産の移転をすることができれば、贈与税の負担なく、将来の相続税の負担を抑える効果が期待できます。
③贈与する相手を自由に選べる
生前贈与で財産を贈与する相手は、将来相続人になる人に限られません。相続人以外の第三者に対しても財産を贈与することができますので、お世話になった人などに対して生前に財産を渡すということもできます。
(2)生前贈与のデメリット(注意点)
生前贈与には、以下のようなデメリット(注意点)があります。
①相続税よりも贈与税の方が負担が大きい
相続税の税率と贈与税の税率を比較すると、贈与税の税率の方が高くなっています。そのため、年間110万円までの贈与税の基礎控除額を超えて贈与を行った場合、110万円を引いた残額については、相続税より高い税率の贈与税の負担をしなければなりません。
②相続開始時から3年以内の贈与には相続税がかかる
贈与をした日から3年以内に贈与者が死亡してしまった場合、死亡前つまり相続開始前3年以内に行われた生前贈与で贈与された財産については、すべて相続税の課税対象に含まれます。高齢の方が慌てて生前贈与をしたとしても、残りの余命との関係で相続税の節税効果がほとんどないということがあり得ます。
3. 生前贈与のやり方は?
生前贈与を行う場合には、以下のような方法で行います。
(1)贈与契約書を作成する
生前贈与は、贈与者と受贈者との合意によって行うことになりますので、口頭での合意だけでも有効に成立します。しかし口頭の合意だけでは、後日合意内容をめぐってトラブルになる可能性もありますので、必ず贈与契約書を作成しましょう。贈与契約書を作成しておけば、税務調査があった場合でも生前贈与の立証が容易になります。
(2)現金手渡しではなく銀行振り込みなど証拠に残る方法によって行う
生前贈与を現金の手渡しによる方法で行うと、贈与の証拠が残らず、税務署に生前贈与を否定されて、相続税が課されるリスクがあります。そのため生前贈与を行う場合には、現金手渡しではなく銀行振り込みなど証拠が残る方法で行うようにしましょう。
(3)長期的な視点で行う
贈与税が非課税となるのは年間110万円までの贈与に限られます。また、死亡前3年以内の生前贈与については、相続税の課税対象になってしまいます。そのため、相続税の節税効果を高めるには、早い段階から生前贈与に着手して、長期的な視点で継続的に行っていくことが大切です。
(4)不安がある場合には専門家に相談を
生前贈与をする際には、法律面、税金面、不動産登記面からのフォローが必要になる場合があります。より効果的な相続対策を実現するためにも、弁護士、税理士、司法書士といった専門家に相談をしながら相続対策を進めていくようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年11月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

遺産相続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年03月08日
- 遺産相続
-
- 2024年02月19日
- 遺産相続
-
- 2024年02月08日
- 遺産相続
遺産相続に強い弁護士
-
楠田 雄飛 弁護士
仙台正義法律事務所
・地下鉄
仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅より徒歩8分
・バス
仙台市営バス・高等裁判所前徒歩3分(仙台駅前バスプールよりご乗車いただく場合、本数が少ないです)
仙台市営バス・晩翠草堂前徒歩5分(仙台駅前バスプールよりご乗車いただく場合、本数が多いです)
・自動車
近隣の駐車場をご利用ください現在営業中 10:00〜18:00- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 24時間予約受付
- メール相談可
ご相談の際は、お電話かメールにて相談日の予約をお願いします。