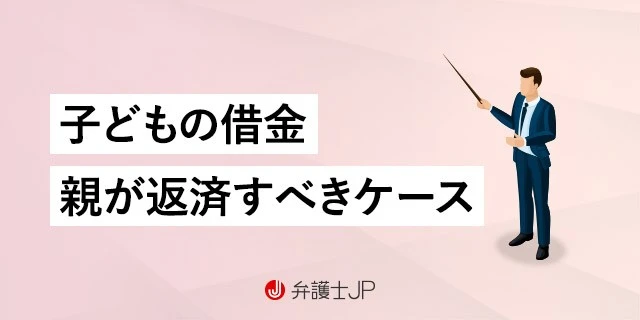
子どもの借金は親が負担しなければならない? するべき行動は?
子どもの借金を親が負担することは原則不要ですが、保証人になっている場合や借金を相続した場合には、例外的に肩代わりしなければなりません。消費者金融などからの借金返済に苦しんでいる子どもに対しては、債務整理による解決を提案しましょう。
今回は子どもの借金について、親が負担することの要否・借金問題を解決する方法などを解説します。
1. 子どもの借金は、親が負担する必要はないのが原則
子どもが借金の返済に苦しんでいるとしても、原則として親が肩代わりする必要はありません。
借金の返済義務を負うのは、あくまでも債務者本人のみであるのが原則です。債務者の親であっても、借金の契約と無関係であれば、子どもに代わって借金を返す義務を負いません。
2. 親が子どもの借金を負担しなければならないケース
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、例外的に親が子どもの借金を負担しなければなりません。
(1)子どもの借金の保証人になっている場合
親が子どもの借金の保証人になっている場合は、子どもが返済を滞納したら、親が代わりに支払う必要があります。
保証契約は書面または電磁的記録で締結しなければならず、口頭での合意は効力を生じません(民法第446条第2項、第3項)。
金銭消費貸借契約書に子どもと連名で署名捺印するか、または別途保証契約書に署名捺印する形で保証人になるケースが多いです。手元に保証契約の書面が存在するかどうかを確認しましょう。
なお、通常の保証人には以下の抗弁権・利益が認められています。
- 催告の抗弁権
主たる債務者へ先に催告すべき旨を請求する権利(民法第452条) - 検索の抗弁権
主たる債務者の財産から先に取り立てるよう請求する権利(民法第453条) - 分別の利益
保証人が複数いる場合に、自己の負担割合の限度でしか保証債務を負わない利益(民法第427条、第456条)
これに対して連帯保証人には、上記の抗弁権・利益がいずれも認められません(民法第454条)。
借金の保証人は、連帯保証人であるケースが大半です。したがって、子どもが借金の返済を滞納した場合には、債権者の請求に応じて滞納金全額を支払う必要があります。
(2)子どもの借金を相続した場合
借金を抱えた状態で子どもが亡くなった場合には、親が子どもの遺産を相続することがあります。
親が子どもの遺産を相続するのは、子どもに直系卑属(子・孫…)がいない場合です。また、子どもの直系卑属全員が相続欠格・相続廃除・相続放棄によって相続権を失った場合も、親が子どもの相続人となります。
これらの場合、親は以下の割合で子どもの遺産を相続します。
- 子どもに配偶者がいる場合
→遺産の3分の1 - 子どもに配偶者がいない場合
→すべての遺産
※親が2人とも存命中の場合は、上記の割合×2分の1をそれぞれ相続する
亡くなった子どもの借金は、相続によって法定相続割合に従い当然分割されます(最高裁昭和34年6月19日判決)。したがって、子どもの債権者から請求を受けた場合は、遺産分割の完了を待つことなく、上記の割合に従って借金を返済しなければなりません。
ただし、相続放棄をした場合には、子どもの借金を返済する義務を免れます(民法第939条)。
相続放棄は原則として、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますので(民法第915条第1項)、お早めにご対応ください。
3. 子どもの借金問題を解決するには「債務整理」
子どもが借金返済に苦しんでいる場合には、親が肩代わりする前に、債務整理を行うことを提案しましょう。
債務整理手続きには、主に以下の3種類があります。
- 任意整理
債権者と直接交渉して、利息・遅延損害金のカットや返済スケジュールの変更を認めてもらいます。 - 個人再生
裁判所に申し立てを行い、原則として債権者全員との間で、再生計画に基づく債権カットなどを行います。 - 自己破産
裁判所に申し立てを行い、債務者の財産を処分して債権者へ配当した後、残った債務全額を免責してもらいます。
適切な方法によって債務整理を行うことにより、借金問題を抜本的に解決できる可能性があります。債務整理の手続き選択や実際の対応については、弁護士に相談・依頼することができますので、お早めに弁護士までご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年05月02日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

家族・親子に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?




