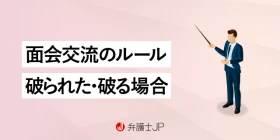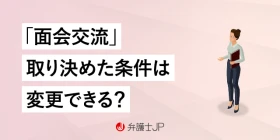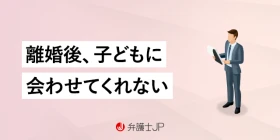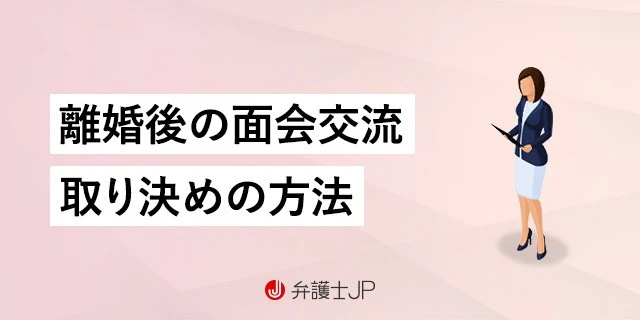
- (更新:2022年05月24日)
- 離婚・男女問題
面会交流とは何か。離婚前に決めるべきか?
子どもがいる夫婦が離婚する場合に、夫婦が対立しやすいのが、面会交流に関する取り決めです。面会交流は、離婚するにあたって対立が激しい問題のひとつです。
この記事では、面会交流の意義や、取り決めの流れなどについてご紹介いたします。
1. 面会交流とは
(1)面会交流とは
夫婦が離婚する場合に、夫婦間に未成年の子どもがいれば、父母のどちらかが親権者となり、子どもと同居し育てます。また、子どものいる夫婦が離婚協議中などで別居し、父母のどちらか一方が子どもと暮らしている場合もあるでしょう。
こういった場合に、同居していない親が子どもと直接会ったり(面会)、面会以外の方法(電話での通話、手紙や携帯電話などの電子メールのやりとりなど)で交流をすることを面会交流といいます。
(2)面会交流を求めることができる人
面会交流が問題となる場面で、親権者(あるいは監護権者)ではない親の父母(つまり、子どもからみれば祖父母)などから面会交流を求められることがあります。
しかし、家庭裁判所で行われる面会交流調停の申立人は子の父母に限定されており、祖父母は裁判所の手続きによって面会交流を求めることはできません。父母が申し立てた調停において祖父母と合わせることを取決めの中に入れたいという主張がなされることもありますが、当事者である父母が合意できない限りは認められません。
2. 面会交流に関する統計
面会交流の内容を決めるにあたって、対立が生じやすいポイントは、面会交流の頻度(回数)です。
面会交流を求める側は、少しでも多い回数でと主張されることが多いですが、子どもと一緒に暮らす親としては、子どもや自身の負担も大きくなるためあまり増やしたくないと思われる方も多いです。
では、実際に、面会交流の頻度はどのくらいが多いのでしょうか。
家庭裁判所を通じて離婚した場合の面会交流の回数等については、統計がとられています。令和2年度の結果は以下のとおりでした。
①面会交流の取決めをした総数
11288件
②取り決めた面会交流頻度
- 週1回以上:238件
- 月2回以上:935件
- 月1回以上:4818件
- 2、3か月に1回以上:561件
- 4~6か月に1回以上:179件
- 長期休暇中:38件
- 別途協議:3280件
- その他:1239件
出典:裁判所「司法統計」
上記の統計からは、月1回程度が平均的であり、半分以上のケースで「月1回以上」と定められていることがわかります。
離婚後も近くに住む場合には月1回以上の頻度での約束がなされることが多いですが、離婚をきっかけに遠方に住むようになる場合には頻度が低くなったり、都度協議するような約束になることも多くあります。
面会交流の頻度については、個別の事例に応じて話し合われることになりますが、他の夫婦がどのような取り決めをしたのかも、知っておいて損はないでしょう。
3. 面会交流を決定するまでの流れ
(1)まずは協議する
まずは裁判所を通さない話し合いで解決を目指します。
具体的には、主に次の事項を取り決めます。
- 面会交流をするかしないか
- 面会交流の方法(実際に合うか、電話やメールなどか)
- 面会交流の頻度
- 面会交流の時間
- 面会交流の場所
- 面会交流の際に費用が発生する場合の負担
- 面会交流支援機関を利用するか否か
合意ができた場合、取り決めた内容について離婚協議書など書面にしておくのがよいでしょう。口頭での約束だけだと、後に言った・言わないの争いになってしまう可能性があります。
なお、面会交流の取り決めにおいて、「養育費の支払いを面会交流の条件としたい」と考えられる方もおられますが、これは適切ではありません。なぜなら、養育費の支払い義務は子どもが成人するまでの親の義務であり、面会交流は子どもが健やかに成長するための子どもの権利であって、交換条件とできるものではありません。そのため、分けて考える必要があります。
また、親権者を決めなければ離婚できないのとは異なり、面会交流については何らの取決めをしなくても離婚することは可能です。しかしながら、取決めをせずに離婚をしたことによって、後々トラブルとなって調停などの負担が生じることもありますので、養育費や財産分与などとあわせて離婚の際に話し合い、取り決めておくことをお勧めします。
(2)調停内で取り決める
協議が調わなかった場合には、家庭裁判所での面会交流調停を通じて取り決めることになります。調停とは、裁判所の調停委員を介して相手と話し合いをし、解決方法を探る手続きのことです。面会交流調停は、おおむね次のように進んでいきます。
①実情の把握、争点の整理
調停委員が当事者の言い分を把握し、当事者や子どもの状況について事情を聞き取り、具体的な状況を把握します。
親権者(監護権者)側において、面会交流を拒否する主張をした場合には、調停委員によって、面会交流を拒否する理由の聞き取りが行われます。場合によっては、調査官が子どもの調査を行う場合もあります。
②調整や助言
調停委員が調停成立に向け調整や助言を行って、具体的な面会交流の方法について検討を促します。
③調停条項の検討
上記の検討を踏まえて、面会交流の実施が可能な場合、面会交流を行っていくうえで、必要となる具体的な取り決め(調停条項)を検討します。
合意できなければ、自動的に審判という手続きに移行します。審判の場合は、調停委員ではなく、裁判官が双方の事情を鑑みて、面会交流の内容を決定します。
なお、別居中に、協議や調停で面会交流の条件を決めた場合であっても、離婚後に改めて面会交流条件を決めなおし、条件を変更することもできます。
- こちらに掲載されている情報は、2022年05月24日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年03月11日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年02月02日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年01月17日
- 離婚・男女問題