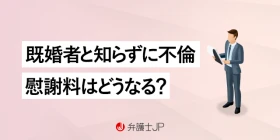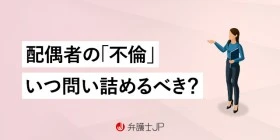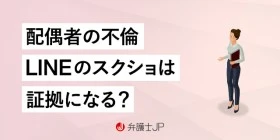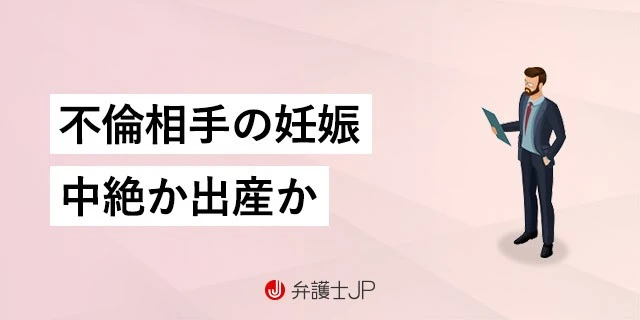
不倫関係の女性が妊娠。相手が出産を望む場合にどう対応すべきか?
不倫相手の女性が妊娠した場合、自身の配偶者・不倫相手・不倫相手の配偶者の多方面に対して、誠実な対応が求められます。
今回は、不倫相手の女性が妊娠した場合における、男性側の対処法や発生する費用につき、中絶の場合と出産の場合の両方を含めて解説します。
1. 不倫相手の妊娠が発覚した場合にすべきこと
不倫相手の妊娠が発覚した場合、短期間の間に数多くの対応を行う必要があります。
具体的に対応が必要となる主な事項は、以下のとおりです。
(1)中絶か出産かを早めに判断する
母体保護法に基づく人工妊娠中絶は、「胎児が母体外において生命を保続することができない時期」(母体保護法第2条第2項)、現在では妊娠22週未満の段階でしか認められません。
そのため、不倫相手が妊娠した子どもを中絶するのか、それとも出産するのかについては、早い段階で話し合って決めておく必要があります。
(2)出産する場合は、養育方針について話し合う
もし不倫相手が出産を希望する場合、無理やり中絶させることはできませんので、生まれてくる子どもの養育について話し合うことが必要です。
養育費の分担はどうするのか、どこで誰が子どもの世話をするのか、子どもと同居しない親がどのように子どもと面会するのか、子どもを認知するかどうかなど、さまざまな事項を決めておかなければなりません。
(3)必要に応じて配偶者に報告する
特に不倫相手が子どもを出産することになった場合、養育費の支払い義務などが発生するため、ご自身の配偶者(妻)に対する説明も早晩必要になるでしょう。
不倫を秘密にしておきたいと考える気持ちも分かりますが、時間がたってから発覚した場合のインパクトを考えると、できる限り早めに配偶者に報告することも大事です。報告した場合には、配偶者が自身や不倫相手に対して慰謝料請求を行うことや離婚に向けた話し合いや調停、訴訟となることも考えられますので、予め想定しておきましょう。
(4)話し合いを先延ばしにしてはならない
上記のすべてに共通して言えることは、不倫相手との話し合いを先延ばしにしてはならないということです。
中絶・出産の判断が遅れれば、仮に中絶となった際の母体への負担も大きくなります。また、対応の遅れによって、ご自身の配偶者や不倫相手に不誠実な印象を与えてしまうと、ただでさえ大変なトラブルがいっそう複雑化してしまうでしょう。
不倫相手の妊娠から目を背けたいという気持ちがあったとしても、ご自身を奮い立たせて、迅速・誠実に対応することが肝心です。
2. 不倫による妊娠・出産で発生する費用
不倫相手の女性が妊娠した場合、後にさまざまな出費が発生することになります。各方面に対応を行うため、資金調達のめどをつけるように努めましょう。
具体的に発生する費用は、以下のとおりです。
(1)配偶者に対する慰謝料
ご自身の配偶者に対しては、不倫慰謝料を支払う必要があります(民法第709条)。
不倫慰謝料の相場は50万円~300万円程度で、責任割合に応じて不倫相手と分担することになります。配偶者と離婚をする場合、離婚しない場合と比べて高額になります。また、不倫相手が妊娠や出産をした場合には慰謝料の増額要素となると考えられています。そのため、特に、不倫相手の妊娠や出産という事情がある場合には、慰謝料についての交渉は弁護士にご相談・ご依頼されるのがよいでしょう。
(2)不倫相手が既婚者の場合、不倫相手の配偶者に対する慰謝料
不倫相手にも配偶者がいる場合(いわゆる「ダブル不倫」)、不倫相手の配偶者に対しても慰謝料を支払わなければなりません。
ご自身の配偶者に対する場合と同様に、慰謝料の相場は50万円~300万円程度で、責任割合に応じて不倫相手と分担します。不倫相手の配偶者から厳しく慰謝料を請求された場合には、早めに弁護士に相談しましょう。
(3)中絶または出産の費用
不倫相手が妊娠している子どもを中絶・出産する際、いずれにしてもまとまった金額が必要になります。
中絶の場合、初期妊娠(4週~11週)の段階では10万円前後ですが、中期妊娠(12週以降)は40万円前後からと高額になります。
出産の場合、正常分娩であれば40万円~50万円程度が平均的です。ただし、健康保険から出産育児一時金等が給付される場合があります。
中絶または出産の費用については、不倫相手との間で負担割合などを話し合っておきましょう。
(4)出産する場合、子どもの養育費
不倫相手が子どもを出産する場合、子どもの養育費を継続的に支払う必要があります。
養育費について家庭裁判所での調停や審判となった場合には、子どもと同居しない親が支払うべき養育費の金額は、裁判所が定める養育費算定表を基準に決められることが通常です。(参考:「養育費・婚姻費用算定表」(裁判所))
親同士の収入バランスなどによりますが、月額数万円程度になることが多いです。
養育費は、子どもが20歳前後になるまで発生しますので、継続的に資金を工面する必要があります。当然ながら、家計からお金が出ていくことになりますので、夫婦間で報告・相談を行うことは必須になるでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年04月04日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年03月18日
- 離婚・男女問題
-
- 2023年10月31日
- 離婚・男女問題
-
- 2023年08月25日
- 離婚・男女問題