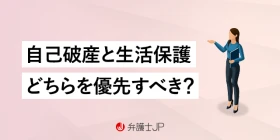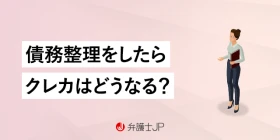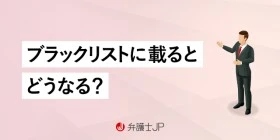個人再生できる条件は? できない場合の債務整理方法も紹介
借金を整理するためには、自宅を手離さなければならない、というわけではありません。住宅ローンを支払いつつ、その他の借金を整理する方法を個人再生と言います。自宅に住み続けたい方にとっては、とてもよい制度だと言えますが、一方で、制度を利用するには、条件もいろいろあります。
本コラムでは、個人再生ができる条件を解説しつつ、他の債務整理方法についても解説していきます。
1. 個人再生ができる条件は?
個人再生は、個人事業主や給与所得者が、自己破産によらずに経済的に再生する手段として平成13年4月に新設された制度です。
個人再生の特徴は、財産を手放す代わりに、一定額を弁済することで債務を大幅に減額してもらえる点にあります。
また、生活の拠点となる住宅に抵当権が設定されている場合でも、住宅ローンは従来どおり弁済することができ、住宅を維持することも可能です。
(1)個人再生の基本的な条件
個人再生には2種類の手続きがあり、それぞれ「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」と呼ばれていますが、手続きには大きな違いはありません。
個人再生を利用できるのは、
- 住宅ローンを除く債務総額が5000万円以下であること
- 減額後の債務を3年から5年かけて分割弁済できるだけの継続的な収入があること
が基本的な条件となります。
給与所得者等再生手続は、債権者の意向にかかわらず債務を減額してもらえるというメリットがありますが、弁済額が大きくなることが多いため、あまり利用されていません。
(2)個人再生で弁済しなければならない金額
個人再生を利用すべきかどうかは、個人再生により債務がどれだけ減額されて幾ら弁済しなければならないのか、が大きなポイントとなるでしょう。
個人再生をした場合の弁済額は、次のいずれか高い方となります。
- 債務総額により決まる最低弁済額
- 自己破産した場合に処分しなければならない財産(清算価値)に相当する額
①債務総額により決まる最低弁済額(民事再生法231条2項3号・4号)
| 債務の額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 債務額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円超5000万円以下 | 債務額の10分の1 |
たとえば、債務総額が500万円であれば100万円が最低弁済額となりますが、次で説明する自己破産時に処分しなければならない財産(清算価値)が100万円を超える場合は、清算価値相当額を弁済する必要があります。
②清算価値により決まる弁済額
個人再生では、大幅に債務が免除される一方で、高額な財産も保有が認められるということになれば、債権者との公平を欠くことになります。
そこで、自己破産した場合に処分すべき財産の額以上を弁済する必要があり、これを「清算価値保障原則」といいます。
清算価値として算定される財産は、99万円を超える現金と個別に評価して20万円を超えるものとされるのが一般的です(裁判所によって異なる)。
③退職金や過払い金が個人再生の障害となる可能性も
清算価値とされる財産には、退職金や貸金業者に対する過払い金、生命保険の解約返戻金のように、現実に資産化していない権利も含まれることから注意が必要です。
給与所得者の退職金は、
- 個人再生をする時点における、支給見込み額の8分の1
- 近々退職金の支給が予定されている場合は、支給予定額の4分の1
- すでに受給している場合は、預貯金として全額
が20万円を超えると清算価値に算入されます。
(なお、平成30年に厚生労働省が行った就労条件総合調査によれば、勤続20年以上の方が自己都合により退職した場合の平均的な退職金は約700万円から約1500万円でした。)
また、平成22年以前からいわゆる消費者金融から利息制限法を超える利率で融資を受けていた場合、払い過ぎた利息(過払い金)の返還請求権が発生している可能性があります。過払い金は、契約当初からの取引履歴を調査しなければ金額が判明しないことから、想定外に清算価値が膨らむ可能性も考えられます。
(3)個人再生の注意点
個人再生は、債権者の犠牲により債務を大幅に免除してもらう手続きであるため、一部の債権者を優遇することはできません。
勤務先や親戚などからの借金や保証人がいる債務を優先的に弁済したり、手続きから除外するためにあえて債務を隠したりすることは、個人再生手続で大きな障害となる可能性があります。
債務整理全般についていえることでもありますが、借金の返済が困難になった場合は、できるだけ早い段階で弁護士など法律の専門家に相談して適切に行動することが肝心といえます。
2. 個人再生が難しい場合の対処法
個人再生を利用したいと考えられた場合でも、
- 弁済しなければならない金額が大きくなり、個人再生のメリットがほとんどない
- 収入の減少や不安定さにより、3年から5年での分割弁済が難しい
ケースもあり、個人再生が必ずしも最善の方法ではないこともあります。
その場合は、任意整理や自己破産による解決を選択肢として検討しましょう。
それぞれの手続きの特徴を解説します。
(1)任意整理
裁判所を通さずに直接債権者と交渉をして返済条件を見直す方法です。
弁護士が任意整理を行った場合は、完済までの利息を免除してもらい、3年から5年で分割弁済する内容になるのが一般的です。
個人再生では、退職金や過払い金がネックになることがありますが、任意整理では受け取っていない退職金は考慮する必要がなく、過払い金がある場合は、過払い金を回収して債務を圧縮することも可能で逆にメリットとなります。
また、住宅ローンや自動車ローンを任意整理から除外することで、失いたくない財産を守ることも可能です。
債務の減額幅は個人再生よりも小さくなりますが、個人再生によるメリットが期待できないケースでは、任意整理も有力な選択肢になると考えられます。
(2)自己破産
個人再生では、再生計画案どおりの弁済が可能か否かも重要な要素となり、収入が少ない場合や不安定である場合は、再生計画案が認可される可能性が低くなります。
この場合は、すべての債務が免除される自己破産が選択肢となるでしょう。
不動産など高額な財産は手放すことになりますが、すべての債務が免除されることにより、経済的な再生は確実といえます。
自己破産の場合、借金の原因(浪費やギャンブルなど)によっては借金の免除が許可されないリスクもありますが、実際には裁判所の裁量により免除される可能性が高いです。
- こちらに掲載されている情報は、2021年08月19日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

借金・債務整理に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年02月28日
- 借金・債務整理
-
- 2024年01月18日
- 借金・債務整理
-
- 2024年01月15日
- 借金・債務整理