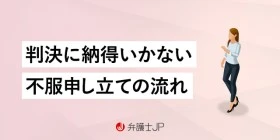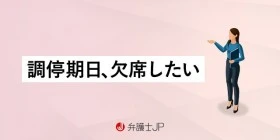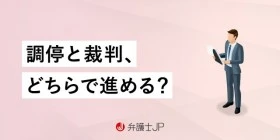交通事故を起こしてしまった! 刑事裁判・民事裁判の流れを解説
交通事故によって人に怪我をさせたり、死亡させたりしてしまった場合には、被害者から損害賠償請求をされるだけでなく、刑事裁判にかけられて処罰されるおそれがあります。
ひとくちに裁判といっても、刑事裁判と民事裁判は、その目的も手続きもまったく異なります。本記事では、交通事故の加害者になってしまった方にむけて、刑事・民事のそれぞれにおける裁判の流れについて紹介します。
1. 交通事故の刑事裁判の流れとは?
交通事故の加害者になってしまった場合の刑事裁判の流れは、下記のようになっています。
(1)交通事故の刑事裁判とは
刑事裁判とは、刑事事件を犯した加害者に対して、刑罰を科すことを目的として行われる裁判手続きです。交通事故によって他人に怪我をさせたり、死亡させたりした場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われ、刑事裁判にかけられる可能性があります。
(2)刑事裁判の流れ
交通事故の加害者が検察官から起訴された場合の一般的な刑事裁判の流れは、以下の通りです。
①冒頭手続き
原則として、刑事事件の裁判は公開の法廷で行われます。裁判が開廷されると、以下のような流れで冒頭手続きがなされます。
-
人定質問
人定質問では、起訴状に書かれた人物と出廷した人物に同一であるかどうかを確かめるために、裁判官から被告人に対して住所、氏名、生年月日、職業などについて質問されます。 -
起訴状の朗読
審理の対象となる具体的な犯罪事実が記載された起訴状を、検察官が読みあげます。 -
黙秘権の告知
被告人には、言いたくないことは言わなくてもよいという「黙秘権」があります。起訴状の朗読後には、裁判官から被告人に対して、黙秘権があることの告知がなされるのです。 -
罪状の認否の確認
検察官が朗読した犯罪事実について、裁判官から被告人に対して意見を聞かれます。質問の内容が自分の犯した交通事故で間違いないときには、「間違いありません」などと答えます。
②証拠調べ手続き
証拠調べ手続きでは、被告人の身上・経歴、犯行に至る経緯など、これから証拠によって明らかにしようとする事実について検察官から説明がなされます。これを「冒頭陳述」といいます。
その後、検察官と弁護人のそれぞれから刑事裁判において取り調べを望む証拠が請求されて、裁判官は双方の意見を聞いたうえで証拠を採用するかを決定します。
証拠は物的なものに限らず、事故に関わっていたり現場を目撃していたりした人物も「証人」として裁判に呼ばれる可能性があります。その場合には、「証人尋問」の手続きが行われます。
そして、証拠調べ手続きの最後には「被告人質問」という手続きが行われて、被告人自身が発言することができるのです。
③論告弁論手続
証拠調べが終わると、裁判官は、検察官と弁護人の双方の意見を聞きます。検察官からの意見は「論告・求刑」と呼ばれ、弁護人からの意見は「弁論」と呼ばれます。
④結審・判決
すべての審理が終わったら「結審」となり、裁判官から判決が言い渡されます。
(3)略式起訴とは
交通事故や交通違反の内容が軽微である場合には、前述のような公開の法廷での裁判手続きではなく、「略式起訴」という手続きがとられることがあります。
略式起訴とは、加害者が罪を認めている場合に、書面審理だけで迅速に事件を終結させる手続きです。裁判所による略式命令によって、100万円以下の罰金または科料が科されます。
2. 被害者から訴えられたときの民事裁判の流れとは?
交通事故の加害者は、刑事裁判を通じて刑罰を科されるのみならず、損害賠償を求める被害者から民事裁判を起こされる可能性もあります。交通事故の民事裁判の流れは、下記の通りになります。
(1)交通事故の民事裁判とは
交通事故の民事裁判とは、交通事故の被害者が交通事故で負担した治療費や慰謝料、休業損害、逸失利益などの損害に関する賠償を加害者に対して請求する手続きとなります。
なお、すべての交通事故で民事裁判が発生するとは限りません。たとえば、加害者と被害者との間で示談が行われ、交渉が成立した場合には、示談金というかたちで損害賠償を支払われることになるので、裁判にまでには至りません。また、示談と裁判の間には、「調停」や「審判」という手続きも存在します。
(2)民事裁判の流れ
交通事故の加害者が被害者から訴えられた場合の一般的な民事裁判の流れは、下記のようになっています。
①訴えの提起
民事裁判は、被害者(原告)が「訴状」を裁判所に提出することで始まります。
訴状は、裁判所から加害者(被告)へと送達されます。そして、被告側に反論がある場合には、決められた期限までに「答弁書」という書面を作成して、裁判所に提出することになるのです。
②第1回口頭弁論期日
原告と被告は、裁判所によって定められた日時に裁判所に出頭して、訴状および答弁書を陳述します。これを「第1回口頭弁論期日」といいます。被告は、あらかじめ答弁書を提出している場合には、第1回口頭弁論期日を欠席することも可能です。
また期日の最後には、次回の期日の日程を決めることになります。
③2回目以降の期日の流れ
2回目以降の期日では、原告と被告がそれぞれの立場から主張を立証していくことを通じて、争点を整理していくことになります。2回目以降の期日については、第1回目のように公開の法廷で行われる口頭弁論手続ではなく、非公開の場で行われる弁護準備手続で進行する場合もあります。
④証拠調べ
争点の整理ができた段階で、争点の判断に必要な証人を裁判所に呼んで、証人尋問の手続きが行われます。また、原告や被告の話を聞くための当事者尋問も行われます。
⑤和解期日
民事裁判では、適宜のタイミングで裁判所から和解が勧告される場合があります。原告と被告の双方が和解内容に合意した場合には、その時点で裁判は終了となります。
⑥判決言い渡し期日
和解によって裁判が終了しない場合には、これまでの双方の主張をふまえたうえで、裁判官が判決を言い渡します。
なお、もし判決内容に不服がある場合には、判決送達から2週間以内であれば「控訴」によって不服申し立てをすることができます。
- こちらに掲載されている情報は、2021年10月22日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

裁判・法的手続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2023年03月10日
- 裁判・法的手続
-
- 2022年03月25日
- 裁判・法的手続
-
- 2022年03月11日
- 裁判・法的手続