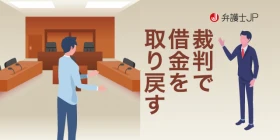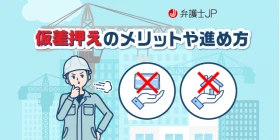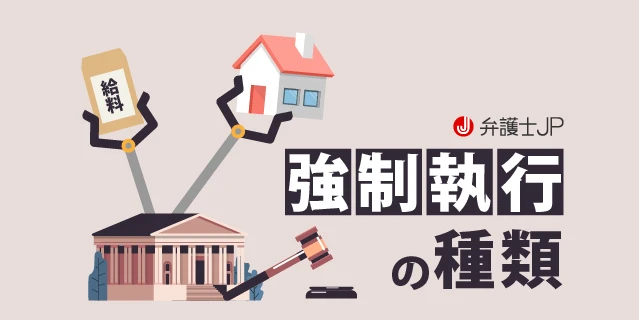
- (更新:2023年05月26日)
- 裁判・法的手続
「強制執行」とは? 債務者から確実に支払いを受ける方法について解説
「貸したお金が返ってこない」「養育費の取り決めをしたのに支払われない」
相手に支払いを求める権利(債権)があるにもかかわらず実現されていないときには、裁判所の「強制執行」の手続きを利用して、債権の回収をはかることができます。
しかし「強制執行」といわれても、「身近に感じられずピンと来ない」という方も多いでしょう。そこで、イメージをもつためにも「強制執行」の概要と大まかな流れについてみていきます。
1. 強制執行とは
(1)強制執行とは
強制執行とは、国(裁判所)の助力を得て、権利を強制的に実現するための手続きです。
たとえば、お金を貸しても返済されないため、債権者が債務者に対して裁判を起こし、勝訴判決を得たとします。しかし、判決に従う債務者ばかりとは限りません。判決を無視して返済しないことも考えられます。そうなれば裁判所の判決が意味のないものになってしまいます。
そこで判決書など公的に一定の権利を証明できる書面(「債務名義」といいます)があるときには、強制執行を申し立てることができるのです。
(2)強制執行の種類
強制執行の種類は、金銭の支払いを目的とする「金銭執行」と金銭の支払いを目的としない「非金銭執行」に分けられます。「金銭執行」のうち、担保権が設定されていない強制執行では、どの財産を対象にするかによって主に次の3種類に分けることができます。
①不動産執行手続
債務者が所有する家や土地などの不動産を差し押さえて強制競売し、その売却代金を債権回収にあてる手続きです。また、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行については、登記されている地上権(建物等の工作物、竹木を所有するため他人の土地を使用する権利)も対象にすることが可能です。
抵当権者などは、担保にしている不動産から収益(賃料など)が見込める場合には、売却せずにその収益を債権回収にあてる「強制管理」という手続きを選択することもできます。
②債権執行手続
強制執行のうち、債務者が第三者に対して有する債務者の預貯金や給料などを差し押さえ、銀行や雇い主などから取り立てて債権回収にあてるものです。事業主や企業の場合、売掛金債務や貸与金債権が対象になるケースが多いです。
③動産執行手続
債務者が所有している家財道具や商品、貴金属、66万円以上の現金、小切手、株券などの動産を差し押さえて強制競売し、その売却代金を債権回収にあてるものです。ただし、動産執行には差し押えを禁止されている財産があります。
債務者の最低限の生活を保護する意味で、生活に不可欠な衣服、寝具、家具、台所用品、畳、建具や、1か月の生活に必要な食糧および燃料、66万円までの現金、債務者の仕事に必要な器具や備品類などは差し押さえの対象外となると定められています。
また自動車を差し押さえる場合においては、動産執行ではなく「自動車執行」という手続きになります。
2. 強制執行の流れ
では、強制執行のなかでも利用されることの多い「不動産執行手続(強制競売)」と「債権執行手続」のおおまかな流れをみていきましょう。
(1)不動産執行(強制競売)の流れ
債務者などが所有する不動産を強制執行の目的にするときには、主に次のような流れで進められます。
①申し立て
不動産執行の申し立ては、強制執行の目的不動産の所在地にある地方裁判所(執行裁判所)に、執行文が付与された「債務名義」を示して書面で行います。また、不動産執行の申し立ての際、裁判所が定めた金額の予納金と申立手数料を納付します。
不動産の買受可能価格で手続きの費用および申立債権者に優先する債権を弁済した金額がゼロもしくはマイナスとなってしまう場合には申立債権者自身は弁済を受けられないため、執行裁判所から通知されます。その場合は「無剰余執行の禁止」の規定によって執行手続きは取り消しとなってしまうため注意が必要です。
②競売開始決定
裁判所は、競売に必要な要件が満たされていると認める場合には、競売開始決定をします。原則として、主な要件は、①執行文が付与された債務名義の取得、②送達証明書、③予納金および手数料の納付です。
そして裁判所書記官は、目的不動産の登記記録に「差押登記」をするよう法務局に嘱託をします。
また債務者(および不動産の所有者)に開始決定がなされた旨の通知を送付します。
③売却基準価格の決定
裁判所に選任された評価人の評価にもとづいて、不動産の売却基準価格が決定されます。売却基準価格とは強制競売で不動産を購入する場合に目安とされる価格のことです。不動産鑑定士などが対象不動産を調査し評価価格を設定後、評価書を元に裁判所が売却基準価格を決定します。
決定された価格は、競売の期日とともに公告されます。
④競売
競売は、一定期間内に入札する「期間入札」の方法でなされます。
入札して売却許可を得た買受人は、裁判所が定める期限内に、決められた金額を支払います。また登録免許税などの費用負担は買受人になりますが、裁判所によって所有権移転登記が行われます。
なお売却許可決定後に、債務者や不動産所有者から競売手続きに関する異議申し立て(執行抗告)がなされることもあります。
⑤引き渡し・配当
買受人に不動産の引き渡しがなされ、差押債権者などに売却代金が分配されます。
(2)債権執行の流れ
債務者の給与や預貯金を強制執行の目的にするときには、主に次のような流れで進められます。
①申し立て
債権執行は、債務者の住所地(住所地が分からなければ目的債権の所在地。法人の場合は本店所在地)を管轄する地方裁判所(執行裁判所)に書面を提出して行います。
申し立てには、裁判所で書式を取得できる債権差押命令申請書や執行文の付与された債務名義、資格証明書、手数料としての収入印紙や郵便切手などの書類が必要になります。
その中でも、特に債務名義には注意が必要です。債務名義とは当事者間の権利関係を記した公証書類です。債権執行を行う場合は、債務名義を取得するための前提として民事訴訟や支払督促手続きなどを経なければなりません。
②差押命令
裁判所は、申し立てに理由があり、第三債務者による陳述によっても債権執行に問題がないと認めれば、差押命令を発します。そして第三債務者(勤務先や銀行など債務者に支払い義務がある者)と債務者に差押命令を送達します。
③差押債権者による取り立て・配当
差押命令が債務者に送達されてから1週間または4週間経過すれば、差押債権者は第三債務者から債権を直接取り立てることができます。取り立てが終わったときには、取立届を裁判所に提出します。
なお債務者が複数の債務を抱えている場合には、同時期に同一債権に差し押さえが重複することもあります。
このような場合には第三債務者は誰に支払ったらよいのか分からないので、供託することが認められています。供託がなされた場合には、差押債権者は裁判所から配当を受けることになります。
以上の通り、強制執行をするには、法的な書類を用意し、裁判所に申し立てをする必要があります。
もし強制執行をしたいとお考えなら、まずは法律の専門家である、弁護士にご相談されることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2023年05月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

裁判・法的手続に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2021年11月08日
- 裁判・法的手続
-
- 2021年05月25日
- 裁判・法的手続
-
- 2021年05月13日
- 裁判・法的手続