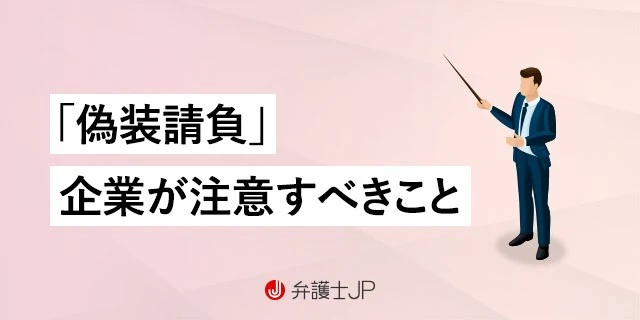
「偽装請負」にあたるケースとは? 判断基準について解説
業務を外部の業者に委託する場合に注意しなければならないのが、「偽装請負」です。偽装請負に該当した場合には、罰則が適用されるおそれもあります。そのため、委託者側の企業としては、偽装請負の当事者になってしまうことがないようにするためにも、どのような状態が偽装請負にあたるのかを知っておく必要があります。
今回は、典型的な偽装請負のケースと違反を防ぐための対策について解説します。
1. 偽装請負とは
偽装請負とはどのようなものをいうのでしょうか。以下では、偽装請負の概要と典型的なケースについて説明します。
(1)偽装請負とは
偽装請負とは、形式的には請負契約(業務委託契約)となっているものの、その実態が労働者派遣または労働者供給であるものをいいます。
労働者派遣事業を行う際には、労働者派遣法に基づき厚生労働大臣の許可を受ける必要がありますが、偽装請負では、そのような許可を受けていませんので、労働者派遣法違反となります。
また、職業安定法では、労働者供給が禁止されているため、職業安定法に違反するおそれがあります。さらに、偽装請負は、労働基準法が禁止する中間搾取の排除にも抵触するおそれがあります。
このように、偽装請負は、労働者派遣法などの各種法令に違反する可能性がある行為です。
(2)偽装請負にあたる典型例
偽装請負にあたる典型的なケースとしては、以下のものが挙げられます。
①代表型
代表型とは、発注者(供給先、派遣先)が業務の細かい指示を行ったり、出退勤などの勤務時間の管理を行うケースです。
②形式だけ責任者型
形式だけ責任者型とは、責任者がいても形だけのものにすぎず、責任者は、発注者の指示を労働者に伝えるだけで、実質的には発注者が指示をしているというケースです。
③使用者不明型
使用者不明型とは、下請け、孫請けが何重にも発生しており、労働者が誰に雇われているか分からない状態になるというケースです。
④一人請負型
一人請負型とは、供給元から労働者のあっせんを受けたものの、当該労働者との間で雇用契約ではなく請負契約(業務委託契約)を締結し、供給先の企業の指揮命令下で働かせるというケースです。
2. 偽装請負の判断基準
適法な請負契約であるか違法な偽装請負であるかの基準は、厚生労働省による告示(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準)によって具体的に公表されています。
下記1.~9.は基本的にすべての要件を充足する必要があり、10.と11.は、いずれか1つを満たせば良いとされています。
- 「業務の遂行方法に関する指示」を、受託者が自ら行っている。
- 「業務の遂行に関する評価等に係る指示」を、受託者が自ら行っている。
- 「労働時間の指示」を、受託者が自ら行っている。
- 「残業・休日出勤の指示」を、受託者が自ら行っている。
- 「服務規律の指示」を、受託者が自ら行っている。
- 「労働者の配置の決定・変更」を、受託者が自ら行っている。
- 受託者が、業務に要する資金を自ら調達し、支弁している。
- 受託者が、事業主としての民法・商法等の法律に基づく責任の負担をしている。
- 業務内容が、単に肉体的な労働力を提供するものでない。
- 受託者が、自らの責任・負担で業務上必要となる機械・設備・器材・材料・資材の調達をしている。
- 受託者自身の企画・専門的技術・専門的経験によって業務を処理している。
3. 偽装請負による法律違反を防ぐには
偽装請負による法律違反を防ぐためにも、企業には以下のような対策が求められます。
(1)請負契約についての正しい理解
偽装請負を回避するためには、請負契約や業務委託契約について、正しく理解することが求められます。そのためには、社員教育と環境整備をすることが必要となります。
例えば、社員教育では、請負会社の労働者に対して発注元の企業が直接指揮命令を行わないように指導し、環境整備では、請負会社の労働者と発注元の企業の労働者の働く環境を区別するなど物理的な距離を保つ対策が求められます。
企業によって求められる対策は異なってきますので、企業の実情にあった対策を実施するためにも、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
(2)契約内容の明確化
請負会社の労働者に対して、発注元の企業が指示や命令を行うと、請負会社の労働者が発注元の企業の指揮命令下にあったと評価される可能性があります。
そのようなことを防ぐためには、請負契約の内容を明確かつ詳細に定めておくことが大切です。仕様書などを詳細に定め、変更が生じた場合の手続きについても明確にしておけば、請負会社の労働者に対して直接指示や命令をするといった事態を回避することができます。
(3)業務実態のヒアリングを行う
経営陣が把握している状況と実際の現場の状況が異なることもあります。偽装請負を回避するためには、実際の業務実態を把握することが必要になりますので、定期的に現場担当者にヒアリングをするなどして、偽装請負の状態になっていないかをチェックすることが大切です。
- こちらに掲載されている情報は、2022年12月13日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

企業法務に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?




