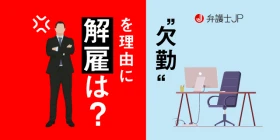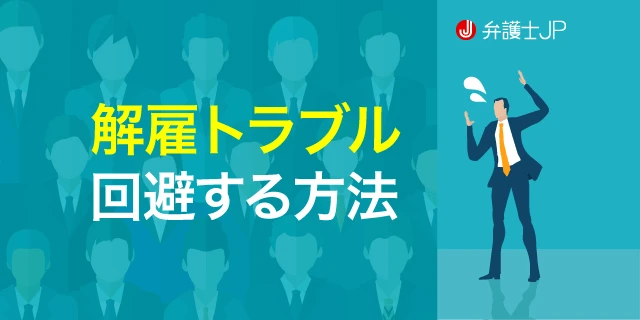
不当解雇の可能性も? 会社が知っておくべき解雇の種類と注意点
日本の労働法では、労働者の権利が非常に厚く保護されています。たとえ従業員の能力が低いとしても、使用者が従業員を安易に解雇してしまうと、後に法的なトラブルに巻き込まれてしまう可能性が高いです。そのため、解雇を行う際には、事前に慎重な検討を行いましょう。
この記事では、事業主の方が知っておきたい解雇の種類や要件・注意点などについてご紹介します。
1. まずは知っておきたい3種類の解雇
法律上、解雇には「懲戒解雇」「整理解雇」「普通解雇」の3種類があります。
(1)懲戒解雇
「懲戒解雇」とは、従業員の就業規則違反などを理由として行われる、懲戒処分の一環としての解雇をいいます。
懲戒解雇は、懲戒処分の中でもっとも重い処分に当たります。労働者の違反行為に対して、会社が重すぎる懲戒処分を課すと無効になってしまいます(労働契約法第15条)。
そのため、処分の重さに相応した重大な違反行為があったといえるかどうか、慎重に調査・検討することが大切です。
(2)整理解雇
「整理解雇」とは、会社の経営難などを理由として、人員整理の必要性から行われる解雇をいいます。
整理解雇の場合、労働者側に必ずしも非があるとはいえません。そのため、後述するように、「整理解雇の4要件」と呼ばれる厳しいハードルが会社側に課されています。
(3)普通解雇
「普通解雇」とは、懲戒解雇と整理解雇を除く解雇全般を意味します。
普通解雇を行うことができるのは、労働契約・就業規則上の解雇事由に該当する場合に限られます。
2. 合理的な理由のない解雇は大きなトラブルになる可能性も
「解雇」は、会社側の判断で労働契約を一方的に終了させる行為です。
労働者は、会社から支払われる賃金に生活資金を依存しているケースが多いため、突然解雇されると経済的に困窮する可能性があります。そのため、会社が合理的な根拠なく労働者を解雇することは、法律上「不当解雇」として無効とされています。
労働者から不当解雇の主張が行われた場合、解雇無効や損害賠償をめぐって大きなトラブルに発展するおそれがありますので、解雇の判断は慎重に行うことが大切です。
特に解雇に関する重要なルールとして、以下の点に留意しておきましょう。
(1)解雇予告義務・解雇予告手当支払い義務に注意
使用者が労働者を解雇する場合、30日以上前にその予告をするか、または30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う必要があります(労働基準法第20条第1項)。
つまり、どのような理由による解雇であっても、労働者の同意を得ずに即日で解雇を行うには、解雇予告手当を支払う必要がある点に注意しましょう。
(2)懲戒解雇・普通解雇は契約・就業規則上の根拠を必ず確認
懲戒解雇には就業規則上の「懲戒事由」、普通解雇には労働契約または就業規則上の「解雇事由」が存在することが、解雇の絶対条件となります。
懲戒事由に当てはまらないのに懲戒解雇をしたり、解雇事由に当てはまらないのに普通解雇をしたりすると、直ちに解雇が違法・無効となるので注意しましょう。懲戒事由や解雇事由の解釈などをめぐって疑義がある場合には、弁護士に相談することをおすすめいたします。
(3)整理解雇は4要件を満たす必要あり
経営難などによる人員整理を目的として解雇を行う場合には、以下の「整理解雇の4要件」をみたす必要があります。
<整理解雇の4要件>
①人員削減の必要性
人員削減をしなければ倒産状態に追い込まれてしまうなど、高度の必要性が要求されます。
②解雇回避努力義務の履行
役員報酬の削減・新規採用の抑制・希望退職者の募集・配置転換・出向など、解雇以外の方法により経営改善を試みたものの、なお整理解雇がやむを得ないと判断できることが必要です。
③被解雇者選定の合理性
整理解雇の対象者は、合理的な基準により、公平・公正に選定される必要があります。
④解雇手続きの妥当性
整理解雇を行うことについて、対象となる労働者個人や労働組合に対する説明を尽くすことが求められます。
このように、整理解雇は一朝一夕の判断で行ってよいものではなく、一定以上の準備期間をとって行うべきものであることを理解しておきましょう。
(4)「解雇権濫用の法理」について
さらに、すべての解雇に共通して「解雇権濫用の法理」が適用されます。
解雇権濫用の法理とは、労働契約法第16条に定められた以下の規定を意味します。
(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
特に懲戒解雇・普通解雇については、懲戒事由・解雇事由に該当するだけでは不十分であり、解雇の客観的合理性・社会的相当性の審査に耐えられるだけの解雇理由を提示できるかどうかがポイントになります。
上記の各ルールを踏まえて、従業員の解雇を検討中の事業主・経営者の方は、事前に弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば、本当に解雇をすべきかどうか、解雇をするとしたらどのようなプロセスを経るべきかなどについて、有益なアドバイスが得られるでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2021年06月23日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください

企業法務に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2021年06月28日
- 企業法務
-
- 2021年05月25日
- 企業法務